意味のない無駄な管理は今すぐやめたほうがいい
意外と、施工計画をただの提出書類と思われている方が結構いるので、その辺は注意して下さい。
工事において施工計画は核です!非常に大事です!
なぜなら、計画をもとに施工を進め、その都度変更があれば、変更施工計画書を作成し提出していきます。それを分かっていない監督は結構多めです。
そして、その中に「前回の工事でやったから管理」は入っていますか?恐らく入っていないでしょう。施工計画にも書かれていない管理を検査官が見るわけもなく、そのままスルーされます。
検査官が唸る管理は、当然の如く施工管理に記載され、それをしっかり施工している物です。その場しのぎの管理なんて評価されるわけもないんですよね~。
意味のない無駄な管理をするよりは、施工管理に書かれている(書いた)管理の精度をあげたほうが、よっぽど価値があります。
仮に、変更する前に現場の状況に合わせた施工管理が必要であれば、現場に応じて管理を行い計画変更を行う。検査官も検査時にはストーリーを大事にする方もかなり多いので、流れが見える現場と書類が好まれます。
ただし、元請監督の経験値や検査慣れ等も影響するため、補足管理というのもあります。メインの管理をするにあたり、どうしても分かりにくいため補足的に管理をするってことです。
こういった場合は、施工計画に載せにくいですが、検査官は好きです。目の行き届いた管理というわけです。さじ加減は難しいですけど(笑)。
検査官もプロなので、「なんでこの管理???」ってことはすぐに見抜きますよ!意味のない無駄な管理はやめて、今の管理の精度を上げていきましょう!
※この記事は、『新エンタの法面管理塾』の記事を再編集したものです。




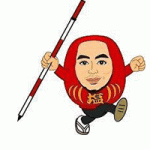


「他の業者がやっていたから」これ発注者の監督員から言われて施工計画に書かされました。管理効果が従来のものと重複するもので意味がわからなかったので聞きましたが「今までずっとそうだから」でした。
意味の無いものとすると人に寄りけりかもしれませんが、少なくとも説明できないもの且つ効果が無く点数もつかないもの、監理技術者は言いなりにならず本当にやめるべき。
発注者側に多々問題あり。
前例がないとか、前からやっているとか、仕様書にすら外れている管理をさせられる事も再々…。
て、検査では見られていない…。
このような、発注者の担当者レベルの思いのみで指示されても、受注者は受け入れるしかありません。これが、現実ですが。
発注者非難されているので1つ擁護を。管理項目で標準仕様書通りであれば問題ないと思っていませんか?仕様書のコピペだらけ。工事する目的は理解してますか?現場は1つ1つ違うんですよ。ってのを理解してない受注者が多すぎ。
それまんま発注者ではないでしょうか。
もちろん受注者にもいますが、その場合は、言ったところやったところでなおせと言われれば2度手間になるのであきらめている場合が多数と思います。
工事の目的を鑑みて、管理値を設定するのが受注者、というところに既に違和感を感じます。発注者がこういう風に管理してほしいって言う指標が仕様書な訳だから、そもそも仕様書に管理値が無い項目があること自体がナンセンス。
標準仕様書に管理値がないなら特記仕様書に記載するべきでは?って思うけど言えない。笑
前年度で竣工検査の時に、指摘されたとか
そんな感じの管理項目はありますね。
その検査官に当たった場合
急遽作成を、発注者から指示され
竣工検査で、褒められた事もあります。
なので、一概には言えないと思います。
本当に無駄な管理と思っているなら自分で変えろよになるね。
将来の業務を減らすために今苦労して施主や役所の担当、上席と協議するんだ。
まあ削減する場合ちゃんとした技術根拠で、責任持つ必要はあるけどな。
それが面倒で、まあ今まで通りでいっか。になるのも理解は出来る笑。
なんで前回はやったのかによる。その監督が理解していないだけで必要なのかもしれない。
少なくともここにいる人達は考えた上でやるやらないを判断しているのではないだろうか。
3のモノですが意外と返信があったので追記。
標準仕様書とはあくまで標準的に決めたモノです。擁壁、護岸工といって道路擁壁と河川護岸が管理値一緒でいいですか?道路は設計値を許容値以内で下回ってもいいかもしれませんが河川も下回っていいですか?その分溢れますよ?(そんなん大した量じゃねーよと言われそう 笑)まぁ結局は全てが標準仕様書に記載されてればいい話ですが。でも何ページになるのかな??
上記の様な状況であればやはり道路と河川で管理値を別に設定する必要があり、それは発注者(設計側)の意図を組み込むべきであると思います。
ページ数に関しては今の時代紙ベースで見る人なんて知れてるし、データにして検索かければなんの問題も無いですよ!
当然発注者もコンサルも気がつかないイレギュラーな物も出てくると思いますが、その場合は実際に施工、計画している受注者側からのアクションでいいと思います。ただその場合も受注者側から管理値をいくらにするっていう協議を出すのではなく、発注者側から管理値をいくらにして下さいって言う指示があるべきかとはおもいます。
擁壁、護岸工といって道路擁壁と河川護岸が管理値一緒でいいですか?
管理値が同じ仕様書にしてる発注者がおかしいでしょう。設計がおかしいのか、その資料をみておかしいとも思わずに発注した方がおかしいのかわかりませんが。河川で下回って溢れてもかまわない設計や仕様書にしてるのは発注者側ですよ。管理しなければならい項目は別途に特記仕様書に明記すべきでしょう?上の方の言う通りイレギュラー的なものなら仕方ないですし、あまりに無理なものは協議もしますが、だれが見てもおかしい設計や仕様書ならば発注前に気付くべきで、見逃したものは設計照査の時にでも発注者側からアクションあっていいぐらいですよ。