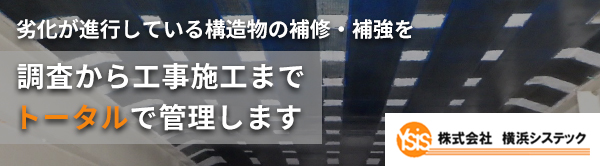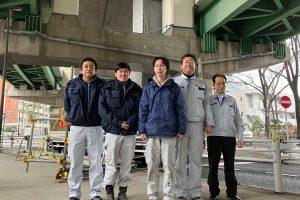土木未経験の新人さん、現場で勉強まっただ中
――実際に若い人を採用していて、学校でも職場でも土木未経験の人も採用していると聞きました。
重松会長 何人か採用しています。未経験の人は昨年7月、今年1月に1人ずつ採用しています。
五十嵐次長 私の現場にその二人が付いていて、今教えているところです。
――初めて土木に入職されたんですね。何が決め手になったんですか?
北原部長 本人に聞いてみましょう。
阿久津さん 自分は今までずっと接客業をしていたので、次にやる仕事はそれまでとはちょっと違う別ジャンルの仕事をやってみようかなっていうふうに思っていて、システックさんとお話させていただいた時に、雰囲気がいいなと思って、それで選ぶというか働かせていただくきっかけになったんですね。
重松会長 土木初めてで、なんか嫌だなとか、しんどいとかなかった?
阿久津さん 東北出身なので、暑さが結構つらかったです。今、寒い分には大丈夫なんですけれど。空調服とか涼しくなる服もあったので、そのおかげでだいぶ助かりました。
他にはそうですね、職人さんの指示出しとか、いま主にやってるのは施工が終わったところの検査とか、次施工するところの調査とかで、確かに聞いていた仕事の内容通りなんですが、狭くてほふく前進したりとか、かと思うと自分の上半身ぐらいの段差を登ったりとか、検査や確認の仕事をするためにそこに行くってだけでも大変で、そういうことにも体力使うんだな~と。材料管理の仕事もありますので、材料がまとまって来て、それを運んで検品して収納して、半端な量じゃないんです、重いし。でも皆さん普通に運んでいるので、自分はパワーがないんだな…と思います。

検査時に書類を確認する阿久津さん(右)と橋本さん
五十嵐次長 例えば、今日だと材料が1トン分搬入されましたが、トレーラーが来て、その1トン分の材料を1回駐車場に置いて、それを今度はじゃあ材料検収があるから並べなきゃいけませんよねって、そこの敷地にまた全部運んで、全部並べて番号振って、写真を撮り終わったら、今度またそれを全部倉庫に入れて…、材料の管理一つとってもなかなかの肉体労働なんですよ。
重松会長 今日も現場は職人さんにディスクサンダーで下地処理をやってもらっているんでしょ。粉塵まみれじゃない、嫌だなとかないの?
阿久津さん 最近ちょっと手が荒れてたんですけれど、いろんな方から教えていただいて、ケアすれば防げるって分かってきました。大変な時とかもあったりはするんですけれど、周りの方に支えていただいて、最初職人さんの怖いイメージがあったんですけれど、優しい方が本当に多いので、おかげでこう続けられてるというか、助かってる部分ではあります。

検査の業務にあたる阿久津さん
重松会長 橋本さんはどうですか?まだ1か月だと、そんなにね、感覚がつかめていないかもしれないけれど。
橋本さん 土木は初めてで、現場の仕事を想像してみたこともなかったのですが、面接で雰囲気がすごくいいなと思って、入社しました。こういう仕事もあるんだという驚きと、毎日毎日新しいことを知るので、すごくいい経験にはなっています。まだ1か月で、まだまだ基礎もないので、いまは半人前なんですけれど、早く1人前になるようまず仕事を覚えたいです。
重松会長 どうしても覚えるまで2~3か月はしんどいよね。体が慣れるとか、仕事のペースをつかむとか、土木とか補修とか専門的なことも覚えるとか、身につけることがいっぱいなので。だんだん基礎が身についてくると落ち着いてくるから。
いまは先輩の監督について、どんどん現場で覚えてもらっているんだけれど、会社として監督にも協力してもらってね、4月からは本社で座学をする学校もはじまるからね。知識も集中的に入れて、現場では先輩の監督が協力してくれてOJTで、どんどん身について力が付くからね。資格も取ってもらうし。
一通り身につけて資格を取ったら終わりってことではなくて、土木もね、実はいろんなイノベーションがあって、技術とか基準とかマニュアルとかね、新しくなっていくし、そういうことに対応した社内の知見の共有とかもね、必要ですから、学校は新人向けということでなく、全社的に活用しますから常設するからね。そういうことも念頭に、取り組んでもらえたらね。
「人は経費でなく資産」 資産価値を高めるためにスクールを常設
――4月から予定している学校はどのようなものですか?
重松会長 グループとして土木の知識を身につけ、知見のアップデートをして、技術士や土木施工管理技士をはじめとする各種資格の取得も促進します。私も先生役をしますが、他にも経験豊富な有資格者が何人もいますので先生役をしてもらって、全社的に取り組んでいきます。
「現場営業」にも通じるのですが、人は経費でなく資産ですから、会社としてリスキリングに積極的に取り組み、その資産価値を常に高くしておくことが、結果として会社に仕事が入ってくることにつながっていきます。
――資格取得だけでなく、恒常的なリスキリングなんですね。
重松会長 そうですね。土木業界も日進月歩ですので、基本に加えてアップデートもしていかないと。
メーカーさんと直接やり取りするするにしても、インフラの補修には土木の構造の知識と化成材も扱いますからケミカルの知識もいるので、その両方の知識がないとなかなか本質的な議論に至らないんですね。
加えて、新たな知見がでてきますでしょ、阪神大震災を経て耐震とか、近年の水害の激甚化で洗掘対策とか、塩害や疲労の影響で大規模更新とか、補修個所の再劣化対策とか…。基準やマニュアルも更新されますからね、新技術も開発されますし。
カリキュラムとしては、必要なものを全部ですよね。土木やケミカルの基礎知識、施工管理、品質管理、書類の見方、材料や工法、エクセルとかパワポ、守秘義務、実習、まだまだあります。ほとんどが定時内で、定時外は資格取得講座くらいですね。
――そういう社員教育というのは、業界では一般的なんですか?
重松会長 一次下請けでここまでやるのは珍しいと思いますね。
北原部長 元請けさんとかの大手は、時間を決めて人を集めて研修とか講習とかはやっていますけれど、一次下請けでというのは珍しいと思います。
人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!
「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、
こちらからお気軽にお問い合わせください。