参事官(イノベーション担当)とは?
国土交通省は近年、データとデジタル技術を活用したインフラ分野のDX(デジタルトランスフォーメーション)にチカラを入れている。
今年4月には、大臣官房に参事官(イノベーション担当)を設置。インフラDXを加速させるため、省内の分野網羅的、組織横断的な取り組み強化に乗り出している。
参事官(イノベーション担当)とはどのようなポストなのか。そもそも、インフラDXによってなにがどう変わるのか。当の参事官に就任した森下博之さんにお話を伺った。
インフラDXのスピードを上げるためのハブ的なポスト
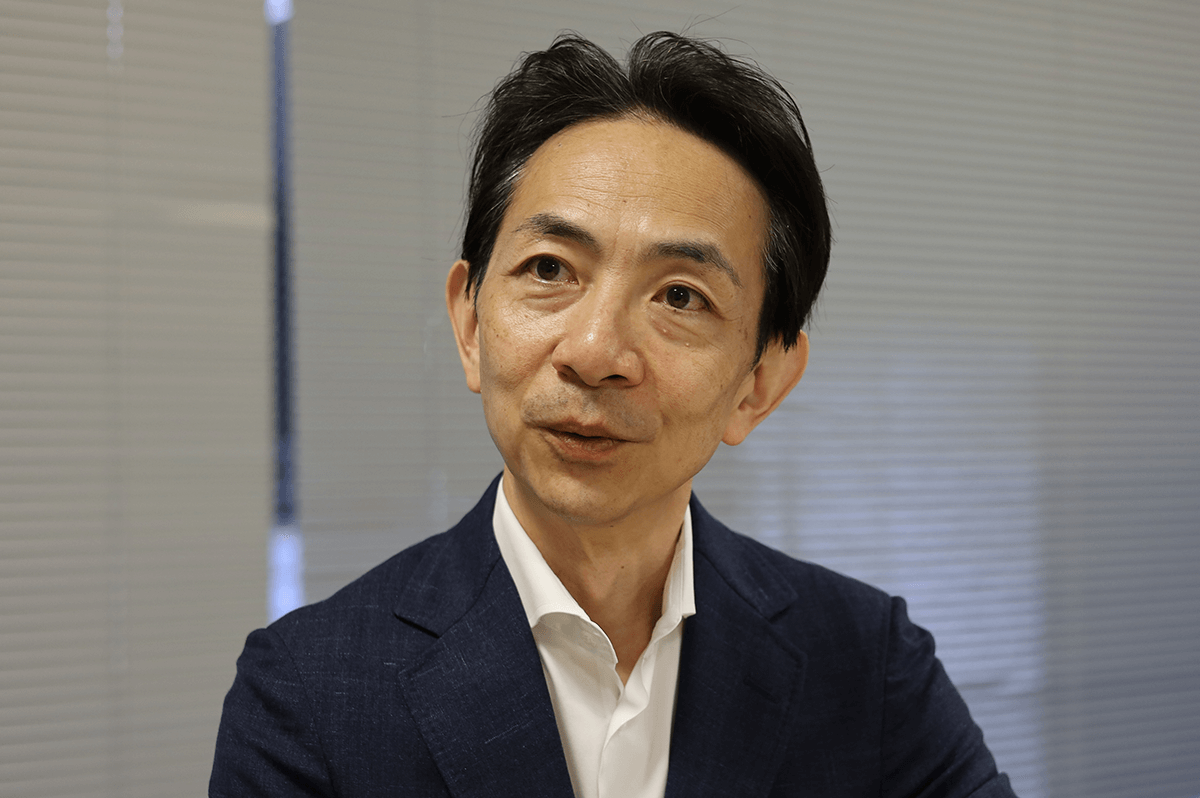
――参事官(イノベーション担当)とはどういうポストですか?
森下さん 国土交通省がインフラDXを掲げて、DXを進めるようになって2年ほど経ちましたが、これまでは道路や河川、都市や港湾空港といった省内の各分野ごとに独自に進めてきたようなところがありました。これを分野網羅的、組織横断的に進めようということで、今年4月に新設されたポストです。
省内のセクションごとにDXを進めていると効率が悪いので、知見や情報を共有して、横展開していく必要がありました。私の役割は、そういった知見や情報を集約することです。言わば、DXの取り組みのスピードを上げていくための、ハブ的な立場です。
とは言え、組織横断的な取り組みがなかったわけではなくて、省内にインフラDX推進本部を設置しています。各局からメンバーが集まって、省全体の方針などを決めたり、それぞれの取り組みなどを共有はしていました。このDX推進本部の機能をもっと強化することも、私の役割です。
――(インフラDX担当)ではなく、(イノベーション担当)となっているのはなぜですか?
森下さん 私が付けたわけではないので、本当のところはわかりませんが(笑)、インフラDXに限らず、デジタル以外にもイノベーションにつながるいろいろな役割を期待されているからだと思います。
機械と土木のハイブリッド職員
――デジタルには明るいのですか?
森下さん 私はもともと機械職として入省していまして、言ってみれば、機械と土木のハイブリッド職員なんです(笑)。ICT施工と言われる前、情報化施工と言われていたころから、デジタル技術を使った施工を担当してきました。私にとって、この分野はライフワークのようになっています。
――組織横断的に進めるという仕事は、DXよりもなによりも難しい仕事だと思われますが(笑)。
森下さん (笑)。DXの取り組みに関しては、権限を侵すとか領域を取り合うといったこととは無縁な世界なので、その辺はあまり心配していません。就任してまだ日が浅いですが、各局からの期待をヒシヒシ感じているところです。
ちなみに、国土交通省全体としては、インフラDXとは別の取り組みとして、働き方改革や職場改善といった取り組みも進められています。
インフラまわりの「作り方」「使い方」「活かし方」を変革する

インフラ分野のDXの全体像(国土交通省資料より)
――そもそもの話ですが、インフラDXとはどういう概念なのでしょうか?
森下さん 生産性向上を目的に平成28年度に始まったのが「i-Construction」ですが、どちらかと言えば、建設生産プロセスに主眼を置いていました。ICT施工をトップランナー施策と位置付けてやり始めたわけです。あとはプレキャストの採用、発注時期などの平準化、BIM/CIMの導入といった施策を進めていました。インフラDXはこのi-Constructionがベースになっています。
インフラDXは、i-Constructionを「もっと広げる」ことを目指した概念で、
- 「インフラの作り方」の変革
- 「インフラの使い方」の変革
- 「データの活かし方」の変革
を柱に据えています。「インフラの作り方」とは、基本的にはi-Constructionの取り組みを踏襲したものになります。
「インフラの使い方」とは、デジタル技術を駆使してインフラの潜在的な機能を最大限引き出す取り組みを指します。たとえば治水と発電を行うハイブリッドダムをイメージしています。
「データの活かし方」とは、国土交通データプラットフォームをハブとして、デジタルツイン化を進めることで、建設現場、建設業界にとどまらず、他の業界の方々にも建設に関するインフラまわりのデジタルデータを積極的に使っていただこうという意味です。








