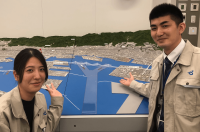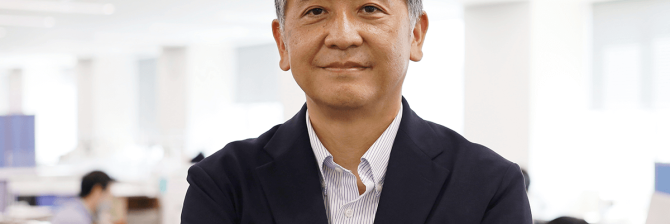われわれが災害対策をやってきた成果だけでなく、幸運もあって大きな災害になっていない
――企画部長としてのお仕事はどうですか。
奥田さん 昨年の6月末に就任して、まだ1年経っていないところですが、いろいろやっています。なにからお話ししましょうか。
――では近畿地方整備局の災害対応からお願いします。管内では近年、大きな災害は起きてない印象がありますが、どういうところに力点を置いて取り組んでいるのでしょうか。
奥田さん われわれがこれまでやってきたハード面の災害対策が功を奏した結果と幸運により、大きな災害に発展していないと見ています。災害につながりかねない、豪雨などの自然現象自体は、近畿はもちろん、全国至るところで発生していますから。災害化するのは、つまるところ、われわれの災害対策のスピードよりも地球温暖化のスピードが上回っているということだと考えています。そういう意味では近年敵である温暖化のスピードに負けないよう、もっともっと整備の加速化をしなければならない、そして責任は重いと感じてます。
近畿地方整備局では、南海トラフ巨大地震による津波被害が想定されていることを踏まえ、企画部内に平成29年度から局内各部を横断する津波対策連絡会議を設置し、情報の共有を図りながら、危機感が強く、やる気のある自治体を支援しています。
近畿地方整備局ではこれまで、L1対応のハード整備を進めてきたところですが、L1以上の津波対策、ハード・ソフト対策については、基本的に各自治体が実施する必要があります。
これらの対策と関係する近畿地方整備局内の部署はそれぞれ異なります。たとえば、まちづくりに関係する対策は建政部、道路に関する対策は道路部というように、所管が分かれているわけです。連絡会議を通じて、各部の対策などに関する情報を共有・連携しながら、局全体として自治体の津波対策を支援しているところです。
津波対策と言っても、堤防だけつくっておけば良いというわけではありません。ソフト面も含め、総合的な対策が必要です。自治体の危機意識が強く、自ら安全・安心な地域を作らねばという思いを持ち、自ら行動を起こす地域に寄り添い、技術面、予算面で支援したい、という思いを持って、取り組んでいるところです。
また、地震発災後の浸水対策についても、がれきなどによって道路が通行できない場合を想定して、排水ポンプ車などの事前配置計画を講じておくことで、最悪でも1ヶ月程度で排水を完了できるようにしています。どこが浸水するかは実際に起きてみないとわかりませんが、人が多く住む地域を優先してやっていくということで整理しています。最悪の想定で配置計画をつくっているので、実際はがれきが少ない場合もあるので、その場合はもっともっと早く排水できると思います。
――緊急輸送路の確保という観点で現在取り組んでいる事業としてはなにがありますか。
奥田さん 福井県の大野油坂道路、和歌山県の串本太地道路などがあります。いわゆるミッシングリンクの解消としての事業ですが、局として最重点事業になっています。そのさきにも兵庫県の大阪湾岸道路西伸部、奈良県の五條新宮道路などが控えています。
淀川を水素船が往来する時代が来る
――河川で言うと、淀川大堰に閘門をつくっていますが、船での資材搬送を視野に入れているそうですね。
奥田さん そうです。災害時に船で物資などを運ぶ目的も持たせています。大阪万博に向けた観光という目的もあります。
国がつくる広域地方計画というものがあって、私が近畿版の幹事長をしています。計画づくりの一環として、地域の代表的な企業の方々にインタビューするということをやっています。その印象としては、各社さんカーボンニュートラルに非常にチカラを入れられていると感じています。輸送で言うと、クルマよりも鉄道、鉄道よりも船が良いという考え方を持っています。船の燃料も油ではなく、水素にしていきたいと考えている会社もありました。
個人的には「また船の時代が来る」と痛感しているところです。淀川大堰閘門が完成すれば、長期的には、淀川にも物資を運ぶ水素船が入ってくるという気がしています。大阪はもともと水都と言われた都市ですので、船の時代の再来を期待しているところです。地元住民やメディアの関心も高いと思っています。
インフラDXの「すそ野」と「高み」
――管内の建設業の担い手確保についてどうお考えですか。
奥田さん 魅力ある職場環境にすることが重要だと考えています。そのためには、たとえば労務単価の見直しであったり、1人当たり仕事量の増加といった取り組みが必要になってきます。1人当たり仕事量の増加は、デジタルや機械などを活用したいわゆるインフラDXの取り組みということです。
インフラDXはまだまだ道半ばです。今まず力を入れているのはインフラDXに取り組む建設会社を増やすこと、すそ野を広げることだと考えています。加えてインフラDXをちゃんとやっている会社は褒め称えて、仕事が取れるようにする必要もあります。つまり、インフラDXに関しては、まずは「すそ野を広げる」、そして「高みを目指す」という2つの施策を進めていくということです。
近畿地方整備局ではインフラDX認定という制度をつくっており、認定会社が工事に手を挙げた際には総合評価で加点するということをやっています。正直に言って、認定基準は今はかなり甘めになっています。この認定制度がある程度浸透したら、高みを目指すほうに重心を切り替えていこうという考えでいます。
――今年度からBIM/CIMが原則適用になりましたが。
奥田さん BIM/CIMについても、まだまだ道半ばです。外注でやっているようではダメで、自分の会社でやる、つまり内製化しないと、受注者にとって儲けなどさまざなメリットは出てないのではないかと思います。