土木業界は、淀んだ沼のような世界
木村さん もしかしたらこれが一番の理由かもしれませんが、土木の世界が非常に保守だというのがありました。とくに国の研究機関の頭のカタさは異常です。たとえば、新しい技術を開発して、論文を書いても、なかなか使ってくれません。実績がないからです。ある程度の規模がある会社であっても、ちょこちょこ実績を積み重ねて、認められるためには、何十年もかかります。一大学教員が開発した技術ごときでは、認められるのは極めて難しい現状があります。とくに構造物関連の技術は。
土木業界は、官僚的な人間が牛耳っている世界なので、「事なかれ主義」が蔓延っています。まるで淀んだ沼のような世界です。ずっとそういう世界のままだと、おもしろくないですね。若い人もその世界から離れていくでしょう。
転身の理由としては、そんなところですね。ようするに、「大学の先生はもうええわ」と思ったということと、「こういう人間が一人ぐらいおってもええやろ」と思ったということです。土木の世界に一石を投じたい、新しい風を吹かせたい、「土木業界ってダイナミックやね」とか「内側から変わろうとしてるよね」とか思わせたい。そういう思いが重なって、決心した感じです。
大学教授の現役は辞めたとは言え、京都大学名誉教授、京都大学アフリカ地域研究資料センター特任教授という肩書きはあります。特任教授とか特命教授とか特別教授といった肩書きがありますが、これらは研究者名義の研究費を大学としてもらうために、大学に籍を残しておくということなんです。
「ごっつおもしろいことになりそう」という予感
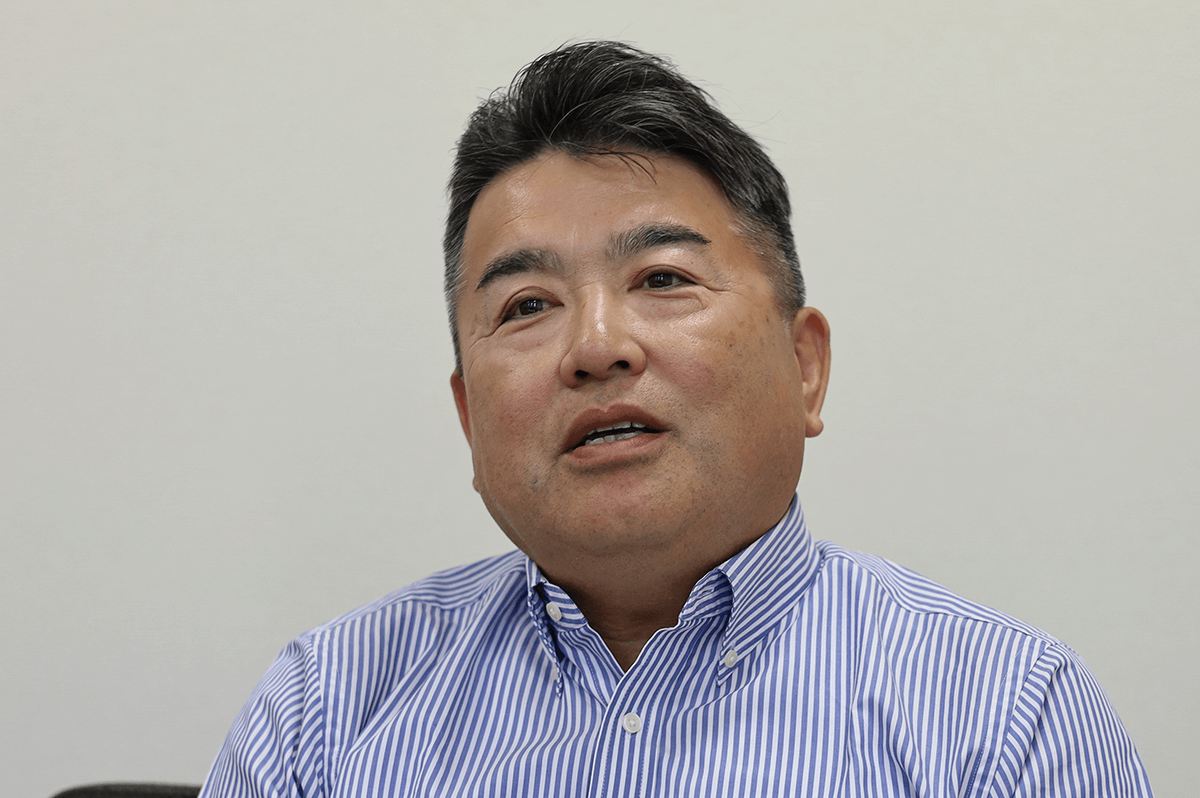
――今の仕事はどうですか?
木村さん それはまだわかりません。まだなにもやっていないからです。入社したのは今年の5月からなので、新入生みたいなものです。これからチカラを発揮していって、いろいろおもしろいことをやっていきたいと思っています。
昔からの知り合いからは「初めのうちはあまりアクセルを吹かさないほうが良いですよ」と言われていますし、あるゼネコンの知り合いからも「先生はあんま来んといてください」と言われています(笑)。そう言われると、ボクとしては「ごっつおもろいことになりそうやんけ」と予感しているんですけどね。ウラの存在として、発注者やゼネコンの人間なんかに「一泡ふかしてやろう」とアイデアを練っているところです(笑)。
せっかく工事会社に入ったので、実は現場監督をやってみたいと本気で思っているんです。実際に「現場監督やらしてくれよ」と言ったことがあるのですが、「専務が現場監督をやった前例はありません」と退けられました(笑)。
――大学教授と中小企業の役員とではかなり世界が違うように思われますが。
木村さん それはそうですけど、ボクは大学教授のころから、中小企業を応援するのが好きなんです。小さな会社と一緒に技術開発するのがとくに好きです。と言うのも、小さな会社は判断が早いからです。
ボクの研究スタンスは、「誰も考えてないことをやる。発想の転換をして、世間を驚かせる」というものです。そのためには、大きな会社だけでなく、小さな会社とも付き合うことが必要なんです。
大きな会社だからと言って、ものごとをちゃんとわかっているかと言えば、そんなことはありません。とくに施工のことなんて、なにも知りませんよ。施工のことを知らずに材料を売ったり、設計したりしているわけです。20年以上前からそういうことがわかってました。
もっと言えば、ゼネコンの人間も施工のことがわかっていません。施工管理はわかっていますが、実際の施工は専門業者に任せているからです。私は専門業者ともたくさんの付き合いがあるので、その辺の話はよく聞いています。ボンドエンジニアリングは小さな専門業者ですが、そういう会社だからこそ、あえて選んだところもあります。
私は大学の先生だったのですが、施工のことも現場の職人さんに教えてもらってかなり細かいことまで知っているわけです。なので、日建連がやっている土木賞の選考委員長をやっています。毎年数十ある土木のプロジェクトの中から施工プロセスに優れたプロジェクトを選ぶという、楽しい仕事です。八ッ場ダム本体工事とかいろいろなプロジェクトが受賞していますよ。
専門は地盤で、得意なのは杭基礎の水平抵抗
――阪神高速と共同研究されてきたようですね。
木村さん ええ、阪神高速とは、若いころから一緒にいろいろやっています。たとえば、構造物や地盤に問題があったときに対応したりとか、阪神淡路大震災で倒れた神戸線のコンクリート杭基礎を調べて、修理するかどうかの判断基準やその方法を提言したりしてきました。
ボクの専門は構造物基礎で、一番得意なのは杭基礎の水平抵抗です。普通は直径1mの杭なら1cmぐらいの水平変位での挙動を研究するのですが、ボクの場合は50cmぐらい変位したときにどうなるかを研究していたんです。つまり、地震でガシャガシャ揺れた後に、杭などの構造物がそのまま使えるかどうかを判定するといった仕事が、私の得意分野だったんです。神戸線の杭基礎を「使えます」と判定したのは私です。
阪神高速とは、新たな構造物の研究開発といった仕事もいろいろしてきました。たとえば、大阪湾岸道路西伸部で連続斜張橋の建設を進めていますが、私はこの事業の基礎の分科会の主査をやっていました。
杭基礎一体型鋼管集成橋脚基礎の大型振動台実験(木村亮研究室HPより)
新しいチャレンジにブレーキをかけられる
――西伸部の話がありましたが、仄聞したところでは、阪神高速はランドマークとして立派な連続斜張橋を架けたいと思っているが、コストや構造を巡って、国とモメているらしいですね。
木村さん この事業がヤヤこしいのは、阪神高速の単独事業ではなく、近畿地方整備局の道路と港湾との3者の共同事業だということです。阪神高速が新しい技術を入れようとしても、「すでに確立された技術があるのに、なんで新しい技術を使うんや」ということで、ブレーキがかけられます。「新しいことにチャレンジするな」と言っているのも同然です。ボクは非常に憤りを覚えました。
橋脚と杭基礎をフーチングレスにする集成橋脚基礎という構造を提案し、大型実験や数値解析でその有効性を検証してきました。実際の構造物として西船場での道路拡幅事業にも使いました。フーチングレスにすれば、構造的にシンプルにできるし、時間も金も節約できるんです。変形性能に至っては、こちらのほうが優れています。
ボクはこの技術を粘り強く提案してきました。しかし、国は取り合いませんでした。ある国の職員は「フーチングのない基礎なんか、聞いたことがない。気でも狂ったのか」と言い放ちました。新しい技術を採用すると言いながら、実際には新しい技術は採用しないわけです。
この「聞いたことがない」というのは良い言葉です。ボクはまさに、前例のない新しい構造を提案しているのですから。そもそも、どこかで聞いたことがあるような技術だったら、わざわざ提案したりしませんよ。
就職するなら、「とりあえずゼネコンに行け」
――若者の建設離れが指摘されていますが、どうごらんになっていますか?
木村さん 大学教授のとき、土木系の学生の就職担当を7年ほどやったことがあります。就職担当として、学生には「とりあえずゼネコンに行け」とススめていました。「設計をやるにしても、ゼネコンで施工を経験してからや」とも言っていました。初めからコンサルに行くのは、まったくススめません。現場を知らないと、設計はできないからです。
ゼネコンで10数年ぐらい現場を経験して、40才ぐらいでコンサルになるというのが、私の理想です。コンサルをやるにしても、どこかの企業に就職するのではなく、自分で事務所を構えて、自分でバリバリやるほうが良い。そんな感じで就職指導をしていました。
ついでに言うと、こういう学生がいました。「都市計画がやりたいんです。だから不動産デベロッパーに行きたいんです」と。それを聞いて、私は「君、ちょっと世の中見えていないのではないか」と言いました。なぜなら、都市計画は国や自治体が絵を描くものであって、不動産デベロッパーは、その計画で許された区域に高層ビルなり複合施設なりを建てるだけだからです。企業の伝え方や学生の受け止め方のところが、変に捻じ曲がっている感じがします。
都市計画をやりたいなら、国や自治体のほうがはるかにチャンスがあるわけですが、京大生には人気がありません。とくに京大から地方自治体に新卒で就職する学生は100人に1人と惨憺たるものです。
ボク個人としては、「そら行かへんわな」と受け止めています。「新しいことにチャレンジできないようなところに誰が行くんや」と思っているからです。普通の学生だったら、国土交通省なんかに行くぐらいなら、デベロッパーあたりに就職して都市開発でもやったほうがおもしろいと考えるでしょう。まあ、そこはそこで、捻じ曲がっているから、そういう選択になるわけですが。






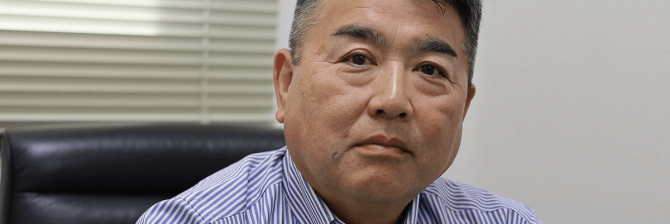

ボンドエンジニアリング株式会社が中小か
まあ定義的には中小なんだけど
学部で授業を受けていた頃から20年弱、久々に拝見したが、エネルギーに溢れているところは変わりなく、改めて尊敬。
現役の頃、あらゆる面で御指導頂きましたが有言実行で仕事を楽しく
やってける先生だと思います。特に若いころから国内外を問わずチャレンジされる姿は我々に勇気を与えて下さったと感謝致しております。
これからもお体に気を付けられてご活躍されん事をお祈り申し上げます。