「自分たちは良い仕事をしている」と思っているが、それが伝わっていない
――建設業界全体としてリクルーティングには苦労しているようですね。
木村さん そらそうでしょう。自治体の採用担当者なんかは、いまだに「ウチの仕事は言わんでもわかるやろ」という態度ですが、私は「そのおもしろさ、楽しさを示さないとわからんやろ」と思っています。
今の学生には、簡潔に、かつわかりやすく伝えないと、なにも伝わりません。就職の時期になると、企業や自治体が私のところに募集要項を送ってくるのですが、どれもPDFで20ページほどの文量があります。それを見るたびに、「アホか」と思ったものです。そんなものを大量に送りつけられて、誰が読みますかいな。文量はせいぜい1〜2ページぐらいで、仕事のおもしろさをしっかり伝えたいという思いに溢れたものでないと、学生には伝わりませんよ。こんなことをやっていては、自分で自分のカラを閉じているのも同然です。
難しいことを難しい言葉で説明するのは誰でもできることです。ボク自身、大学の教員として、難しいことを簡単に説明することを心がけてきました。採用活動にも同じことが言える、ということです。
そもそもなぜ、どこもかしこも新卒にこだわっているのか疑問です。たとえば、ある学生が「デベロッパーをやりたい」と言って東京に出ていったとしても、どうせ3年も経てば、地元に戻ってくるのがオチです。その戻ってきたところを狙えば良いと思うんですけどね。新卒を喜んで採用しているのは意味がわかりません。
もちろん、「新卒を採るのがアカン」と言っているのではありません。「どっかで仕事を3年経験したら採る」というのもあって良いと言っているのです。たとえば、国連なんかは新卒を採っていません。ある程度修行してからでないと、入れないんです。とくに役所の採用については、「それぐらいの気魄を込めて採らんかい」と言いたいところです。
自治体の採用試験の時期についても、ズレていると感じています。私は3年生の6月にやるべきだと考えています。現状と比べるとかなり早いですが、外資系の企業だと、3年生の夏のインターン終わりで内定を出しているので、それぐらいに試験をやってもべつにおかしくはないと思っています。就職戦線があらかた終わった4年生の7月になって、「なんで今さら内定出して喜んどんねん」という感じがします。そういうことを指摘していたら、ある県庁なんかは、本当に試験時期を前倒ししました。
――つまるところ、切実さのあるなしですかね。
木村さん そうですね。切実に採用を考えているかどうかです。役所の連中は「自分たちは良い仕事をしている」と思っていますが、その良さを表現できていません。なので、学生には伝わっていなんです。非常にもどかしい状況です。これは土木業界全体に言えることですが、「自分たちが良いことをしているとして、それをちゃんと伝えられているんか」ということです。
誰がやるということではなく、一人ひとりの土木人、土木関係者がそれぞれで伝えていかなければいけません。後輩である藤井聡先生が「ももいろインフラーZ」をやっているのは、まさにこのためでしょう。
アフリカでパイオニアになるのはおもしろい
――アフリカでの活動について教えていただけますか。
木村さん 私の師匠にこう言われました。「一流の研究者というものは、難しい技術を駆使できるけども、簡単な技術も扱えるんだ」と。そう言った後、「どやお前、アフリカの貧困を救えるのか。大学の教員として、アフリカで通用すんのか」と詰め寄られたわけです。
それをきっかけに、アフリカでの仕事が始まりました。30年ぐらいやっていますが、研究の成果や高度な技術なんか一切使っていません。アフリカの貧困地域にそんなものは必要ないからです。今でこそ、少し必要になっていますが、基本使わないです。
最初アフリカの現地に行ったとき、道がボコボコで通れないのを目撃しました。アフリカの農村の道は舗装されていないので、雨が降ると、ドロドロになって、通れなくなるんです。「ウチらには技術も金もないけど、この道をちゃんと通れるようにしてくれ」と頼まれたんです。そこで、頭をひねって、人が考えつかないことを考えて、実行しました。ここに、アフリカでの仕事の醍醐味があります。
――学生時代にアフリカを自転車で回ったそうですね。
木村さん ええ、大学院のときに1年間休学して、自転車でサハラ砂漠を縦断したんです。
――そのことと研究者になったことは関係あるのですか。
木村さん いえ、ありません。ボクは子どものころは左官屋になりたかったんです。大学院を出たらゼネコンに就職して、海外でバリバリ仕事をしたいと思っていました。ところが、指導教授から「大学に残らへんか」と言われたんです。「この先生が言うなら、そうするか」ということで、大学に残ったんです。最初の10年間ぐらいは基礎的な研究や実験をやりました。修士課程を出て、博士課程には行かずに、助手をしながら博士号を取りました。当時はそれが普通でした。
博士号を取ったときぐらいのときに、「アフリカにJICAがつくったジョモケニアッタ農工大学というのがあるから、現地に行って教えてくれ」と言われました。それで短期専門家としてアフリカに行きました。それがアフリカとの関わりの始まりです。1993年のことでした。
普通の人はアフリカ行きをイヤがるのですが、ボクはもともと、冒険心があるので、「アフリカでパイオニアになるのはおもしろい」と思ってやっていました。「お抱え外国人学者」みたいな気分でした(笑)。毎年1〜2ヶ月間アフリカで教鞭をとってきました。今も関わりを持ってやっています。
アフリカでの活動を通じて、アフリカ人の研究者、技術者を育ててきました。その研究者にお金を配って研究してもらったり、いろいろやってきました。現地住民と一緒に、雨季に泥濘化する未舗装道路をなんとか通れるようにするプロジェクトも、その活動の中から生まれてきたわけです。
チャリティではなく、ビジネスをしてもらおう

ケニアでの道直しの様子(木村さん写真提供)
――どのようなプロジェクトですか?
木村さん 路盤として土のうを敷き詰めて、道路を整備するプロジェクトです。現地住民が人力で作業します。土を袋に詰め締固めると、構造的に強くなるのはわかっていたので、それをベースに未舗装道路を治しているわけです。アフリカの農村の道は舗装されていません。雨が降ると、グジュグジュに崩れてしまって、通れなくなるんです。現地に人力はなんぼでもありますし、道を通れるとなれば、彼ら自らドンドンやってくれるんです。
このプロジェクトを進めるために、「道普請人(みちぶしんびと)」というNPOを立ち上げました。チャリティみたいな感じでずっとやり続けていきました。アフリカだけでなく、東南アジア国々なんかでもやりました。
チャリティとして5年ぐらいやったころ、あるアフリカのJICAの職員から「いつまでチャリティをやるんですか」と訊かれたんです。それを聞いて、最初は「お前らもチャリティやないかい」と思ったんですが、その後、「そうか、世の中の人はチャリティだけやと、認めてくれへんのか。だったら、現地住民にビジネスをしてもらおう」と気がついたんです。
それで、道直しに携わった現地の人たちに、地元の建設学校で2ヶ月ぐらい勉強してもらって、政府から許可証をもらった上で、建設会社を設立してもらう、というスキームを始めたんです。政府からお墨付きをもらっているので、この建設会社には政府から仕事が与えられるようになりました。たとえば、ケニアでは、若い人たちがつくった新しい建設会社に対し、優先的に仕事を割り振るというルールがあります。
ただ、建設学校で学ぶには、20万円〜30万円ほどの金がかかります。この費用をNPOで負担するのはキビしいので、政府の人間と交渉した結果、政府から金が出る制度ができました。普通のNPOの代表だったら、政府は信用しませんが、大学の教授という肩書きがあったので、あっさり信用してもらえました。かりに500人の人間を学校で学ばせるとなると、だいたい1億円ぐらいの金が必要になりますが、それぐらいの金だったらアフリカの政府でも出せるわけです。
最初のうちは、土のうによる道直しの仕事ばかりでしたが、そういう建設会社がどんどん増えていくと、建設会社の技術レベルも上がって、地方政府が普通の道路工事や水路工事を発注するようになりました。
小さな建設会社がたくさんないと、国力は上がらない
木村さん 日本は災害が多い国ですが、リカバリーするチカラがあります。それはなぜかと言うと、全国津々浦々に建設会社があるからです。その中でも小さな建設会社があるからこそ、リカバリーできるわけです。逆に言えば、小さな建設会社がないと、災害が起きたときにすぐにリカバリーすることはできません。
ボクは、アフリカの政府の人間に対し、「小さな建設会社をたくさんつくらないと、国力は絶対に上がらない」と言っています。ボクはこれこそが、本来の政策提言だと考えています。「貧困を削減するべきだ」とか「若者に仕事を」とか、そんなお題目を百万回唱えても、なにも起こりません。具体的になにかをつくり、具体的になにかをやらなければなりません。
NPO道普請人は、これを世界中でやろうとしているんです。この活動は2005年から始めて、現在31か国で250km弱の道を直しました。日本発の国際NGOとして2万5千人に土のうによる道直しの方法を教えています。
人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!
「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、
こちらからお気軽にお問い合わせください。






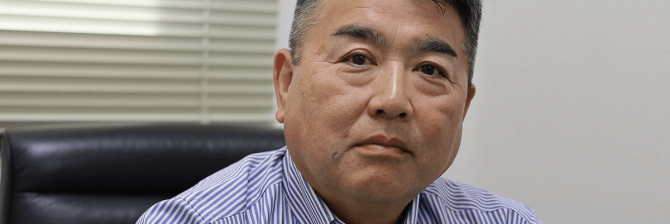

ボンドエンジニアリング株式会社が中小か
まあ定義的には中小なんだけど
学部で授業を受けていた頃から20年弱、久々に拝見したが、エネルギーに溢れているところは変わりなく、改めて尊敬。
現役の頃、あらゆる面で御指導頂きましたが有言実行で仕事を楽しく
やってける先生だと思います。特に若いころから国内外を問わずチャレンジされる姿は我々に勇気を与えて下さったと感謝致しております。
これからもお体に気を付けられてご活躍されん事をお祈り申し上げます。