書類のフォーマットを統一化しないと、ビジネスとしてスケールしない
――シェルフィーは当初、建築関係の内装マッチングアプリ事業を手がけていたということでよろしいでしょうか。
呂さん そうです。建築のイメージと言えば、安藤忠雄さんや隈研吾さんをはじめとする建築家が最初に浮かんだので、最初は建築設計に携わる人々に向けたマッチングサービスを始めました。建築士が必要とする業者をマッチングさせるということです。
当時は、いろいろな会社に自分自身で足を運んで、売り込んでいました。お客様からは一定の評価をいただくものの、「あまり刺さらないな」という印象がありました。なぜだろうと考えているところに、「マッチングアプリを必要としているのは、設計会社ではなく、施工会社だよ」と言われました。
それを聞いて、「なるほど」と思いました(笑)。早速、設計会社から施工会社にピボットしたわけです。それからと言うもの、お客様からの引き合いが増え、売り上げも上がっていきました。
「これは成長するぞ」という感触を得つつも、もっと手前に解決しなければいけない業界課題があることに気づきました。それは、見積もりのフォーマットが各社バラバラだったことです。バラバラだと、しっかり読み込まないと、比べられません。
マッチングサービスでは、WEB上で、複数社の見積もりを統一されたフォーマット上で簡単に見比べられることが重要です。一番低い見積もりは一番目立つ場所に表示されるといった機能が必要です。2018年ごろだったと思いますが、ステップ1からステップ2に行くためには、ステップゼロが必要だと気づき始めました。
そこで目をつけたのが、建設業界の書類でした。いろいろな会社にヒアリングしてみると、見積もり書類もバラバラでしたが、安全書類など他の書類も各社バラバラだったんです。見積もり書類は受発注のタイミングしか発生しませんが、安全書類は毎日のように発生する書類です。「そんなことになっているのか」と驚きましたが、フォーマットがバラバラな書類を統一すること、ここからやろうと考えました。
これをきっかけにして、安全書類をはじめ労務関係のことについて勉強するようになりました。CCUS(建設キャリアアップシステム)という流れがあることも知りましたし、働き方改革の中での建設業の位置付けについても知りました。そういったところから、安全書類をはじめとする書類業務の統一化、効率化に関するサービスを提供することで、建設会社の働き方改革に貢献するという方向性が生まれてきたわけです。これがグリーンファイルというサービスにつながるわけです。
安全書類作成という一番のストレスを解消したい
――マッチングアプリとグリーンファイルは、時期的に重なっているのですか?
呂さん 重なっています。グリーンファイルを始めるに際して、「こっちに振り切ろう」という判断をしました。
――グリーンファイルに全振りということですね。
呂さん はい。2019年当時の建設業界では、われわれのようなSaaS企業が流行っていました。そういった企業がなにを提供していたかと言えば、写真、日報、図面、チャットといったところでした。
ただ、私としては、この風潮に若干違和感がありました。と言うのも、こういったサービスはいわゆる「GAFAM」をはじめとする世界的な巨大テック企業群が、ケタちがいのお金を投入しながら、すでにサービス展開していたからです。すでに存在するサービスと同じようなサービスを、起業家としてわざわざやる意義があるのかと感じていたからです。
そもそも、既存のサービスより便利なものをつくれるのかというのもありました。そんなところで努力するなら、彼らにとって、グローバル展開できないサービスは合理的ではないので、やらないけれども、日本国にとっては、超必要なサービスをやるほうが意義がある、と考えたわけです。日本国のためのサービスは日本人がやらなければならないということです。建設業界の安全書類は、完全に日本だけのルールで縛られている分野なので、「われわれがやる」と考えたという面もあります。
さらに言えば、お客様から「一番ストレスがたまるのが安全書類だ」というお話を聞いたというのもあります。「モノづくりをしたいから建設会社に入ったのであって、こんな書類をつくるために建設現場に入っているわけじゃない。なんとかしてよ」とも言われました。安全書類をつくるストレスの圧倒的な大きさが伝わってきました。「このストレスを解消したい」というのも理由になっていますね。
安全書類ビジネスは明らかにブルーオーシャンだった
――「安全書類の領域はブルーオーシャンだ」ということで参入を決断したのですか?
呂さん そうですね。エンタープライズ向けの安全書類作成サービスはありましたが、地場の中小建設会社さん向けのサービスはありませんでした。この分厚い層向けにサービスを提供するのは、明らかにブルーオーシャンですし、社会的意義も大きいと考えました。
受け入れていただくために「浸透しやすさ、使いやすさ」には特にこだわっています。例えば、協力会社さんにも料金が発生すると「導入しても、ツールが浸透せず、結局費用対効果が感じられない」というのはあるあるです。そこで、当社のサービスは、協力会社は完全無料にすることにしました。また実際に使う事務員さんや職人さんの目線に立って、とにかく使いやすいサービスを目指しています。
実際に当社サービスを導入して解約するケースはほとんど発生していません。
――スーパーゼネコン以外の建設会社と協力会社という市場に目をつけて、そこに特化することで、既存サービスとの差別化を図ったということですかね。
呂さん そういうことですね。なので、弊社のサービスは、どちらかと言うと、地方に強いんですよ。
グリーンファイルのため、エンジニアなどのリソースを全振り
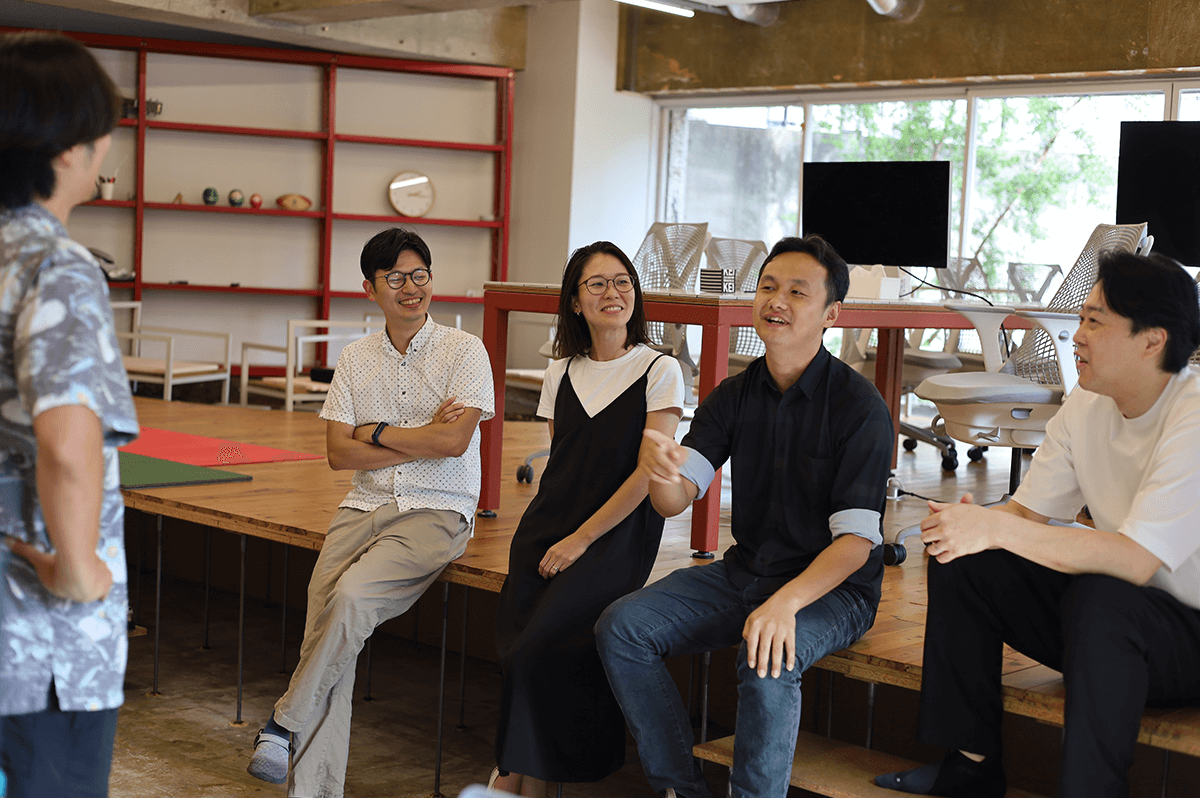
仲間とフランクに語り合う呂さん
――グリーンファイルに全振りしたと言うお話でしたが、社内のリソース、とくにマンパワーをどのようにコントロールしたか、教えていただけますか?
呂さん マッチングアプリを手掛けていた当時、社内にはけっこうな数のエンジニアがいましたが、2人を残して、残り全部をグリーンファイルに引き抜きました。マッチングアプリをやるつもりで入社したエンジニアばかりでしたが、フォーマットの統一化、デジタル化は最優先でやらなければならないという確信があったので、3か月ぐらいで一気にシフトしました。その後、優秀なビズリーダーも引き抜きました。
――最終的にマッチングアプリはバイアウトしたんですよね。
呂さん そうです。グリーンファイルに全振りするとは言え、会社を成り立たせるためには一定の収益が必要だったのでマッチングアプリはその後も、当社の15%ぐらいのリソースで運営していました。当時のマッチングアプリのスタッフは、疎外感を感じることもあったと思いますし、本当に大変だったと思いますが、よく頑張ってくれました。私は彼らをリスペクトしています。






