実際の建物と同様なモデルをコンピュータ内の仮想空間に再現するツール「BIM」をプラットフォームとし、さまざまなICTシステムと連携し、生産性向上や働き方改革に寄与する動きが活発となっている。特に、技能労働者不足や建設資材の高騰など、建設業界には不安要素もあり、各社ともデジタルの活用によってこの難局を乗り越える構えだ。
主に新潟県に地盤を持ち、全国展開している中堅ゼネコン・株式会社植木組(新潟県柏崎市)もいち早く、BIM/CIMに着手した。現在、設計段階でのワークフローの改善を目的にBIMを活用、意匠、構造や設備設計で各BIMモデルを作製、各モデルの統合を目指す。
中期経営計画の中にも「BIMの整備」も明記し、今や経営上でも重要なテーマだ。今後の動きとしては、設計・施工段階でのフロントローディングやICT建機のほか今後活用が考えられるAIやロボットなどの様々なデジタルツールなどとの連携も視野に入れる。
今回、植木組の建築設計部長の鳥羽寛氏にBIM戦略について話を聞いた。
1冊の本との出会いからBIMを導入
──2015年からと業界内でも早い時期からBIMに取り組まれていますが、どのようなきっかけだったのでしょうか?
鳥羽寛氏(以下、鳥羽氏) 私の経歴からお話させていただくと、新卒で植木組に入社して、それから3年間は現場監督を経験していました。最初の現場は旧建設省の工事事務所の管理棟や格納倉庫の工事に携わり、新入社員ではありましたが、S造・RC造・SRC造すべて担当させてもらいました。それからはコンクリート二次製品の工場や事務所を4棟施工して、湯沢スキー場のマンション棟の人工地盤の施工途中に社会人留学で大学へ入り直して、設計事務所へ出向することになりました。大学は意匠系を専攻していたので、社会人留学では構造系を学ぶことにしたんです。
以降は構造を中心とした設計畑を歩むことになったのですが、昇格試験のレポートを執筆中に、これからの設計分野ではどのような未来が待っているのかを考えている中で、(株)日建設計の山梨知彦氏が執筆された『BIM建設革命』という本に出会ったんです。
同書では「BIMとは何か」から始まっていたのですが、BIMの導入による生産性向上の効果に衝撃を受け、これから建築業界でも大幅に導入されていくと思いました。私自身、手書きからCADへと移行する時代も経験していたので、同じようにCADからBIMへと移行することもイメージしやすかったんです。
それから当時の上司に軽い気持ちで、「今後、BIMが本格的に導入される時代が来ます」と提案したら、「それならウチでもやってみよう」とトントン拍子で話が決まっていったのがきっかけです。
――BIMの導入を決めてからは、どのように動いていったのでしょうか?
鳥羽氏 まずは意匠チームでBIMを採用することにしたのですが、開始から数年間は部分的な3次元化レベルの活用に留まっていました。若手は吸収が早いので、BIMの使用頻度自体は高かった半面、個人の力量に任せていたことが思うように取組みが進まなかった要因だと思います。一方で、国土交通省が土木分野でCIMを積極的に採用する動きに連動して、同時期から土木技術部と技術開発部がCIMを積極的に取り入れており、建築設計部としてもBIMのスピード感をCIMと同様に早める必要がありました。そして、5年前に私が建築設計部長に昇格し、中期経営計画の作成にも参画するようになってから、BIMの本格導入を進めていきました。
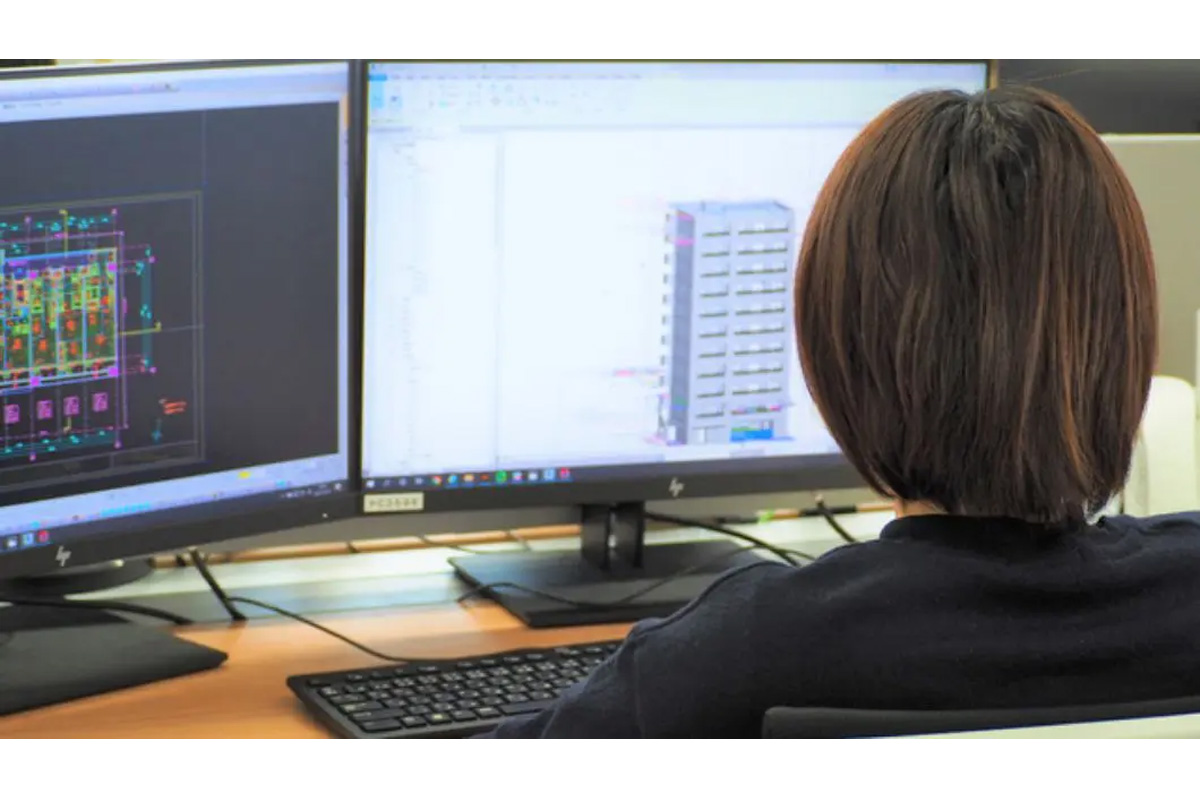
BIMモデルを扱う女性技術者
──現在の建築設計の体制は。
鳥羽氏 本社11名、東京本店5名です。私を除いて、意匠が5名、構造が3名、設備が4名、BIM担当が2名です。そのうちの1名をBIMのワーキングリーダーに任命して、意匠、構造、設備設計分野を横断的に管轄しています。









