国土交通省(四国山地砂防事務所)のご協力を得て、四国中央部の山奥、祖谷地区で動いている3つの砂防(地すべり対策)工事の現場を取材する機会を得た。砂防の現場ではなにをしているのかと言うより、砂防の現場ではなにを喜びとしているのかが知りたいというのが、今回の取材の動機となっている。
現場取材3発目(最後)として、徳島県三好市内に位置するヤナギ谷、ナカズ谷の2つの砂防堰堤工事を担当するエス・ビー・シー・高木建設JVの主任技術者の松岡洋介さん、現場代理人の梶浦智也さん両名に、工事の概要、施工管理上のポイントなどについて、お話を聞いてきた。(取材時期は2024年2月)
ヤナギ谷堰堤を受注した後、ナカズ谷堰堤が追加発注
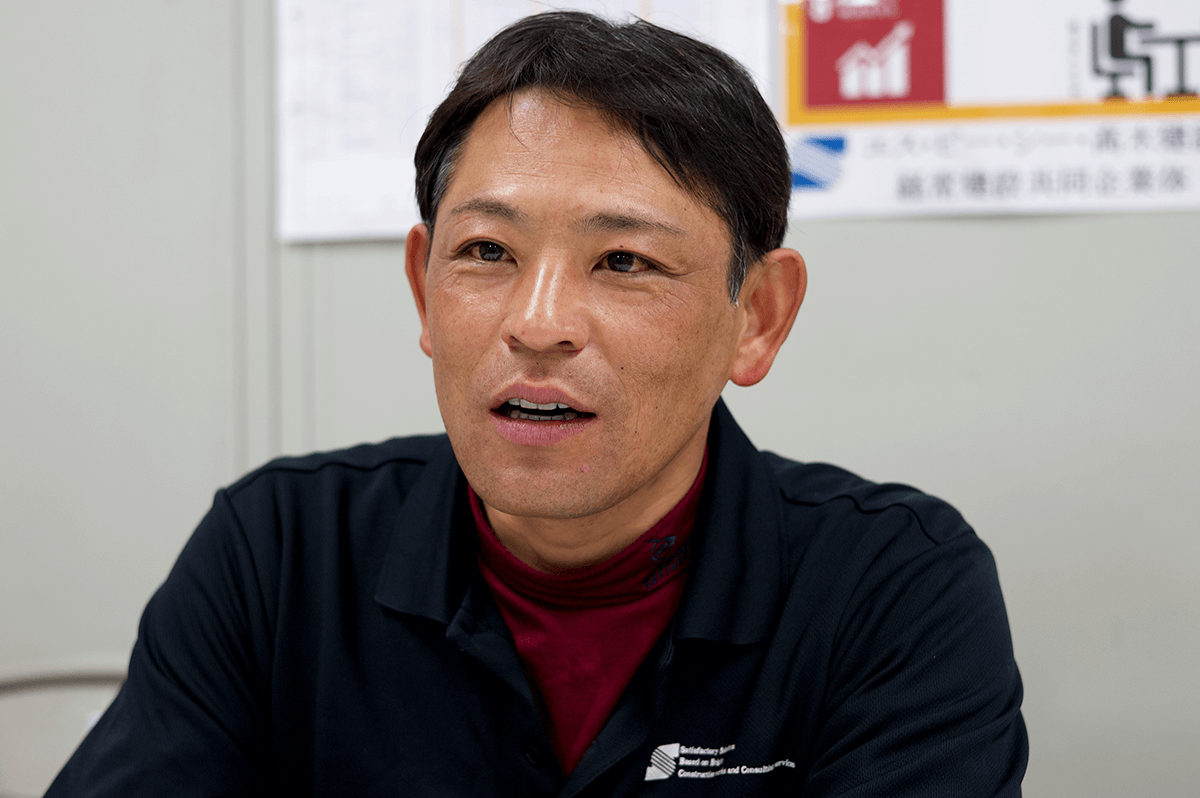
松岡 洋介さん エス・ビー・シー・高木建設JV 主任技術者(監理技術者)
――こちらはどのような現場ですか?
松岡さん ヤナギ谷とナカズ谷にそれぞれ砂防堰堤を施工している現場です。令和2年度からヤナギ谷の管理用道路が発注されました。2~3年度で管理用道路の完成。その後、令和4年度で堰堤工掘削・コンクリート打設(7割)完成となり今回が本堤完成となっています。令和3年度からはナカズ谷の砂防堰堤工事が追加になり、今年度は本堤工、側壁工、床固工などを施工しています。
――どちらの堰堤も令和5年度中に完成予定ということですか?
松岡さん ヤナギ谷について、堰堤本体工事は完了予定です。ただ、側壁工、床固工、法面工など沢山工事は残っています。来年度発注になります。ナカズ谷は、本体をはじめ、全ての工事がほぼ完了していて、あとは撤去作業だけです。
――JVを組んでいるのはなぜですか?
松岡さん お互いの技術力をアップさせるためです。
山をたった36m切り開くのに1年かかった
――施工管理上のポイントとしては、なにがありますか?
松岡さん ヤナギ谷の現場条件としては、まず、下に県道が通っているのですが、西祖谷につながっている道で、観光道路になっています。けっこうな交通量があって、路線バスも走っているので、通行止めにすることができません。堰堤を構築するには、36m上から山を削らないといけないのですが、下に県道があるので、どうやって県道への落石を防ぐのか、どうやって重機を運ぶのか、といった問題がありました。
施工に関しては、セーフティクライマー工法という、機械を吊り下げて無人掘削できる特殊なバックホウで坂巻施工しながらの施工でした。距離にしたらほんの30mほどなんですが、落石にはかなり注意し精神的に苦労しました。また観光道路で道が狭いので、ダンプの搬出入にも制限があり工程調整も苦労した感じでした。
――発注者などとの修正協議も大変だったのではないですか?
松岡さん そうですね。初期段階の設計図、施工計画などは、あくまで予想と言うか、机上のモノなので、現場条件、施工状況、天候の変化に合わせて、刻々と変わっていきます。なにか変化が起きた際は、そのたびに協議を行なってきました。
発注者である砂防事務所(祖谷詰所)との協議ということで言えば、自分としてはスゴくやりやすかったです。温かいと言うか、優しいと言うか、「なんでも言うて来いよ」という寄り添ってくれる雰囲気があるからです。おかげで、修正協議を含め、仕事が進みやすかったです。
松岡さんのおかげで、ボクのスキルが上がっている(笑)
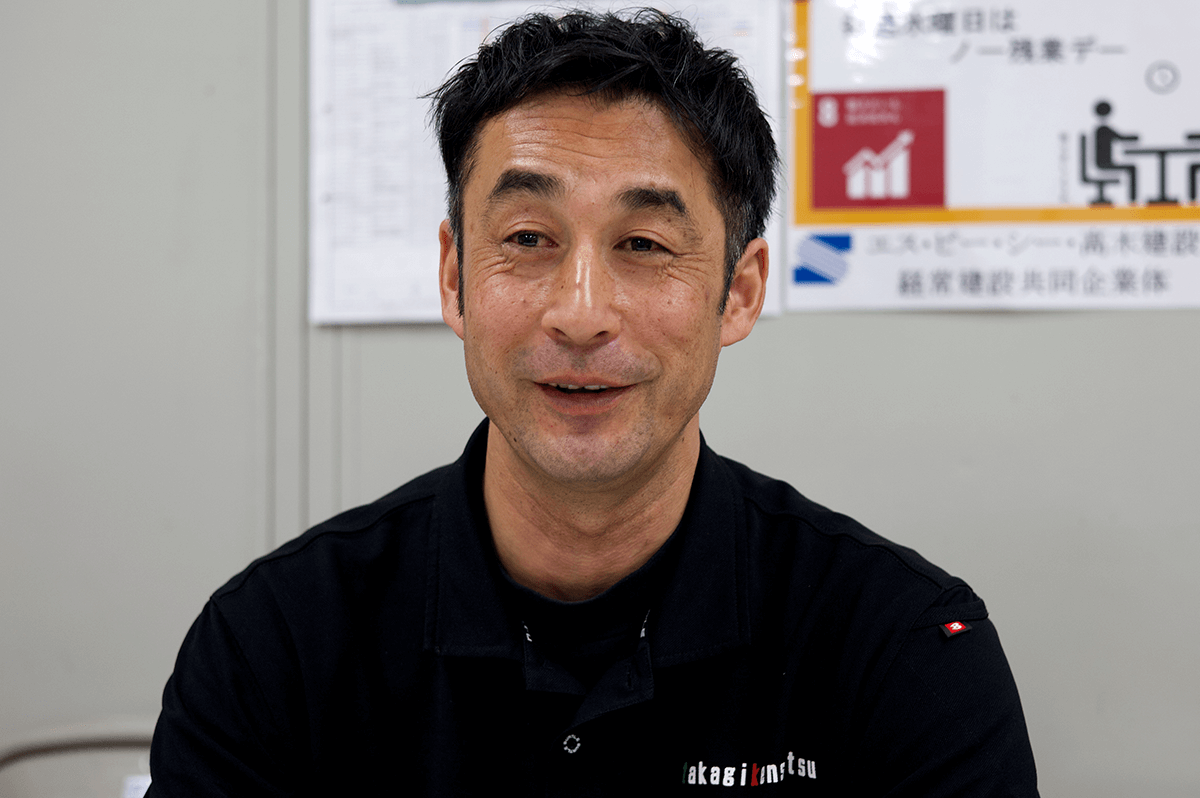
梶浦 智也さん エス・ビー・シー・高木建設JV 現場代理人
――梶浦さんは、こちらの現場にはいつから?
梶浦さん 2023年4月から現場担当になりましたが、国土交通省の砂防の仕事は今回が初めてです。松岡さんからいろいろ学びながら、仕事をさせてもらってるところです。すでにヤナギ谷堰堤工事は掘削も終わり、本堤工も7割完成していました。
――この現場ではどのような仕事を担当してきましたか?
梶浦さん ヤナギ谷工区は、堰堤はすでに14mまで完成し、今回残り4.5mの工事を担当させていただきました。材料やコンクリート打設を行うのも手間がかかりましたが、協議により、狭いヤードに50tラフテレーンクレーンを設置させていただき、工程通り完了することができました。
ナカズ工区については、令和3年度に4tクラスのモノレールを設置し、令和4年度に本堤掘削完了。今年度より本堤工コンクリート打設、側壁工、床固工、などナカズ谷工区については全て完成予定でした。大型重機も入らないダンプトラックも入らない状態でモノレールを見たとき、「なるほどな!」と感心されられました。
ただ、この方法だとコンクリートを打ち終わるのに時間がかかりすぎるので、どうやって工期内に終わらせるか、その計画を立てるのに苦労しました。モノレールを2路線ロスがないよう有効に使いながら工夫していきました。
――まさにJVを組んだねらいが実現されたカタチですか?
梶浦さん そうですね。スキルが上がっていっています(笑)。









