総合建設機械レンタルの株式会社アクティオは、ペーパレススタジオジャパン株式会社(PLS)と協力し、福井コンピュータ株式会社によるICT施工ソフトウェア教育用ライセンスの提供、株式会社NTTPCコミュニケーションズのクラウド型プラットフォーム実行環境を利用した、BIM/CIMの実益化のワンストップサービス「ICT施工トレーニングパッケージ」を、全国の建設会社向けに提供を開始した。
「ICT施工トレーニングパッケージ」は、ICT施工に必須の6つの要素(起工測量、設計・モデリング、AR/VR、マシンガイダンス、マシンコントロール、出来高・出来形管理)を、「e-Learningによる基本スキルの習得」と「BIM/CIMプロジェクトOJT」の2つの観点からサポート。コンサルティングと教育、教育環境(VDI・最新測量機器・ICT建機など)や実案件に向けた実践的なBIM/CIM活用をワンストップで提供する。
1年間のトレーニング期間を経て、「BIM/CIMを導入したいがどう進めればいいかわからない」「BIM/CIMの必要性は理解しているが、手をつけられていない」「ICT機材を導入しても、ちゃんと使えるか不安を感じている」との顧客の課題に対し、BIM/CIM導入による実益を最大限享受できるように支援する。
国土交通省は、安全で生産性の高い建設現場の実現に向けた「i-Construction 2.0~建設現場のオートメーション化~」を策定。生産性の向上と安全な作業環境の実現を目指し、2040年度までに建設現場の省人化を少なくとも3割、生産性を1.5倍の向上を目標に据える。一方、BIM/CIMへの取組みの恩恵を享受できる建設会社は少なく、より実務に即した実益的な取組みが今後の課題。とくに土木関連の建設会社のBIM/CIMの活用、ICT施工への取組みは急務であるが、導入への費用や活用に向けた実践的な教育、人的リソースの確保など、導入から活用に向けた取組みでは、一定の障壁がある。
今回、株式会社アクティオ レンサルティング本部営業次長の日南茂雄氏とペーパレススタジオジャパン株式会社(PLS)の代表取締役の勝目高行氏に話を聞いた。
トレーニングのパッケージ化で建設会社の負荷軽減
――このほど「ICT施工トレーニングパッケージ」をリリースされましたが、全体像を教えてください。
日南茂雄氏(以下、日南氏) ICT施工やBIM/CIMのメリットは施工段階で出やすいのですが、そのためには測量や設計データの3D化を展開しなければなりません。最終的にICT建機と連結する際には、フォーマットの変更などの細かい作業を行わなければなりませんが、1社トータルで展開していくにはハードルが高い。そこで我々は測量、データ作成や最終的にICT建機に連携させてパッケージ化したサービスをリリースしました。
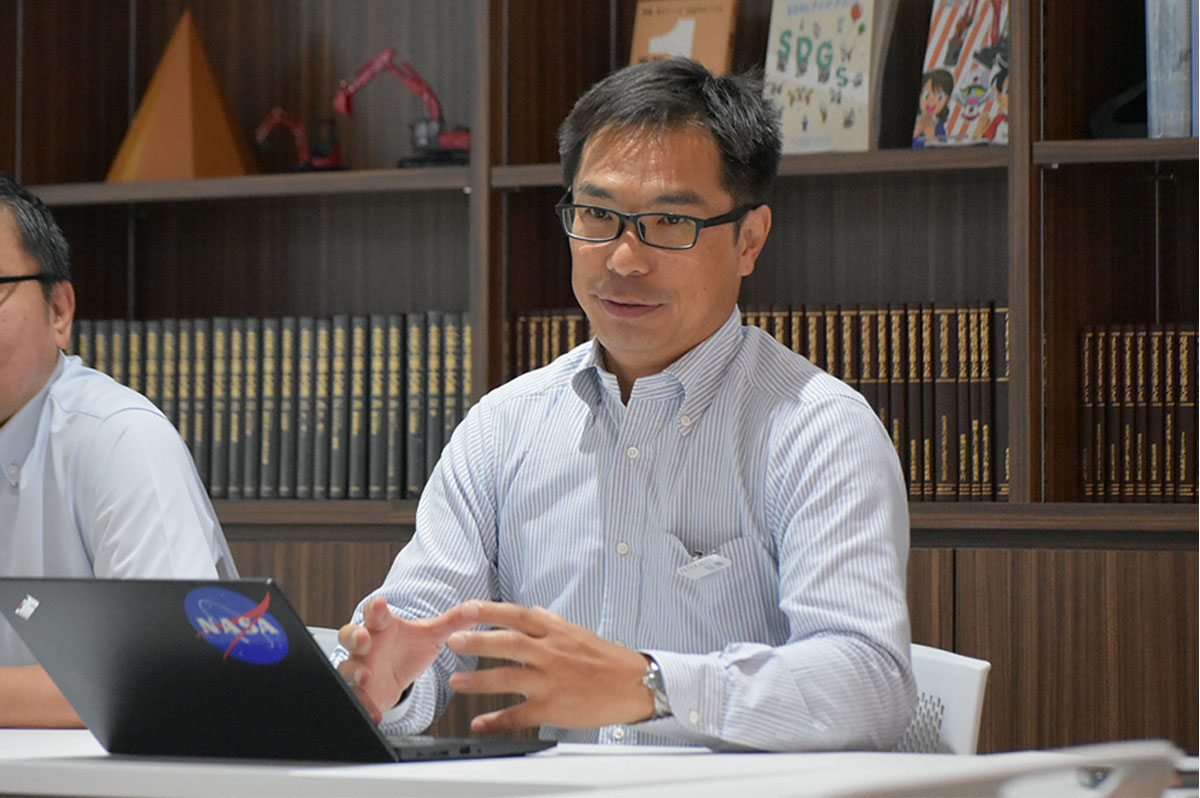
株式会社アクティオ レンサルティング本部営業次長の日南茂雄氏
――サービスとしては、BIM/CIMのコンサルティングとeラーニングによるICT施工の教育に分かれていますが、「eラーニング」ではどこからどこまでをカバーされているのでしょうか。
勝目高行氏(以下、勝目氏) PLSはアクティオとともに、ICT施工に特化した動画コンテンツをゼネコンなど向けに作成し、操作方法を座学で学んでいただきます。しかし、これだけでは身につきませんから、実際の現場で体験する教育も実施しています。機器やソフトウェアの基本的な操作から学ばれますから、ICT施工をまったく導入していない企業でも1年後には対応できるようになります。

ペーパレススタジオジャパン株式会社 代表取締役の勝目高行氏
――eラーニングのコンテンツはどのような内容ですか?
勝目氏 ICT施工に必須の6つの要素「起工測量」「設計・モデリング」「AR/VR」「マシンガイダンス」「マシンコントロール」「出来高・出来形管理」の6つのコンテンツに分かれ、全体の教育での組み立ては当社とアクティオが連携して行っています。
――現場ではどのようなサポート体制を整備されているのでしょうか。
日南氏 まず「起工測量」から習得し、基礎知識を習得した段階で、顧客は評定点や基準点を設ける準備を行っていただきます。ドローンで測量するため、アクティオから顧客に下準備の内容を説明。次にドローンを飛ばし、顧客に写真を見てもらい、解析は少し時間がかかるため、アクティオでも行いますが顧客もチャレンジされます。解析の方法は、アクティオが顧客にサポートする伴奏型で徐々に習得されていきます。
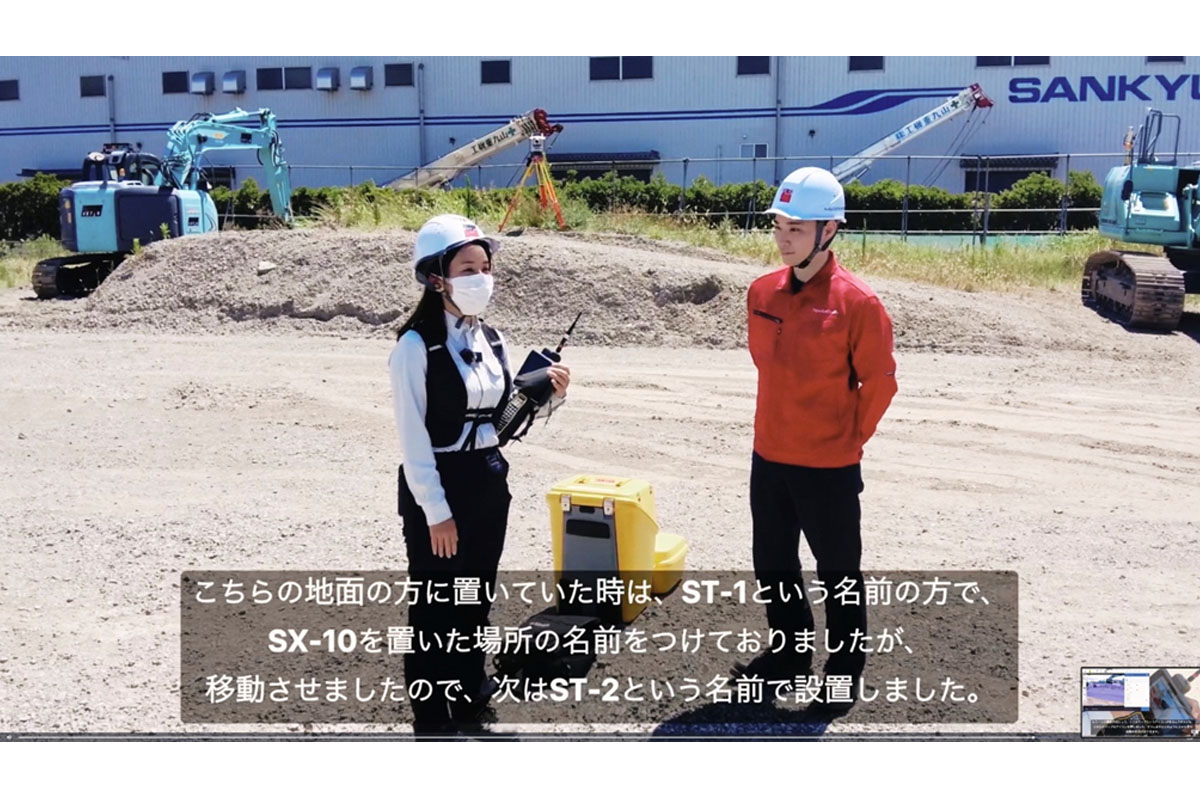
動画の一部の映像
――OJT によるBIM/CIMのコンサルティングは?
勝目氏 BIMツールでは、オートデスク社製品の「Revit」が中心に導入の支援を行っていきます。ただし顧客の要望に応えてさまざまなソフトウェアを組合わせ、福井コンピュータの協力を得て教育を展開中です。川上の設計段階は、「Revit」、土木系ソフトであれば、「Civil 3D」での操作教育を行っています。
――BIM/CIMの支援では他社も行っていますが、どのような点で高い効果が得られるでしょうか。
勝目氏 まずトータルでパッケージを提供している企業は我々以外ありません。他社では部分的なコンサルティング、一定部分のツールのみの提供、現場のみでの教育するサービスに留まっており、この点が他社と大きく差別化している点です。
国土交通省は、2023年度からすべての詳細設計・工事でBIM/CIM原則適用の方針を示し、詳細設計や工事では一部義務化され、BIM/CIMの必然性が日に日に増している状況です。建設会社もBIM/CIMを実施しなければいけないことは理解されていても、何から着手すればいいのかは不透明で、社内でBIM/CIM推進部を設けてもなかなか進展しない実情もあります。
我々が呼びかけているのは、「それならばアウトソーシングしてみてはどうか」ということです。社内のBIM/CIM推進の音頭から我々が担い、教育までお任せいただければ、BIM/CIMの実装は1年で進展します。
――アクティオがこのようなパッケージをリリースされた理由は?
日南氏 当社ではBIM/CIMのみのパッケージは従来から展開してきました。しかし、ICT施工で受注した企業が当社からICT建機をレンタルされるにあたり、「ただ建機をレンタルするだけではなく、測量関係からすべて面倒見てほしい」という要望も多く寄せていただいていたんです。2016年に始まった国土交通省のi-Constructionに対して、アウトソーシングだけで対応すると自社の人材は育ちません。ICTの活用には、やはり技術と人材を自社で蓄積していくことが大切ですから。
「起工測量から出来形管理まで」をアウトソーシングされている企業もあるかと思いますが、同じような金額を使うのであれば自社で内製化されるべきです。内製化を進めたうえで、一部は外注化するなど、取捨選択ができるようになれば顧客の業務の幅も広がっていくと考えます。
単独でBIM/CIMやICT施工が困難な企業に活用してほしい
――国土交通省は2024年4月に、「i-Construction 2.0 ~建設現場のオートメーション化~」を公表し、2025年度からICT施工を原則になるため、パッケージのオーダーが強く求められると思います。
日南氏 将来的にBIM/CIMデータが発注図書になれば、設計変更等で変更する図面も当然BIM/CIMデータの変更を行わなければなりません。そのときに会社として誰がどのように対応するかを決めていかなければなりません。仮に、外注化すると設計図書も読み込めず、現場監督も変更点が分からないとなれば、課題は山積していきます。2025年度に向けてできることから進めていくためにも、自社で内製化できる部分を増やしていくことが肝要だと考えています。
――どのような企業がこのパッケージを活用すると効果が表れるとお考えですか。
勝目氏 我々がパッケージを設計したときは、単独でBIM/CIMやICT施工が困難な企業。売上的には100~300億円の建設会社を中心に、50億円ほどの企業にも活用いただければと考えていますが、リリース時には大手建設会社からのお問い合わせが多かったですね。あるゼネコンのDX推進部から話を聞くと、60現場を担当していて既存の人材ではとてもカバーしきれないとのことで相談をいただいたことがありました。

――案件により金額も異なると思いますが、全体の費用感はいかがですか。
勝目氏 1社月額50万円で、依頼いただければプランニングから社内推進までを行います。ニーズに応じて、それに金額がプラスしていくことになります。
また、今回は特別に福井コンピュータから教育用ライセンスを提供いただいているので、まずは操作できるようになることから始めていただきます。基本的なことができるようになれば本格的にパッケージを購入いただき、案件の中から予算を組んでいただき、機器のレンタルも含めて全体を実行していきます。
権限とノウハウを若手に移譲すべし
――今、建設会社はICT施工やBIM/CIMの活用にあたって、何を悩まれているのでしょうか?
日南氏 ITに理解のある人材の枯渇でしょうね。たとえば、ICT施工を経験した現場監督個人にスキルは身についても、会社には水平展開されずに属人的なものに留まってしまっている。ICT建機やGNSSの測量機器などは安価なものではないので、会社全体として理解が深まっていかなければ、何をレンタルもしくは購入すればよいのかが分からず、導入も進んでいきません。
――いまのお話をより深堀りしたいのですが、建設会社側の問題点はどこにあるとお考えですか?
勝目氏 正直に申し上げると、組織が古い。BIM/CIMは新しいプロセスなので、それにあわせた組織づくりをしなければいけないはずなのですが、できていないんです。
――”変革”しなければBIM/CIMの導入・推進は難しい?
勝目氏 未だに「クラウドにデータを置いてはダメ」だとお考えの方もいますから。その固定観念から変革しなければならないと思います。

――それでは、どのような体制が望ましいと考えますか?
勝目氏 組織の”重心”を変えることが第一です。企業の組織体はシニアの方がメインですが、この層がICT施工やBIM/CIMをけん引していくことは難しいので、新たに若いマネージャーを育成していく必要があります。ただ、若手には権限がないので、組織やプロセスを変えるほどのパワーを持っていません。ですから、どんどんと若手に権限を委譲していかなければならないと考えています。
そのためには、今まで活用できなかった人材の登用を図っていくことも重要です。BIM/CIMの導入を開始されるにあたっては、大学で建築や土木を専攻した学部卒の人材を望まれる企業が多いですが、PLSがコンサルタントに入った建設会社では事務職で雇用した女性スタッフがすぐに操作できるようになった実績もあります。BIM/CIMのソフトウェア操作では一度、これまでの固定観念を取り払い、新しい層・人材に目を向けて、戦力化していくことが大切です。
また、重心を若手にシフトしつつも、ベテランのノウハウも承継していくことも重要で、これは急がなければなりません。そして、ノウハウを承継するツールとしてもBIM/CIMは非常に相性がいいんです。具体的には、若手がつくった現場システムに対して、ベテランが修正を促す体制が望ましいと考えています。このプロセスを繰り返すと、仮にベテランの方々がリタイアしてもノウハウが承継されるので、企業の持続的成長が期待できます。
属人化しているベテランのノウハウと権限を若手へと移譲していくことがこれからの組織づくりで重要だと考えます。
――BIM/CIMについては若手への権限移譲、三次元データをたたき台としてベテランが助言する体制とのことでしたが、ICT施工については。
日南氏 理想はICT機器やサービスをコーディネートする人材が現場に一人いるべきです。その方がマネジメントをし、具体的な機器やサービスの活用について主導する体制がよいと思います。
――アクティオとして、ICT施工やBIM/CIMの戦略は今後どのように進めていかれますか?
日南氏 BIM/CIMについては、アクティオとしてBIM/CIMデータの作成サービスについては考えていません。三次元データが当たり前の社会になれば、我々ICT建機レンタルにも紐づくのではないかと考えています。
――PLSとしてはいかがですか
勝目氏 設計のコンサルティングを得意としており、現場の効率化やICT化はアクティオと連携しています。国の方針としては設計を三次元データとする方針です。最終的には設計も施工も三次元データでつながり、PLSは両方を熟知しているので、正確に橋渡しできるようにパッケージをもとに顧客の改善を提案する方針です。
次に、大手建設会社であれば問題はないかもしれませんが、中小建設会社であればさまざまな特色を持つ案件ごとに1社単独で対応していくことは難しいので、その点を継続的に支援していきたいと思います。
人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!
「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、
こちらからお気軽にお問い合わせください。








