平面詳細図の失敗事例
代表的な例として、エントランスの建具がある。
特に、壁が石張りなどの目地のあるものの場合、ステンレスやアルミ、さらに鋼製建具や三方枠など様々な種類の建具が存在する。
そこで、平面詳細図だけを眺めていて陥りがちな失敗は、平面詳細図に記載されている建具の寸法は「内法寸法」である、ということだ。
どの建具も「H=2000」と記載されていれば、「揃っている」と感じてしまう。当然ながら設計図の寸法も同様に全て「H=2000」と記載されている。
では、同じ内法寸法の建具を配置することが本当に「揃っている」のか?
いや、私は今までに2度「揃っていない、失敗した!」と感じたことがある。それは、目地のある壁において、建具の枠の外面が揃っていないと美しく見えない、ということだ。
具体的には、建具の高さ方向の内法寸法の押さえている場所から、枠の上端までの寸法がそれぞれ違うということ。鋼製建具なら一般的に40mm程度ある寸法も、三方枠の場合は25mmしかない。つまり、建具の内法寸法を揃えることで、枠の上端に15mmの段差が生じてしまう。もし、2つの建具が近接していた場合などは、誰もが「揃っていない」と感じてしまう原因となってしまうのだ。出来上がったものを見て文句を言われるのは目に見えている。
つまり、平面詳細図をチェックする場合は、展開図を書きながら、高さの関係や見栄えを気にしてチェックを行うことが非常に重要である。私はこれを自分自身の失敗を通して学んだ。
「平面詳細図」と、日本人独特の「割付」の関係
平面詳細図の壁や床の内法寸法を考える時、切っても切れない考え方として、パネルやタイルなどの「割付」がある。パネルや石、タイルを張った時に美しく見えるように寸法を調整していくということは、平面詳細図をチェックしていく上で欠かせない考えである。
しかし、欧米などにはタイルなどを割り付けるという発想はない。タイルを端から張っていって最後に半端を入れておしまい、となる。決してタイルの寸法に合わせて壁をふかしたりすることはない。正直、羨ましい。
でも、ここは日本。だから、私は早い段階で、ある程度の割付を行いながら、平面詳細図のチェックを同時に進めていく。なぜなら、平面詳細図を確定した後に、石やタイル割りなどで建具を左右にずらしたいと言っても、工事の進捗具合によっては対応できない可能性があるからだ。
石などの仕上げ業者は、当然、躯体業者よりも後に決定することが多いが、なかなか業者が決まらなくて製作図による検討が出来ないという事情があるかも知れない。つまり、最悪の場合は、建具が取り付いてから石割りをチェックすることもあるわけだが、その時に「あっ、しまった!」と叫んでもあとの祭りである。私も同様の失敗をしたことがある。
このように平面詳細図というのは、現場の中の全ての納まりを考える、いわゆる「集大成」の図面である。実際に取り扱う知識も情報量も多く、ある一定の経験を積まないとチェックすら出来ない図面であるとも思う。が、同時に未経験の方でも、どんどん平面詳細図のチェックにチャレンジして欲しいとも願っている。

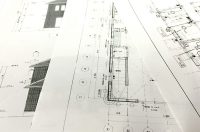




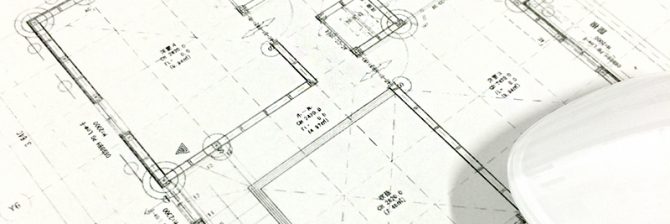

建築だけでなく、設備配管等を考慮した総合図を作ってからでないと、二度手間になると思います。
でも面倒だからか、そこまでつめずに、結果として壁や天井が出っ張ってくることがありますよね。
BIMで3次元の図面を書くようになると、その辺を考えなくて良くなるのでしょうか。