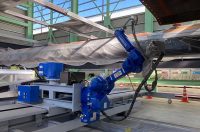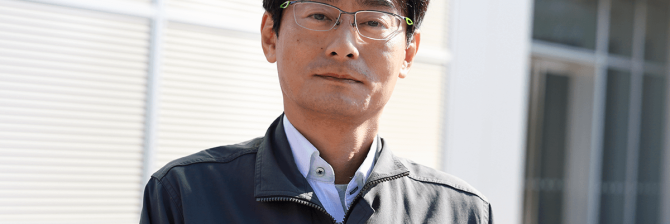フロアドクターの成功 現実的なロボット革命
山崎氏が特に誇るのは、物流倉庫のコンクリート床のひび割れ検査ロボット「フロアドクター」だ。200,000平方メートルもの広大な床を人間が検査するのは非現実的。顧客は「夜中にボタンを押せば朝に検査が完了する」全自動ロボットを期待したが、山崎はあえて「手押し台車型」を提案した。「自動化は魅力的だけど、現場の環境が整っていないと動かない。床が汚れていたり、物が散乱していたりするとデータが取れない」と彼は説明する。
代わりに、AR技術で仮想のガイド線を表示し、作業者がその線に沿って台車を押せば正確な写真が撮影できる仕組みを採用。「まずは床を綺麗にしましょう」と現場の運用改善を促した。最初は「こんなのいらない」と否定されたが、実際に運用するとその実用性が認められ、業界のデファクトスタンダードに。「ロボットそのものより、顧客が欲しいのはデータ。ニーズに応える設計が成功の鍵だった」と山崎氏は語る。
フロアドクターの成功は、イクシスの哲学を象徴している。派手な全自動化より、現場の現実を踏まえた実用性を優先。環境や運用を整えることで、ロボットの価値を最大化するアプローチは、インフラ業界に新たな可能性を示した。
i-Constructionとロボットの未来 人とロボットの共存を目指して
イクシスは、国土交通省のi-Constructionに即した建設現場のロボット活用を推進している。しかし、課題をこう指摘する。「ロボットは30年前から必要と言われながら普及しない。ロボットの性能の問題もあるが、現場や本社の環境や意識がロボットフレンドリーじゃない。ロボットリテラシーの低さもボトルネックだ」
2018~19年に点検要項が改訂され、ロボットでの撮影が認められたが、5~6年経っても浸透は遅い。「技術を向上させるだけでなく、現場環境の整備とリテラシー向上が必要」と強調する。イクシスは、大手企業と共同で3~5年後に必要となる技術の研究開発を進めつつ、今すぐ役立つITサービスやAI技術を段階的に導入し、ロボットが受け入れられやすい現場環境づくりを構築している。
ドローンについては、「参入障壁が低く、ボタン一つで動くので人気だが、重量制限や飛行時間の短さ、風への弱さでなかなか100点の顧客満足にはなりにくい。オペレーターも必要で省力化につながりにくい」と分析。イクシスは「地に足のついたロボット」で、ひと手間かかるけど確実なデータ取得を目指す。「顧客が欲しいのはロボットそのものじゃなく、データ。そこを見誤らない」と言う。
建設業界へのメッセージ 課題を分解し、未来を築く
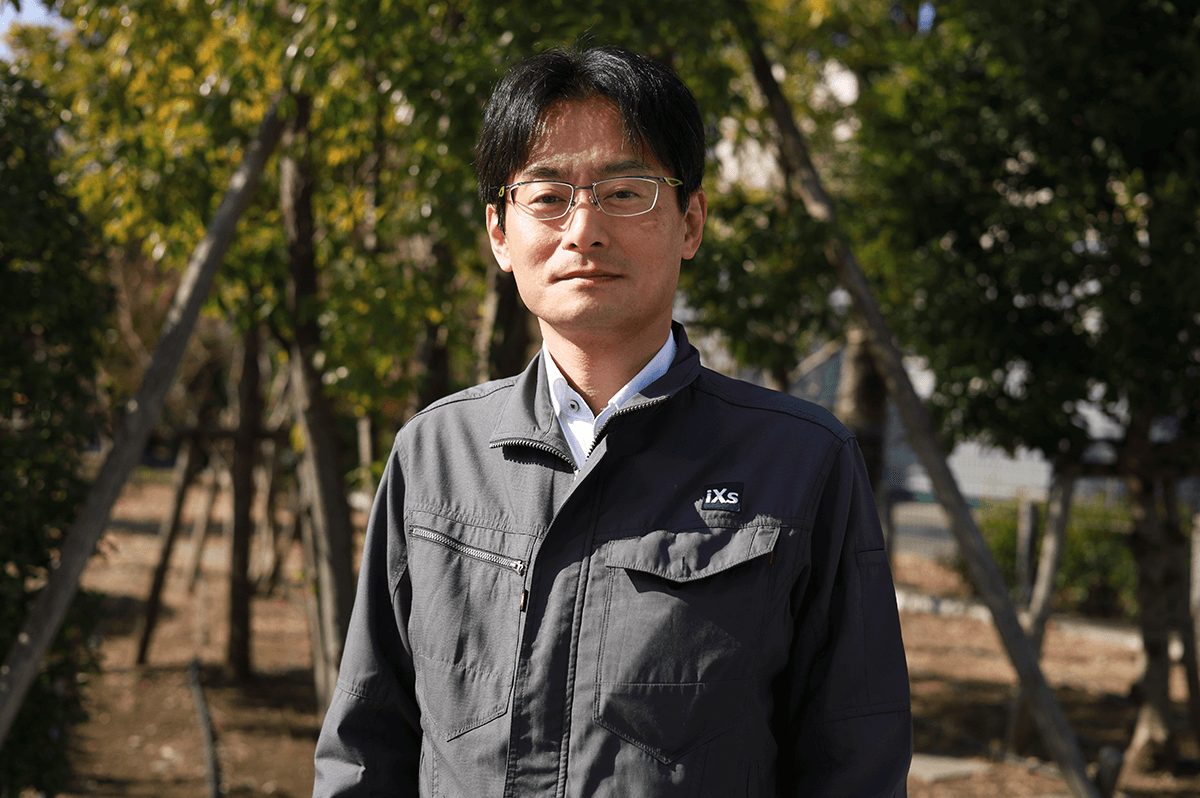
山崎氏は、建設業界に向けてこう呼びかける。「自動化やロボット化は正面突破ではなく、課題を分解して議論すべき。人手不足で熟練者が減る中、まだ人がいる今、ノウハウをシステムに蓄積する取り組みが急務だ。この数年が勝負。ぜひ一緒に未来を創りたい」。
ロボット愛から始まった山崎氏の挑戦は、インフラ業界に静かな革命を起こしている。ものづくりの楽しさと実用性を追求する彼の姿勢は、建設現場の未来を確実に変えていくだろう。イクシスのロボットは、派手さはないかもしれない。しかし、現場の課題を一つひとつ解決することで、インフラの安全と効率を支える縁の下の力持ちとして、着実にその存在感を高めている。
人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!
「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、
こちらからお気軽にお問い合わせください。