福岡女子大学で働くようになった理由とは
以前、九州大学土木系OG会「乙未(いつび)の会」に関する記事を書いた。なかなか興味深いお話が聞けたと思っているが、リモート取材だったため、いろいろ物足りなさみたいなものが残っていた。
「やっぱりリアルな取材がしたい」ということで、同会事務局を務める松永千晶さん(福岡女子大学准教授)に取材を申し入れたら、ご快諾いただいた。
ということで、ドボジョである松永先生に福岡女子大学で働くようになった理由、ふだんの仕事ぶりなどについて、リアルにお話を聞いてきた。(記事内容は昨年8月末時点)
そろそろどこか外に行こうかな
――福岡女子大学は歴史のある大学のようですね。
松永さん そうですね。2023年に創立100周年を迎えます。
――ただ、土木とは無縁そうですが。
松永さん 土木とは、まったくと言って良いほど縁がありません。私が所属する環境科学科は、理学系に環境や衛生、情報など、いろいろな分野が混ざった学科です。
――なぜ福岡女子大学の先生になったのですか?
松永さん 私自身、教員の公募に応募する前まで、福岡女子大学について、ほぼなにも知りませんでした(笑)。今思えば、私が通っていた九州大学箱崎キャンパスと福岡女子大学のキャンパスは近いですし、一緒のサークルなんかもあったようですが、ご縁がない状態でした。
私が福岡女子大学の存在を知ったきっかけは、夫でした。私の夫は、企業研修など人材育成の仕事をしているのですが、たまたま本学の女性トップリーダー育成研修に関わっていて、それで知ったわけです。夫からは「小さいけど、いい雰囲気の学校だよ」といった話は聞いていました。
福岡女子大学の前は、けっこう長い期間、九州大学で助教をしていたのですが、数年前から「そろそろどこか外に行こうかな」という気持ちがありました。そんなとき、たまたま福岡女子大学で教員の公募があったんです。ただ、それは住環境学分野の教員、建築系の科目を教えるものでした。
私の専門と分野は違いますが、まったくかけ離れているわけではない思ったのと、なにより職場が近いのに惹かれて、とりあえず受けてみました。そしたら、運良く採用されたという感じでした(笑)。
住環境研究室で土木計画学を教える
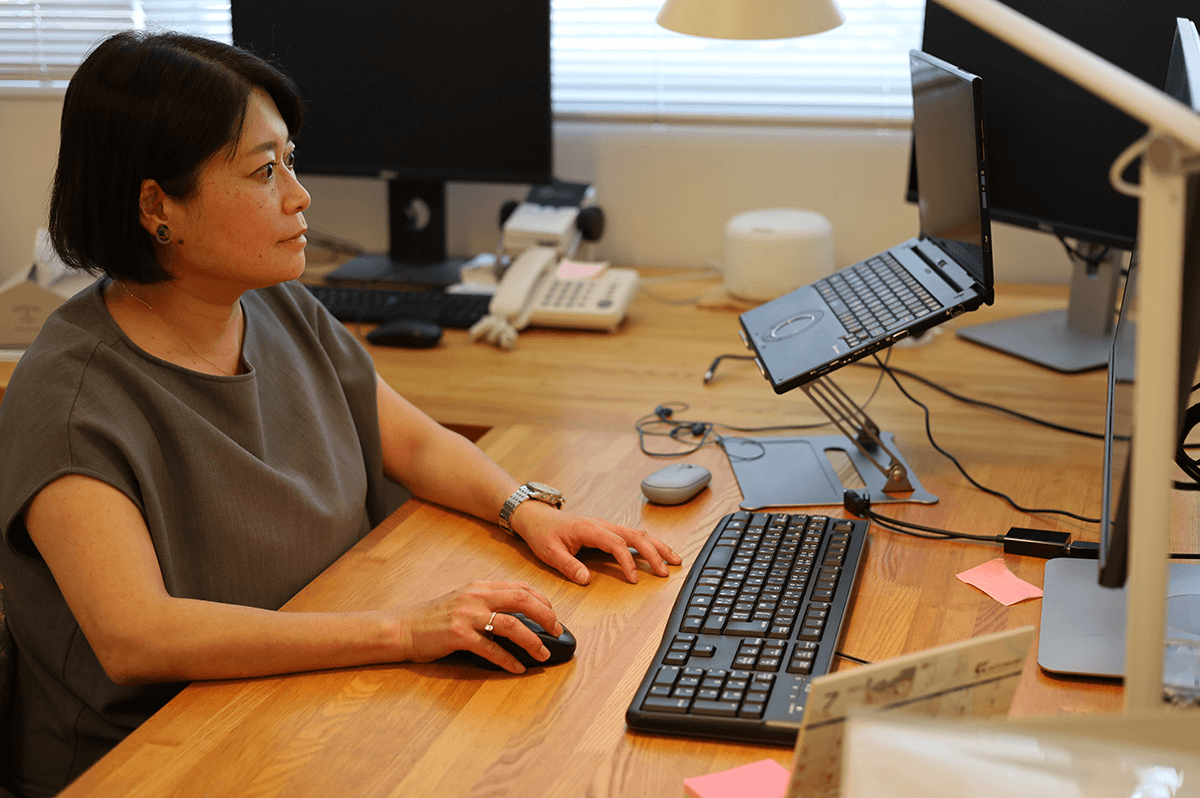
――大学のホームページの松永先生の教員紹介には、「土木計画学」と書いていますが。
松永さん 研究室の名称は、住環境のまま残しているのですが、私個人の専門分野は土木計画学なんです。それは正直に書いて良いはずなので、そうしています(笑)。住環境を広くとらえれば、都市環境といった領域も含まれるので、余計な混乱を招くよりは、住環境研究室のままのほうが良いと考えました。
――そこまでして土木を「主張する」必要もないと。
松永さん まあ、そうですね。私のもともとの専門は交通計画学でしたが、九大の助手時代の最後の5年間ぐらいは環境経済学の研究をしていました。退官された私の元ボスの先生のポストに環境経済学の先生が新しく着任されたので、一緒にやらせて頂くことにしました。振り返ってみれば、九大助教のころから、土木以外の分野に片足を突っ込んでいたような気もします(笑)。
そういう意味では、福岡女子大学に来たことは、自分の研究分野について、ゼロベースで考えを巡らせる良いきっかけになりました。また交通計画学をやってみようかなとか、いろいろ考えました。
ただそうは言っても、なにも知らない福岡女子大学の学生相手に、いきなり土木、しかも交通計画学を教えるのは、なかなか厳しいところがありました。そもそも、私が2020年4月に研究室に来たときの学生は、前の先生がいたときに研究室を決めてたので、学生と相談しながらなにをやるか決めていく必要がありました。
――前の先生は住環境を専門とする先生だったのですか?
松永さん そうです。建築関係の民間企業出身の先生で、光環境とか照明がご専門でした。私の専門分野とはまったくの別分野です。










土木の課題は、従来は人に頼りが外国人、低賃金。これからは機械化自動化の時代ですから、女性の新しい職場。
女性の性で業界の再編成。
子供達の為に宜しく。