コンクリート打設で支保工足場が崩壊する?
そして、実際に支保工足場の工事が始まった頃、様々な問題が発覚してきた。大きなトラブルは2つ。
まず1つ目は、支保工足場が外部足場とクランプでつながっている計画になっていたことだ。具体的には、片持ちスラブの先端部分の荷重を受けるための足場と外部足場が近接していたので、何気なく外部足場と支保工足場をクランプで抱かせてしまったのである。
支保工足場というのは文字通り、型枠支保工の荷重を地面までしっかり伝える役目があるので、ジャッキベースで建枠の荷重を受けなければいけない。しかし、足場の組み立て順序としては、建物下の支保工足場より外部足場の方が先に組むので、建枠にクランプを抱かしてジャッキベースが設置できないのは、必然的に支保工足場の方になる。
そんな感覚を持ち合わせていなかった私は、それに全く気付かず、存置期間の計算をしていない躯体の計画をしていたのである。実際に足場を組むタイミングになってから、鳶さんに「支保工足場でクランプ抱かせだったら、コンクリート打設したときに最悪崩壊するで!」と忠告されて、ようやく計画変更の必要性に気付いた。
幸いなことに、支保工足場を数字的には100ずらせば良く、ジャッキベースの不足分を別の工区で使用する材料で補うだけだったので、1つ目の問題はおおごとにはならなかった。
支保工足場に捨てコンクリートを打設しないの?
2つ目は、足場の足元について。
私は支保工足場の足元を、「埋め戻し土の上に、足場板2枚敷き」で計画していた。しかし、先程と同じ鳶さんから「支保工足場を受けるなら、足場の足元に捨てコンクリートくらい打設した方が良いよ」と忠告された。
こちらは今さら計画を変更する余裕はなかったため、「大丈夫ですよ。型枠大工さんも大抵埋め戻し土の上に足場板2枚敷きでやっているから」と忠告を無視した回答をして、支保工足場を完成させた。
ところが、型枠大工さんの支保工も組立て終わり、コンクリートの打設日がせまったある日、型枠大工さんの親分が現場にきて、作業性と安全対策について私に強い口調で苦言を呈した。
「何で支保工足場の足元に捨てコンクリート打設せんかったん?埋め戻してすぐの土だったら、絶対に足場が下がるぞ!一応パイプサポートのレベルは高めに設定させるけど、あとでそれ以上下がったら知らんぞ!」
私はかなり焦ったが、支保工足場の下に捨てコンクリートを打設するためには、いまから足場を一旦解体・撤去しなければならない。コンクリート打設を数日後に控えた現場の状態で、そんな手戻りが発生する指示を出す勇気は、私にはなかったのである。






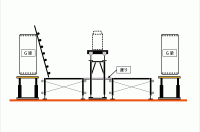



勉強になります。
技術面でも、コミュニケーションの面でも。
施工管理一級の勉強をしていますが、仕上げの職人は経験してきましたが、躯体については、見てはいますが、さっぱり分かりません。
本を読んでもチンプンカンプンです。
こうした失敗談は、初心者には非常に勉強になります。
感謝いたします。