技術的問題点の解決策「補助工法の検討」
まず、補助工法が必要な区間を把握するため、アイアンモール工法の施工機を1台追加し、No.17立坑からNo.18立坑に向かって推進してみました。
しかし、15m地点で先端部が計画線から下方にずれ、方向制御ができなくなったため施工を中断。そこで、補助工法区間はNo.18立坑から40mと定めました。
次は補助工法についての検討です。
補助工法の検討結果を表-1に示します。この結果、補助工法は効果の確実性から「高圧噴射撹拌工法(JSG工法)」を採用することにしました。注入材料は通常、孔壁安定材に使用しますが、今回は撹拌分離された砂土粒子を被膜で覆い、砂層のせん断強度低下を目的としたベントナイト溶液としました。
溶液濃度の検討に関しては、実機であるJSG施工機を使用し実地盤で行い、表-2の結果が得られました。そのため、互層地盤の均一性からベントナイト5%溶液としました。
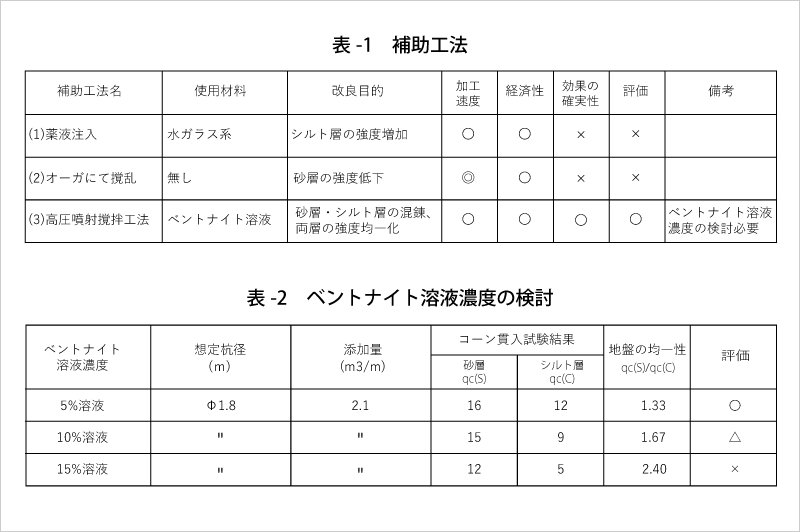
表-1 補助工法の検討 表-2 ベントナイト溶液濃度の検討
以上のとおり、施工仕様は、補助工法をJSG工法とし、施工延長40m、打設間隔1.5mで1列施工(想定杭径φ1.8mを考慮)、そして、改良高さは下水道管の外径(φ960mm)を考慮して、1mとし推進中心線で案分しました。
補助工法完了後、この問題の区間をアイアンモール工法によって推進しましたが、先端の制御も十分に行うことができ、到達時点での精度は下方へ15mm、左へ10mmと高精度で施工することができました。
「発想の転換」アイアンモール工法とJSG工法
この工事は、単純に考えると、アイアンモール工法では、施工不可能な地盤でした。
しかし、アイアンモール工法による適用地盤を十分に理解したうえで、「発想の転換」によって、補助工法として地盤改良工法を適用したのが、困難突破のカギとなりました。
本来、地盤改良工法は地盤強度を増す目的で使用されますが、上下の地盤を同強度にする(硬質砂層を軟弱なシルト層と同程度の低強度で均一な地盤に変える)ために、最適な施工機械と注入安定材を組合わせたことが、高精度の推進を実現しました。
しかし、いま振り返ると、転石等の障害物が存在した場合には、さらに工法の変更が必要であったとも考えられます。
以上、現場で困難に直面した際の、ひらめきの一助になれば幸いです。








素晴らしいです。経験の裏打ちが無いと、こういう発想は出て来ません。また、発注者や元請上司の承認・判断もスムーズに進んだ様で、羨ましい体験ですね。