横浜湘南道路トンネル工事の現場見学会
8月1日、横浜湘南道路トンネル工事の現場では「こども見学会」を開催した。小学生を中心に親子連れ約20名が参加し、シールドマシンの制御室を見学。発進立坑を地下まで降りて、工事準備中のトンネル内を歩くことが許された。

横浜湘南道路のトンネル構内


見学会で熱弁をふるう坪井所長

重機や高所作業車に試乗する子供たち
現場見学の前には、国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所の原田駿平計画課長と佐藤貴之工務課建設監督官の二人が、道路整備の概要やシールド工事の進め方などを、わかりやすく説明した。クイズあり、ユーモアありで、子供たちも興味津々だった。抜粋すると、次の通り。
- 日本の環状道路の整備は遅れており、3環状線の供用率はまだ約80%。一方、フランス・パリの環状線は2009年時点で85%完成し、中国・北京の6環状道路は2007年時点で100%完成している。
- 今では信じられないが、東北自動車道が全通していない1980年代は、翌日配達できない地域が多かった。1990年代から道路整備によって、翌日配達がほとんどの地域で可能になった。
- 道路整備の目的は、交通の利便性や物流効果のみではなく、防災面からも重要。もし東日本大震災のような大災害が発生した場合、三浦半島沿岸部の復旧は、横浜湘南道路を基盤とした「くしの歯作戦」が必要となる。

工事の進め方を説明する佐藤建設監督官
- 横浜湘南道路トンネル工事の掘削工事は、シールドマシンで進めている。掘削スピードはカタツムリよりも遅く、1時間に約2.4mしか進めない。
- シールドトンネルの発祥は、イギリス・ロンドンのテムズ川トンネル工事だった。ふなくい虫にヒントを得て1893年にシールド工法が誕生した。ふなくい虫は木に穴を掘る際、口で木くずを食べて尻から出し、穴の内部を自らの体液で補強しながら、木の内部に穴を穿っていく。
- シールド工事は、まず開削工法で地中に立坑を掘削し、その立坑内に発進設備を収める。シールドマシンのパーツを立坑内で組立て、シードルマシンを完成させたら、ここから横方向にトンネルの施工を開始する。
- 円筒形のシールドマシンで土圧や水圧を抑制しながら、ジャッキの力で前進。前面のカッターディスクの力で土砂を掘削し、後部のリング上でセグメントを組み立てていく。
- セグメントの組み立ては機械化・自動化している。セグメントの外側に裏込め剤を注入して固める。掘削して発生した土砂は、ベルトコンベヤーで地上の処理施設に送られる。
- 目的地にシールドマシンが到達する頃、そこに到達立坑を構築し、貫通したらシールドマシンを分解・回収。トンネル内の設備工事などを実施して、工事が完成する。
現場公開の社会的意義
見学会の終了後、国土交通省のメルマガを見て参加したという親子連れに、見学会の感想を聞くと「現場を見られる機会がないので大変良かった」「高所作業車に乗れて楽しかった」などの声があった。
一方、原田課長は「建設業や社会インフラへの理解はまだまだです。非日常を体験し、建設業のことを少しでも知ってもらえたらと思っています。」と熱く語る。
「現場を見学した方々からは、トンネル工事はわからないことが多かったが、それだけ高度な技術を使って工事をしていることが分かったという感想もありました。現場も頑張っているということを国民の皆様にご理解いただけるよう、今後も発注者と受注者で協力して現場見学会を開催していきたいです。」(原田課長)
佐藤建設監督官も「工事現場で何をやっているかを地域住民の方々に知ってもらわないと事業は進みません。もっと事業内容や現場をオープンにして安心感を与えていきたい。」と現場見学の社会的意義を語る。
「現場見学会をきっかけに、将来、建設業に入る若者が誕生し、建設業界が活性化するかもしれない。そんな願いも込めて、国民に寄り添う方向を目指しています。」(佐藤建設監督官)
なお、同現場は、日本建設業連合会による「けんせつ小町の現場見学会」や、近隣小学校の現場見学会でも活用されている。


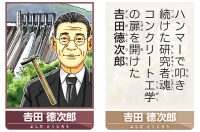






私は建築屋ですが、メッチャ面白かったです!?
私も九州で建築関係の仕事に携わてます。新人時代は使い走りそれぞれのス―パー親方衆と子分たちと一諸に仕事しながら現場を纏める親方衆の仕事の段取りはさすがです。
超笑ったわ!土木最高!
土木系の営業しております。我々のなかでは土方の親方に気に入られたら一人前と言われます。
記事書いたやつ頭悪そう
貴様が言うな!!
何様や!?
アナリストにツボりました。
どの地方でも当てはまる職人さんアルアルだと思いました。
そんな職人さん達に囲まれて楽しく現場をやっていきたいです。