最初に入れた建設機械で大体なんとかなる
吹付機の場合も同様で、小型吹付機から通常吹付機に変更する場合などがあります。
明らかに吹付量が違いますが、狭小の場合もあります。そんな時の機械選定は非常に難しいです。
その理由には、
- 施工に掛かる機械設置位置の拡大・縮小に伴う説明等
- 施工計画書の差し替え
- 施工手順書の差し替え
などがあります。
上記のように書き出しましたが、実際はここまで出していないことのほうが多いのが事実です。施工管理者がこのような書類を集めている間に、施工が終わってしまう可能性も十分あります。
機械を変更したとしてもさほど変わらないのであれば、そのまま施工したほうが良い場合がほとんどです。
職人が少しでも楽なほうを選ぶのは大事なことですが、その裏で途方も無い書類を作っている現場監督がいるんですよね(笑)
ただ、少しでも進む方を提案し打ち合わせして試してみるのも、現場では大事なことです。
全てがダメだということではなく、現状で工夫することも大事です。(現状で工夫する職人はデキる職人!)
ただし、コレがゼネコンの現場となると話は変わります。
ゼネコン現場の場合は、特に先に打ち合わせして実行しないと、作業手順書と違うことを指摘され面倒になります(笑)
完璧にやらなければ認めてもらえません。
やはり、事故があってからは遅いので、当たり前の話ではありますが。
しかし、経験的には最初に入れた機械で大体なんとかなることのほうが非常に多いです(職人が現場になれて対応できるようになるため)。
※この記事は「新エンタの法面管理塾」の記事を一部編集して掲載したものです。







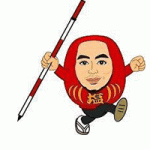

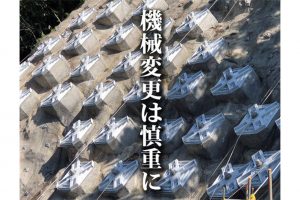
変更計画書は非常に無駄ですね。
工種の変更や大きな追加変更等なら安全面やその他から計画書の修正はわかるのですが、数量の多少の変更やBHが0.1から0.25になったくらいでまた概要からなんやら修正した出すことになんの意味があるのか?
あくまで計画であって実際が異なったところで安全基準を守っているのだから何の問題も感じない。
ただの担当の安パイでしかない。
働き方改革なんてできない。