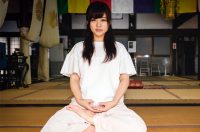不発弾の多くは建設現場で見つかる
人材不足や資材の高騰、週休2日制導入による事実上の工期短縮・・・ただでさえ工期が足りない工事現場で、絶対に“掘り当てたくない”ものがある。それは不発弾と遺跡。運悪く発見されれば、まず工期の延長は避けられない。
不発弾とは、砲弾や焼夷弾、手榴弾などのうち、起爆装置が何らかの理由で作動せず、爆発しなかったものを指す。戦時中の空襲や艦砲射撃で着弾したものだけでなく、旧日本軍が保管していた弾薬なども含まれる。終戦から70年以上が過ぎたが、今もなお爆弾としての威力を保ったまま、地中表層に埋まっている。

東京都港区での不発弾処理 / 陸上自衛隊
陸上自衛隊陸上幕僚監部広報室によると、自衛隊によって処理を行った不発弾の数(全国的な処理件数)は、2015年度は1,392件、2016年度は1,379件、2017年度は1,611件もあったそうだ。
しかもその多くは、建設現場から見つかっている。最近では、昨年12月に東京都と沖縄県で発見され、2019年に入ってからは京都府や山口県で見つかった。
戦時中、全国のほとんどの主要都市は空襲を受けた。特に軍需工場などの軍事施設があった地域は、集中的に狙われた。さらに米軍の爆撃機は帰還する際に、余った弾薬を“標的ではない地域”に捨てて(落として)から帰っている。軍事施設とは関係のない地域で不発弾が見つかることがあるのはこのため。「ウチには関係ない」と思っていた工事現場からも出てくる可能性はあるのだ。
万が一、工事現場で不発弾が見つかった場合、どのように対処すればいいのか。過去に何度も不発弾処理を経験したことがある陸上自衛隊武器学校の教官に、対処方法を聞いてきた。