旧二重橋や日本橋も造った技術者集団「種山石工」
熊本県には約800基もの石橋が残るとされ、このうち江戸時代後期から明治時代に建設されたものは約270基にも及ぶ。
熊本県におびただしい数の石橋が残っている謎を解くカギは、「種山石工(たねやまいしく)」の存在が握っている。
種山石工とは、熊本県八代市で活躍した技術者集団で、長崎の武士だった藤原林七が祖といわれる。
江戸時代、出島に滞在したオランダ人から円周率の計算方法を学び、その後、八代市に移り石橋の知識、技術を磨くとともに、子孫たちにそのノウハウを伝えた。
東京の旧二重橋や日本橋も、種山石工の子孫たちの手によるもので、石橋造りの技術の高さをうかがい知ることができる。
熊本でも通潤橋(山都町)や霊台橋(美里町)など多くの石橋が国指定重要文化財となっており、その雄姿は今も健在だ。

熊本県湯前町にある石造アーチ橋「下町橋」も種山石工系の作
単一アーチ式石造橋「下町橋」の補修を検討
種山石工によって数多くの石橋が現役で残っている熊本県だが、1906年(明治39年)に竣工した石橋の補修が検討された。
対象となった石橋は「下町橋」と言い、熊本県の南部に位置する湯前町に存在する。この下町橋も種山石工系が造ったものとされる。
湯前町の町道下城線に架かる単一アーチ式石造橋で、橋長18m、幅員3.5m。架設後112年が経過しており、町指定文化財となっている。
2017年に実施した橋梁診断によると、下町橋は「輪石・要石の剥離・はなれやうき、ひび割れ(最大幅0.5mm)」「防護柵の変形・欠損や防食機能の劣化」「舗装の凹凸(ひび割れや欠損、段差95mm)」「壁石の剥離(はなれ)」「A2橋台の基礎石流失による欠損」などの所見が報告され、一部補修が望ましい『判定区分Ⅲ』と診断された。

A2橋台の一部では基礎石が流失している下町橋


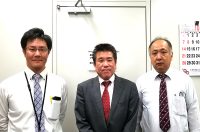







権力を振りかざす世間知らずの勘違い野郎どもは本当に消えていただきたいです。