「お前みたいな飛び込み入社は初めてだ」
――大学で土木を学んだのですか?
永田 そうです。イヤイヤ土木を学びました(笑)。本当は化学を学びたかったんですよ。中学生の頃から、白衣を着て、研究所で研究開発をしたいという夢があったんです。
例えば、光触媒の研究なんかをやりたかったんです。大学に入るときに、応用化学科、機械工学科、土木工学科の3つを順番に志望したのですが、土木にしか入れなかったわけです。研究室は土質力学でした。
就職の際にも、化学者の夢を捨てきれずに、土木職で研究職を募集する東京のとある会社を受けました。首都高速道路公団(当時)に就職したのは、試験会場がたまたま近かったのと、たまたま試験に受かったからです(笑)。
私は大阪の大学にいたのですが、当時の首都高速道路公団は入社試験を受けるのに新幹線代とホテル代を出してくれたので、ついでに受けたわけです(笑)。他の学生はすでに内定をもらっている人間ばかりで、入社後、会社の人から「お前みたいな飛び込みを採用したのは初めてだ」と言われました(笑)。
――首都高速道路でやりたいことはとくになかったということですか?
永田 なかったですね(笑)。こういう人間は珍しいと自分でも思います。首都高速道路に入ってしばらくしてから、光触媒を用いたガードレールや遮音壁の開発に携わることができたので、今となっては、首都高速道路に入って満足してはいるんですけどね。
死亡事故をきっかけにメンテの大事さに目覚める
――首都高速道路に入ってどういう仕事をしてきたのでしょうか?
永田 最初は特殊設計課という長大橋などをつくるセクションに配属されました。横浜ベイブリッジとか鶴見つばさ橋の設計を担当しました。入社当時はバブルだったので、華やかな仕事をしていました(笑)。スゴく楽しかったです。特殊設計課の後は、ずっとメンテナンス畑です。維持管理の事務所や維持管理の設計などをやってきました。
――やはり橋のメンテナンスに関わってきた感じですか?
永田 そうですね。首都高320kmのうち80%が橋ですから。ただ、僕は自分のことを「橋屋」ではなく、「インフラ屋」だと思っています。社内的には「メンテナンス屋」だと思われています。「メンテナンス畑がこんなに長いヤツはいない」と(笑)。入社して31年のうち、24年メンテナンス一筋ですからね。

――これまでで一番印象に残る仕事はなんでしょうか?
永田 これは一つしかありません。本社の保全技術課にいた1999年4月、首都高7号小松川線で、排水桝のフタを車が踏んで跳ね上げて、反対車線を走っていた車のフロントガラスを突き破って、トライバーの方が亡くなられたことです。その年には、3号渋谷線で標識柱が落ちたこともありました。
当時はいろいろなモノが落ちていました。この事故の前までは、橋本体の構造物のことしか考えていませんでしたが、事故をきっかけに「附属物やメンテナンスって大事なんだ」と考えるようになりました。
当時の首都高速道路には、その排水桝の図面すらありませんでしたし、首都高全体の排水桝の数は誰も知りませんでした。ちなみ排水桝の数は5万1,000個です。後で数えたんですけどね(笑)。メンテナンスをしっかりやるためには、ちゃんとしたデータベースが必要だと気づきました。
一連の事故をきっかけに、「メンテナンスこそが大事だ」と僕の考え方がガラリと変わったんです。


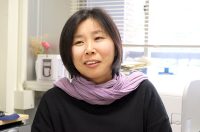







純粋な方だ。尊敬する。
インフラを守る、そのための技術向上は、開発にて対応する『ない技術はつくる』考え方に共感します。
今の日本のインハウスエンジニアに一番求められる資質をお持ちの方だと思います。
明るい未来を考えられる、すばらしい記事でした。
この方の「考え」「思考」をもっと知りたいと思いました。
いつかお会いしてお話ししてみたいですね