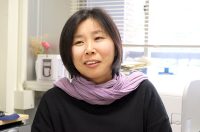未開通区間20.9km中、14.5kmを事業化
大阪湾岸道路(4号、5号湾岸線)は、神戸淡路鳴門自動車道(垂水JCT)から関西国際空港(りんくうJCT)を結ぶ延長約80kmを指し、延長約59kmが開通している。大阪湾岸道路西伸部は、湾岸道路の未開通区間(六甲アイランド北〜垂水JCT)の延長20.9kmを指す。
この区間のうち、六甲アイランド北〜駒栄間延長14.5kmが今回事業着手した区間になる。西伸部は、31号神戸山手線と接続される。駒栄〜垂水JCTについては、都市計画はあるが、事業化については、現在白紙だ。
西伸部のルートは、5号湾岸線の終点である六甲アイランド北が起点。六甲アイランドを横断し、西端部の六甲アイランド西ランプ(仮称)から、灘浜航路、新港航路が通る海上をまたぎ、ポートアイランド東端部のポートアイランド東ランプ(仮称)に接続する。
ここから島を西南に進み、西端部のポートアイランド西ランプ(仮称)から、再び神戸西航路が通る海上をまたぎ、和田岬西防波堤付近に上陸。海岸沿いを進み、南駒栄JCT(仮称)を経由し、31号神戸山手線に接続する。

大阪湾岸西伸部の概要(阪神高速道路HPより)
全国ワーストの渋滞緩和、災害時の代替路確保など
西伸部の整備効果は、主に3点ある。
1つ目が、移動時間の短縮だ。神戸の海沿いを通る都市高速は今のところ神戸線だが、慢性的な交通渋滞が発生している。国土交通省の調査によれば、神戸線(西宮JCT〜第二名神接続部)の渋滞損失時間(1万人が1年間のうち損失する時間)は、下りが323.8時間、上りが245時間に上る。この数字は、上下線合わせて年間568.8万人が渋滞により、1時間ムダにしていることを意味する。
全国の都市高速の中で、ワーストのワンツーとなっている。西伸部が開通すれば、玉津IC〜神戸港の所要時間は45分から31分に、玉津ICから大阪駅の所要時間は96分から64分にそれぞれ短縮される(国土交通省調べ)。
2つ目が、代替路の確保だ。神戸線では、年間855件(2018年)の交通事故が発生しており。このうち392件で車線規制(一部通行止め含む)が実施されている。車線規制により、一般道に車両が集中し、渋滞が発生している。
神戸線の開通は1961年。建設から60年近くが経過しており、大規模更新の必要もある。西伸部は、神戸線の代替路として機能させることができる。代替路の確保により、神戸線の大規模改修も可能になるほか、災害発生時のリダンダンシー確保にもなる。
3つ目が、ポートアイランドに立地する企業や神戸空港などの経済活性化だ。現状では、ポートアイランドには都市高速は接続しておらず、大阪方面への移動には神戸市が管理するハーバーハイウェイ(有料)を経由し、阪神高速に乗り入れる必要がある。
ポートアイランドには2つの出入り口を設置予定で、阪神高速への直接乗り入れが可能になる。立地企業、ポートアイランドの先にある神戸空港利用者にとって、アクセス向上になる。

ポートアイランド周辺の現況(写真提供:阪神高速道路株式会社)
神戸線は、西日本の物流の大動脈であり、そのリダンダンシーを考えれば、西伸部は早期開通が必要な重要な路線だと言えるが、当初の計画から事業化まで40年以上の年月を要した。なぜもっと早く事業化できなかったのか、という素朴な疑問が湧く。
この点、「それはやはり事業費がネックになっていたからだ。神戸市は1995年の兵庫県南部地震で大きな被害を受け、震災復興には大きなお金と時間が必要だった。われわれとしても、早期に事業化したいのはヤマヤマだったが、『まずは復興』ということで、新線の事業費としての地元負担の合意ができなかった」(広瀬鉄夫・阪神高速道路㈱神戸建設部長)と振り返る。