実物大の躯体を活用した実技研修
そこで開設されたのが、「DO SPACE上尾」だ。
ここでは、単に商品の組み立てや取り付け方法を学ぶだけではなく、実物大の躯体や研修体を活用した実技研修により、商品の長さや重量を感じつつ、現場調査や墨出し、基礎用の穴あけや柱の立て方、調整などエクステリア工事の基本を学べる施設となっている。

実技研修場全景
障害物など、実際の施工現場を再現した環境で実技研修することで、より実践的な施工技術が習得できる点も大きなメリットだ。
また、座学コーナーもあり、施工の知識や技術、現場で必要なマナー、安全知識、関連法規などの研修も行っている。

座学研修
職人ワザを”見える化”し、”伝承”する
施設を見学したのち、エクステリア施工技術研修所の三輪哲也所長と金田義久エクステリア技術力強化チームリーダーに話を聞いた。
――研修所では、具体的にどのように研修を進めていく?
三輪 「カリキュラムを開発」→「施工効率・品質をあげるため、職人ワザの見える化と研究開発を進化させる」→「カリキュラムを充実する」というPDCAサイクルを効率的に回すことを考えています。
職人ワザは、従来は見えないものでしたが、これからの時代は可視化して伝えていくことが重要です。これまで親方から子方へと伝承されてきたものが、現在は崩壊しつつあります。これは、エクステリア業界でも同様です。
そうなると、職人ワザをみなで持ち寄り共有していくことが望ましい形となります。そこで弊社から全国約600社1,000名からなる施工協力会にアプローチし、研修を通して職人ワザを見える化し、広めていきたいと考えております。
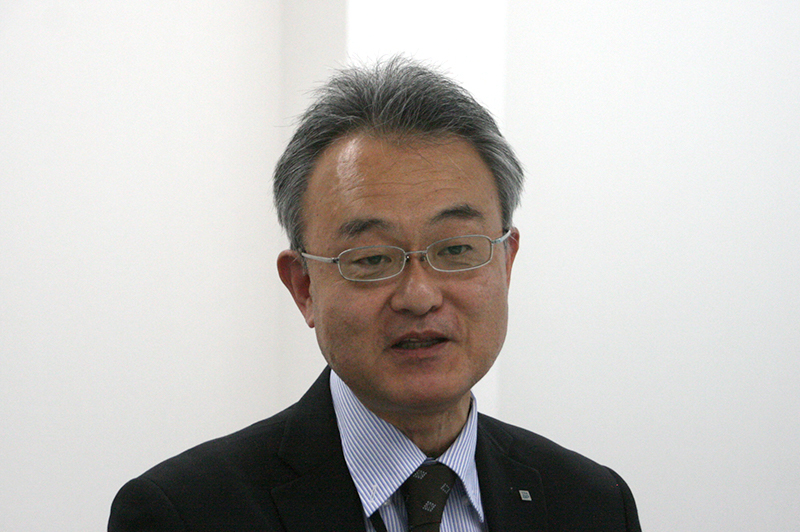
三輪哲也氏
――どれくらいの方が受講される?
三輪 受講者は施工協力会の施工技術の向上および安定と、弊社の商品を扱っていない流通店様、エクステリア工事店様が受講することによるエクステリア施工の担い手の拡大という2本柱で受講者を募っております。
具体的には、4月入社との新卒者向け研修ではなく、ある程度エクステリアの知識があり、窓、サッシの組み立てや電動工具の経験者をターゲットにしています。
必ずしも、YKK APの施工協力会に入会されている方に限ってはいません。例えば、商品のお取引先で施工を行っている方でも受講は可能です。
――講師はどなたが担当する?
金田 講師は、弊社で生産技術部門を担当し、施工部門に精通している社員が担当します。これまでも、移動型研修にて各地で施工協力会向けに講師を行ってきた社員もいるので、研修所で引き続き講師を担当します。

金田義久氏
――これまでのYKK APの研修と異なる点は?
金田 これまではYKK APの商品の組み立て方法を説明してきました。これに加えて、基礎の底面の納め方、柱を立てた後のレベル出しなど、実現場に近い研修となっています。

「リウッドデッキ200」実技研修




