「自助・共助・公助」に加え、「民助」の理念も
――国の税金だけではなく、民間活力を導入すべきという意見もありますが。
谷口 イギリスはPFIの発祥地であり、新しいファンド活用も検討しているのではないでしょうか。菅義偉総理が自らの政策理念として掲げている「自助・共助・公助」に加えて、ボランティアも含めた「民助」も必要であると思います。
地域社会とともに歩んでいく企業の姿を求めていくことがこれからも大切ではないでしょうか。
――そもそも「ビックピクチャー」は誰に向けての発信になりますでしょうか。
谷口 我々の土木は、青山士(あおやま あきら)ではありませんが、「世のため人のため」の事業です。まず我々の生活経済社会があって、それに伴い我々土木やインフラがどうあるべきかを考えなければなりません。
「ビックピクチャー」がどういう結果になるかわかりませんが、一般国民とりわけ若い方の意見を聞きたい。我田引水で我々の思いだけではなく、単に過去や諸外国の投資額を提示し、将来世代にツケを残す形でしかるべき投資額を提案しても受け入れられないと思うのです。
しかし、将来にわたるインフラ投資額は本来、アメリカ、イギリスや中国がそうであるように政府が発表するものです。国の当初予算では社会保障費がおおよそ3割で、公共事業費は6%です。全体で限りある財政の中でインフラのあるべき姿を提示することが肝要です。
国民にインフラへの危機意識を共有していただかないと、政府に思いが届かないのです。それが失われた30年という停滞・閉塞状態を招いておりますが、この国家的危機を転換しなければなりません。
土木技術者の地位向上の提案も
――土木技術者の地位向上の提案について現在、お考えになっていることを教えてください。
谷口 生産性向上の結果、コスト縮減になり、デフレスパイラルを及ぼしては意味がない。やはり、世間並みの労働対価へと上げていかなければならない。その時に設計積算の歩掛りが人工になっています。
昔は受発注者間で様々なやりとりがありました。土木技術者のしかるべき評価については、産官学の集合体である土木学会が、オープンで忌憚のない意見交換を踏まえ、社会的地位向上に資する提案を行いたい。
この1年、感じていることは土木学会がいろんなツールで情報発信を行っていることです。しかし、若者にそれが伝わっていない部分がかなりある。
そこで一方的なプッシュ型の情報発信では限界があるのではないか。現場とのコミュニケーションをとりながら、「プッシュ型」も採用しつつ、双方向での「プル型」も導入し、意見交換を活発にしたい。そこで、若者に人気のある「note」を取り入れ、気持ちとしては双方向で対話していきたいです。
――土木学会が組織として変えていくべきことは。
谷口 会長任期1年の伝統を変えることは難しい。一方、家田仁前会長の発案で前・現・次期会長が三位一体で取り組む姿勢を打ち出しました。とはいえ、現会長がリーダーシップをもっと行っていくことは変わりませんが、やはり、コミュニケーションのありようだと思います。
私も実は、すべて変えるというのは短いと感じています。今回の発案である「ビックピクチャー」について全力投球して燃え尽きることは考えておりません。私のような人が後に続くことを期待しております。
われわれが育んできた土木の原点、日本の伝統文化、自然や和の大切さとグローバル化に齟齬をきたさないように土木の立ち位置も変えていく必要があります。
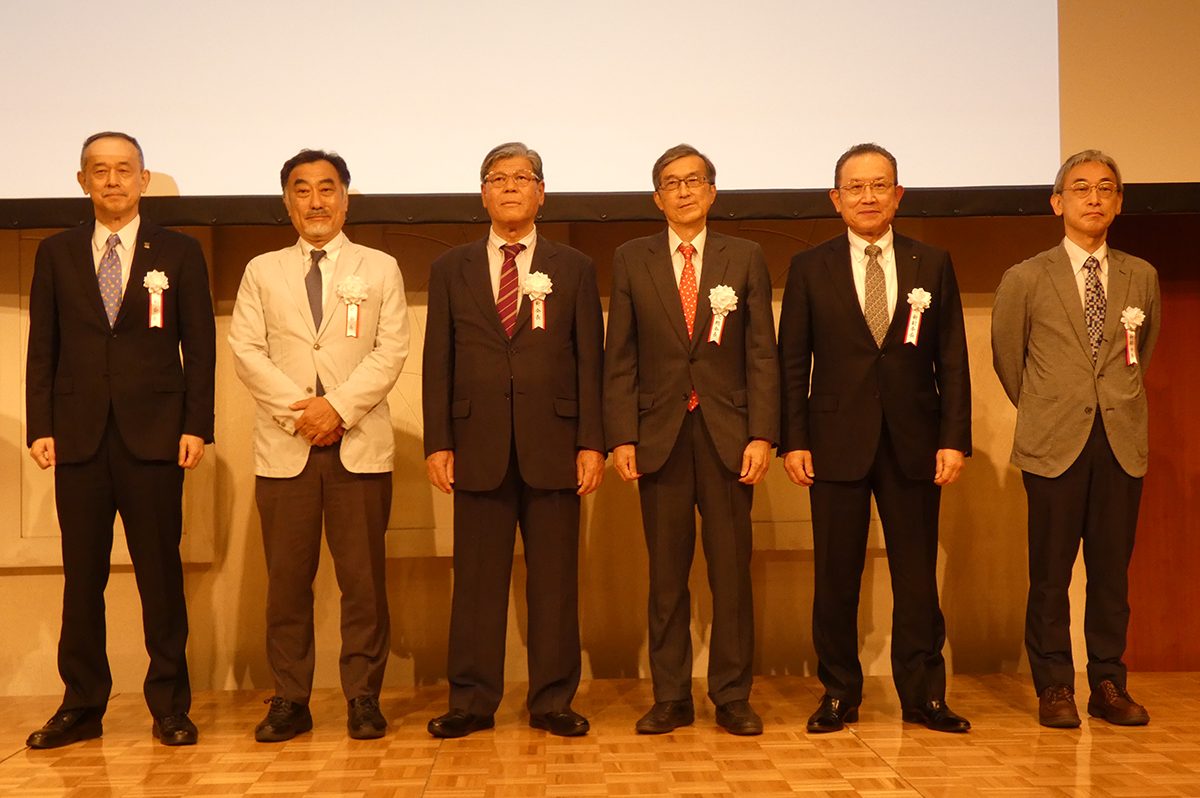
定時総会後、家田仁前会長・谷口博昭新会長、上田多門次期会長や 各新副会長らが並んで記念写真
人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!
「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、
こちらからお気軽にお問い合わせください。






