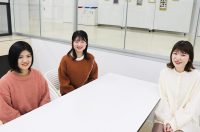「研究室に残ってやらないか」

松永さん
――卒業後の進路はどのように決めたのですか?
松永さん 学部在学中は、就職に対するイメージが漠としたものしかありませんでした。土木をしっかり勉強したという実感もなかったので、とりあえず大学院に行って、「ちゃんと土木を勉強しました」と言えるようになろうと考えました。
ところが、修士を終えて就職活動をするときになっても、依然として自分が社会に出るイメージが浮かばなかったんです。「国際機関に行きたい」というなんとなくした願望はあったのですが、そのために努力することはありませんでした。
そんなとき、私が所属する研究室の助教の先生が他の大学に移ることになって、ポストが一つ空くことになりました。研究室の先生から「研究室に残ってやらないか」と言われました。当時の私には研究者になりたいという気持ちはなかったのですが、数年の腰かけで研究を続けるつもりもありませんでした。
そこで、先生には「一回社会に出たい」と言って、お断りしようとしたのですが、「研究室は小さい組織だけど、小さな会社だと思えば、社会に出るのと同じだよ」と言われました。「そこまで言っていただけるのは幸せなことだな」と気づいて、助手として、研究者としてやっていくことを決めました。学位をとったのはだいぶ後でした。
――公務員とかゼネコンとかは一切考えなかった感じですか?
松永さん そうですね。たぶん向いてないので(笑)。
――研究室に残ってからは、どんな感じでした?
松永さん 研究室の助手として4年ほど働いた後、一旦退職し、1年半ほどフランスの大学院に留学しました。コース名は交通と持続可能な開発でした。2006年から同じ職場に復帰し、助教として働いていました。
――福岡女子大学ではなにを教えているのですか?
松永さん 大学では現在、生活コースというところに所属しています。女子大学ですので、土木工学科はもちろん、工学部もありません。二級建築士関連の科目を教えたり、どちらかと言うと建築よりです。文理統合科目として、主に文系の学生を対象に、土木の文化や歴史などを講義したりしていますが、概要だけという感じです。今の大学に来て、土木色は若干薄まっていますね。
働き続けるなら、地方公務員

吉岡さん
――吉岡さん、就職活動はどんな感じでしたか?
吉岡さん 私は在学中から「早く働きたい」と思っていて、最初から公務員志望でした。ゼネコンなど民間で女性が働いている事例は少ないということは知っていたので、働き続けるなら地方公務員という考えでいました。就活の際、地元の役所を受けようと思いましたが、ちょうど土木職の職員採用がゼロだったので、あきらめました。
――当時はそもそも女性を採用する枠がなかったという話を聞いたことがあります。
吉岡さん そうですね。就職活動をするまでは、男女の差を感じたことはなかったのですが、そこには大きなカベがありました。
――コンサルは考えなかったですか?
吉岡さん あまり考えなかったですね。公務員は、計画のほか、建設も携わることができるし、分野も幅広いので。
――地方公務員をやるなら、福岡市役所が良かったわけですね。
吉岡さん そうですね。採用枠も多かったですし。福岡県庁も考えたのですが、勤務エリアが広いので、馴染みのある福岡市役所のほうが良いと考えました。
まちづくりをするなら、やはり地方公務員

塚本さん
――塚本さん、就活はどんな感じでしたか?
塚本さん 私も吉岡さんと一緒で、すぐ働きたいと思っていました。公務員志望も同じでした。福岡市役所しか受けていません。ゼネコンやコンサルに対して抵抗があったわけではありませんが、やはり働き続けるには公務員が良いのかなという感じでした。まちづくりに興味があったので、どんなまちにするか決めるのは公務員、というのもありました。福岡市役所では、都市計画とか、まちづくりに関する仕事をやりたいと思っていました。
――福岡県庁とかは考えなかった感じですか?
塚本さん そうですね。福岡市は政令市なので、仕事の幅が広いですし、県庁と比べて転勤が少ないのも魅力でした。
治水をやりたかったので、コンサル一本
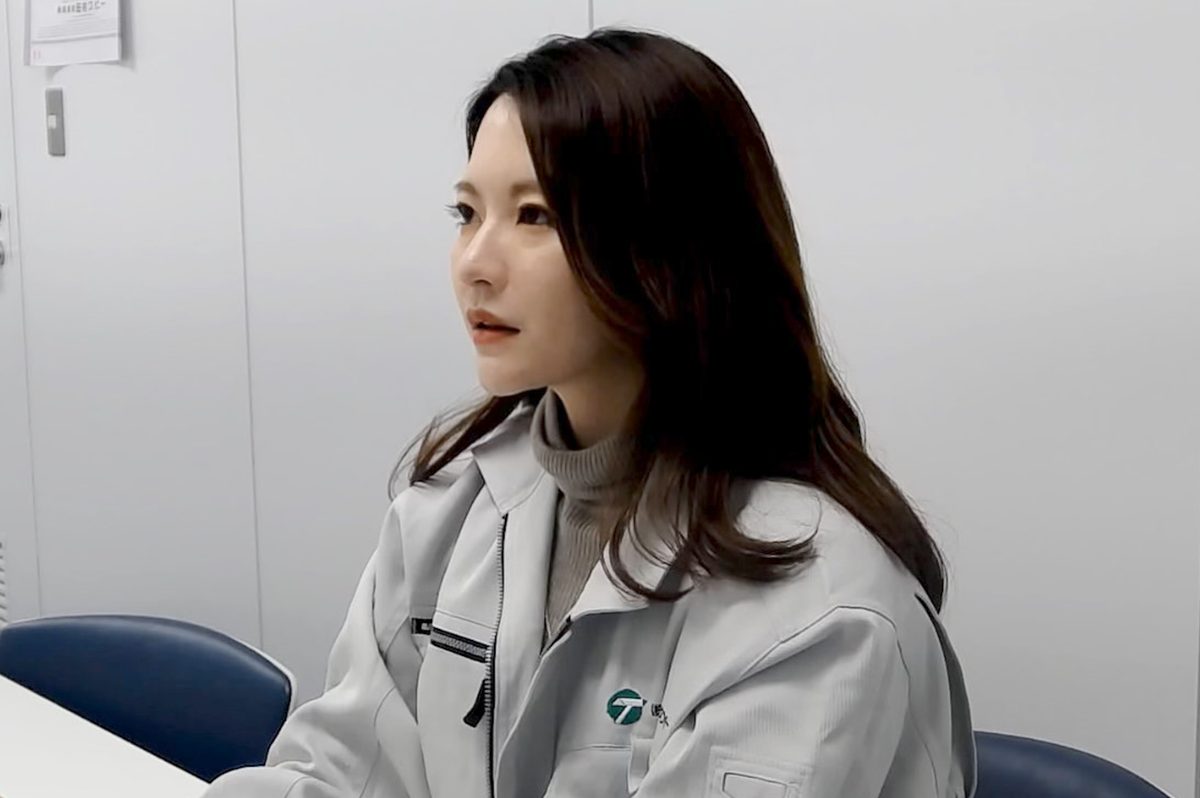
増田さん
――増田さん、就活はどんな感じでしたか?
増田さん 私も早く就職したいとは考えていましたが、公務員ではなく、コンサル一本でした。いくつかのコンサルを受けましたが、最終的には東京建設コンサルタントに決めました。コンサルを選んだ理由は、研究室で河川をやっていたので、実際に自分で手を動かしながら、治水対策に関する業務などをやりたいと思ったからです。
――河川関連の設計をやりたかったのですか?
増田さん そうです。運良く、配属先も希望通りの部署でした。
――コンサル志望なら、大学院は考えなかったですか?
増田さん 院卒のほうが仕事の上でのアドバンテージはあるとは思いますが、早く実務経験を積みたかったので、それはあまり考えなかったです。
――転勤は大丈夫でしたか?
増田さん 基本的には転勤はしたくないと思っています。実際には転勤してしまいましたけど(笑)。
――最初から関西本社ですか?
増田さん いえ、最初は東京本社採用でした。東京のほうで主に治水関連の仕事をしていました。2021年夏から関西本社に異動になりました。
自分で計算して、自分で図面を引くのが魅力
――コンサルの仕事の魅力は?
増田さん 私にとっては、「自分の手で計算して、図面を引く」という行為が魅力です。私の場合は河川関連になりますが、インフラを一貫して見守る仕事であることにもやりがいを感じています。疫病の影響で、最近はあまり参加できていませんが、コンサル他社の若手による勉強会などもあるので、いろいろな人々と交流できるのも、楽しいです。
――実際に仕事をしてみてどうですか?
増田さん とても難しい仕事だと感じています。当然ですが、マニュアル本を覚えたから、できる仕事というわけでもありません。上司や先輩の仕事ぶりを見ながら、今も勉強しているところです。最近になって、やっと仕事のやり方が少しわかるようになってきたかなと感じています。発注者さんとの打ち合わせなども、任せてもらえるようになりました。
技術士という資格があって、院卒だと入社3年目から受験できるのですが、学部卒だと5年目からになっています。それでいくと、学部卒の4年目は「全然一人前ではないんだな」と感じているところです。
――仕事の内容はどんな感じなんですか?
増田さん 基本的には、河川氾濫の流れを計算したりとか、デスクワークが中心です。ただそれだけだと机上の空論になってしまうので、実際の現場に出て、河道のカタチだったり、植生の状態などを確認しながら、作業を進めています。そうやって資料をつくったら、発注者さんのところに行って、打ち合わせをしています。複数の案件に関わっていますが、基本的にはチーム単位なので、チームの一員としてそれぞれに関わっている感じです。
――流域治水関係とか、ハザードマップ関係ですか?
増田さん そうですね。河川が氾濫したときに、どういうハード整備が必要なのかという検討だったり、気候変動に伴う治水計画の見直し、ハザードマップのための浸水想定区域の作成といった仕事がメインになります。
――ツラかったことはありましたか?
増田さん あまりありませんが、発注者さんとの打ち合わせで、答えにツマッてしまったときは、ちょっとツラかったですね。
――コンサルには長時間労働のイメージがありますか?
増田さん 昔はそうだったという話は聞きます。実際のところ、年度末などは忙しい時期はありますが、連日深夜まで働くということはありません。