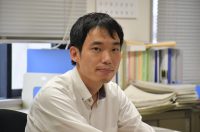国土交通省は、周りの受験生もスゴいし、きっと楽しい
――最初は地元志向だったんですねえ。
井上さん ええ。ただ、そんなとき、「国家公務員の試験も試しに受けといたら」とアドバイスをもらったので、国家総合職の試験を受けてみました。実際に試験を受けてみると、周りは東大生、京大生ばかりで、地方大学の学生はあまりいないわけです。面接を受けたり、先輩職員と意見交換するうちに、「こんな組織で働けたら、周りの受験生もスゴいし、きっと楽しいだろうな、良い経験ができるだろうな」と考えるようになりました。
そうするうちに、まさかの最終面接に残りました。その時は「ヤバい」と思って、実家に帰って、家族会議を開きました(笑)。「もし受かったら行ってみたい」と伝え、家族の了承を得ました。その後、内々定をいただき、結果的に国土交通省に入ることになったわけです。
――九州地方整備局は考えなかったのですか?
井上さん 考えなかったですね。一般職の試験も申し込んではいましたが、面接には行きませんでした。やはり、総合職の仕事に魅力を感じたからです。
川の仕事ってやっぱり良いな

木曽川時代。よく遊びに行っていた、揖斐川の河口です(写真本人提供、キャプション本人談)
――国土交通省ではどのようなお仕事をしてきましたか?
井上さん 最初の配属先は、三重県桑名市にある、中部地方整備局の木曽川下流河川事務所の調査課でした。2年目は工務課で、3年目は管理課に半年ほどいました。同じ事務所にずっといるというのは、けっこう珍しい人事でした。堤防を2mかさ上げする工事などに携わり、河川整備の実務の流れを経験することができました。また、木曽三川下流部はゼロメートル地帯が広がることから、県域を越えた連携を図る広域避難に関する取り組みも担当しました。
川をやりたいということで入省して、最初に川幅が1kmもある大きな河川の仕事に携われたのは、衝撃でした。地元にはそのような川はなかったので。なので、毎日川に行くのが楽しくてしょうがなかったです。休日も川に行っては、写真を撮ったり、眺め続けたりしていました。「川の仕事って良いな」と改めて思いました。
浄化槽に関する講演のため、全国行脚

環境省時代。国交省下水道部と一緒に、汚水処理に関するイベント開催したときの写真です。前列右から4人目が私です(写真本人提供、キャプション本人談)
――次の職場はなんでしたか?
井上さん 入省3年目は、本省勤務になるのが普通のパターンなのですが、私の場合は、環境省への出向となりました。環境省では浄化槽を担当しました。最初異動先を聞いたときは、なにをやるのかさっぱりわかりませんでした。「浄化槽」という言葉すらも知りませんでした(笑)。あと、当時テレビドラマの「半沢直樹」の影響で、「出向」という言葉に対して、あまり良いイメージはありませんでした(笑)。
ただ、実際に仕事をしてみると、スゴく楽しい仕事でした。職場では、技術系の係長が私だけだったので、予算の要求をはじめ、全国調査のための業務発注、コンサルとの打ち合わせのほか、全国で講演会、研修会などを担当しました。毎月全国を飛び回って、多くの地域を回りました。
当時は、政府としてインフラの海外展開が盛り上がっており、浄化槽の国際展開のために、アジアや中東、東欧などへ海外出張にもちょくちょく行きました。インドの大御所大臣に日本の技術を売り込んだり、国土交通省の下水道部とタッグを組んでミャンマーでイベントを開催したりしていました。浄化槽は河川水質とも関わる部分もあったので、やりがいを感じながら仕事できました。係長の海外出張は、国土交通省ではまずないので、貴重な経験ができました。
【九州特集】都市開発と震災復興を中心とした高待遇求人[PR]
流域治水はアツい
――環境省には何年いたのですか?
井上さん 1年半でした。その後は国土交通本省に戻って、水管理・国土保全局の河川計画課に2年間いました。最初の1年は、組織改正や定員要求などの内部事務、オリ・パラや観光政策の局内とりまとめなどを担当していました。
2年目は、同じ課の河川計画調整室で気候変動の影響評価と対策の検討という仕事をやりました。われわれがシミュレーションしたところ、産業革命以前と比べて気温が2度上がると、降雨量は1割増えるという結果が出ました。1割増加と聞くと、たいしたことないように見えるかもしれませんが、実はものスゴい影響が出るんです。たとえば、増えた分の雨は、地下に蓄えられることもなく、川に流れ出るので、川を流れる水の量で言えば、2割増えます。また、洪水の発生頻度は2倍になるという試算でした。そういう内容をとりまとめたわけです。
その上で、このリスクに対応するためにはどうしたら良いかということについて、提言のとりまとめに着手したのですが、とりまとめる前に異動になりました。その提言というのが、流域治水への転換でした。流域治水のベースづくりに関わっていたということです。個人的に、流域治水で一番アツいと思う部分は、水害リスクを考慮したまちづくりということで、河川管理者と都市部局の連携を位置付けたことです。