縦目地による騒音解消のため、延長約600mにわたって橋脚を拡幅し、橋桁を架け替える
阪神高速道路株式会社が「リニューアルプロジェクト(大規模更新・修繕事業)」の一環として進めている阿波座拡幅部の鋼桁大規模修繕工事の現場を取材する機会を得た。
この事業は、路面に設置された縦目地で生じる通過騒音の解消が主な目的だが、高速、市道に交通規制をかけ、延長約600mの区間にわたって既設橋脚の補強拡幅、既設桁の撤去、新設桁の架設といった作業を4年ほどかけて行うというもので、大がかりな工事となっている。
なぜこんなことになったのか。騒音の原因や工事の進捗、ポイントなどを踏まえつつ、取材してきた。
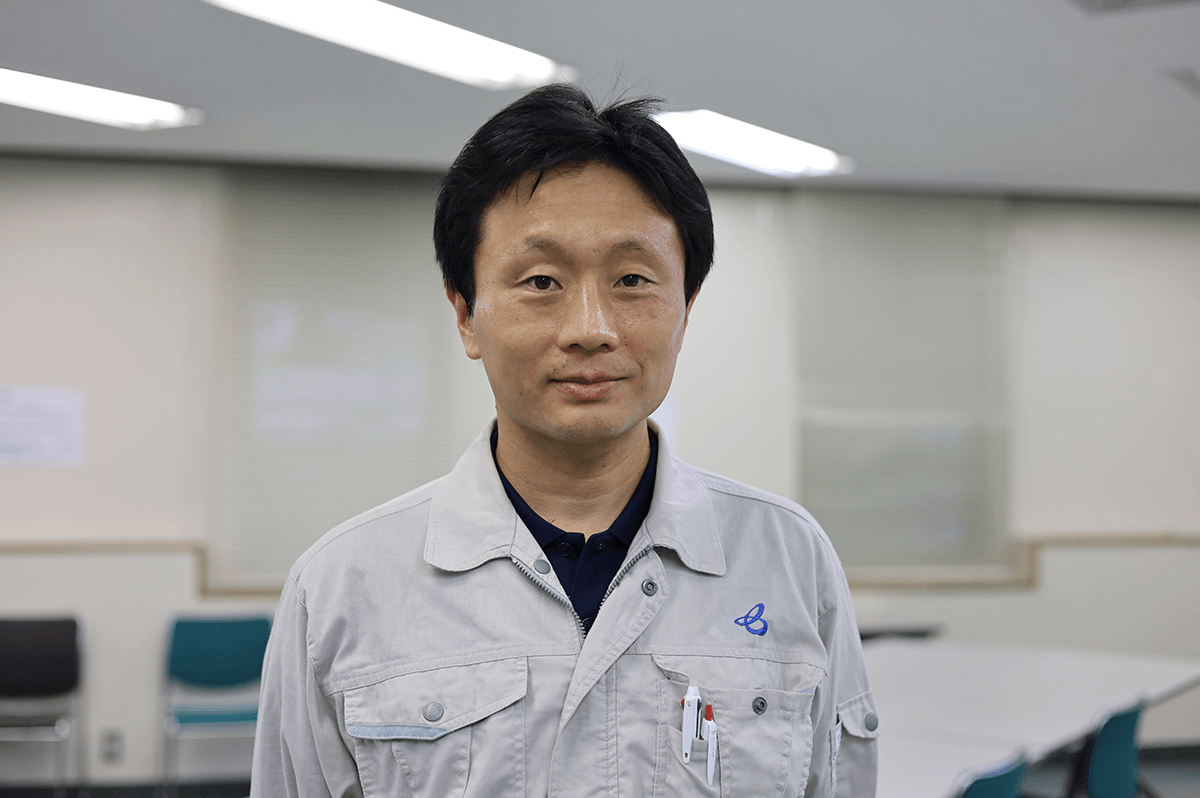
杉村 泰一郎さん 阪神高速道路株式会社 管理本部 大阪保全部 改築・更新事業課 課長代理
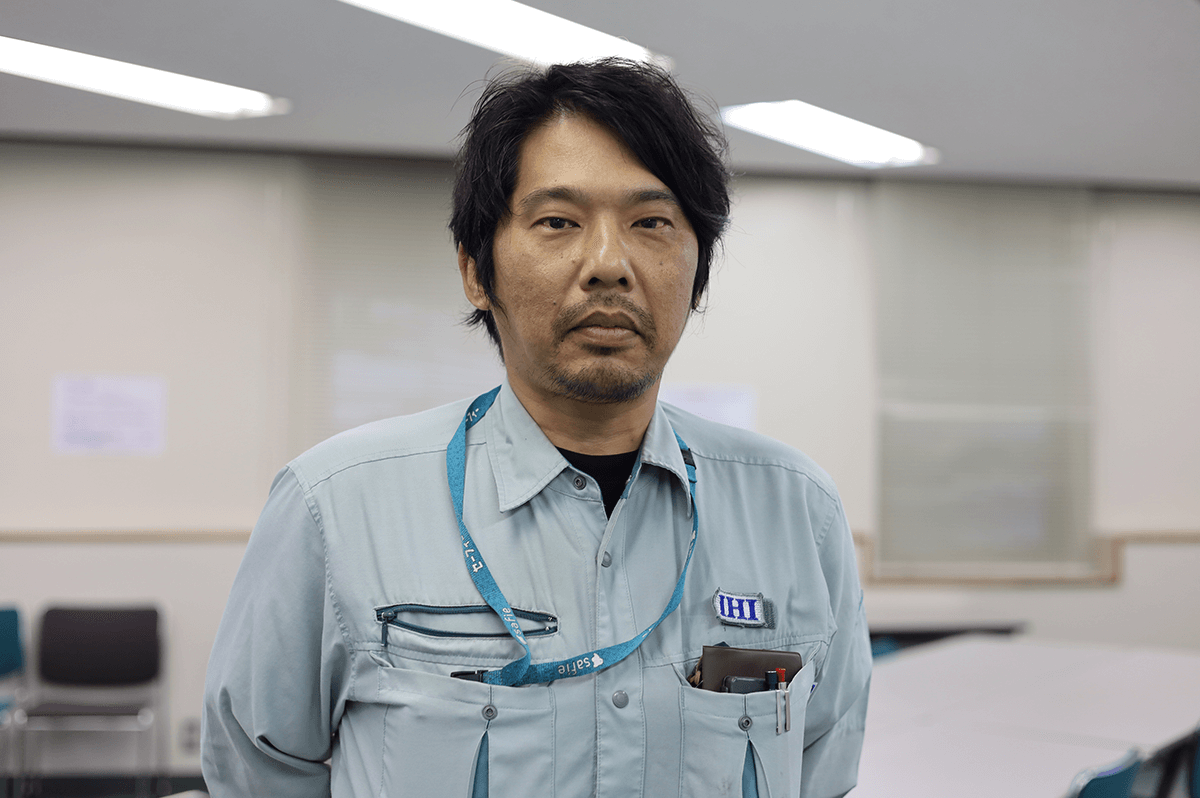
井爪 規夫(いのつめ・のりお)さん 株式会社IHIインフラシステム 東大阪線鋼桁大規模修繕工事(その1) 現場代理人
拡幅工事の後、「ゴロゴロ」という異音が発生し始める

問題の縦目地部分
工事対象となる阿波座拡幅部は、阪神高速13号東大阪線(西行き)と1号環状線の神戸・天保山方面の渡り線の合流部から16号大阪港線と3号神戸線へ分岐する阿波座ジャンクションまでの延長約600mの区間。拡幅部は、1997年に、この区間の渋滞対策として、3車線から4車線への拡幅工事を施した部分(左側レーン)を指す。この拡幅工事で設置した縦目地構造が、現在の大規模修繕工事の原因になっている。
拡幅工事が完了してまもなく、既設桁と拡幅桁の境界線部分にある縦目地(ゴム製の伸縮装置)付近から、車両通過に伴う異音が発生するようになった。通常の通過騒音とは異なり、「ゴロゴロ」というカミナリのような異音が発生するようになったのだ。かなり大きな音が四六時中鳴り響いていたそうだ。
異音の原因は桁を支える支点位置の違いによる「たわみ差」

たわみ差発生原因のイメージ(阪神高速資料より)
阪神高速がこの異音発生の原因を調べたところ、既設桁と拡幅桁との「たわみ差」にあることがわかった。なぜ、そんなたわみ差が生じたのか。結論的に言うと、それぞれの桁を支える橋脚の位置の違いにあったからだ。それはこういうことだ。
もともとあった桁はRC橋脚で支えられていた。橋脚は、大阪市道築港深江線(中央大通り)の本道と側道の分離帯に立っていたため、建築限界から柱を太くするなどの補強ができず、拡幅桁の荷重を支えることができなかった。
そのため、拡幅工事の際、拡幅した桁を支えるため、橋脚間に新たに逆L字型の鋼製橋脚を設置したのだ。既設桁はRC橋脚で支え、拡幅桁は別の位置にある鋼製橋脚で支えるというカタチで、それぞれ別々に支えていたため、桁間のたわみ差が生じそれを吸収するために縦目地を設置したというわけだ。









