テック企業が手掛ける、安全書類自動作成・管理サービス
建設現場の安全書類自動作成・管理サービスである「Greenfile.work(以下、グリーンファイルドットワーク)」を運営するシェルフィー株式会社(東京都目黒区)。その創業者であり、社長の呂俊輝(ロイ・シュンキ)さんにお話を伺う機会を得た。
同社は2014年設立のソフトウェアベンチャーで、当初は内装建築のマッチングアプリなどを手がけていたが、2018年ごろから安全書類作成サービスであるグリーンファイルドットワークへとシフトした。
グリーンファイルドットワークは、煩雑で、ストレスフルな安全書類をWEB上で半自動的に作成できることなどがユーザーから評価され、現在は登録企業14万社を超える人気サービスへと成長している。国土交通省が主催する令和4年度インフラDX大賞のスタートアップ奨励賞を受賞しており、建設業界的な評価も高い。
まさに飛ぶ鳥を落とす勢いといったところだが、個人的には、明るく奔放なイメージのあるテック企業が、安全書類という暗くておカタいイメージがつきまとう領域にビジネスチャンスを見出したこと自体が、興味深い。
シェルフィー起業のストーリーなどについてを振り返ってもらいながら、なぜ安全書類だったのか、聞いてみた。
シェルフィーは私にとって2回目の起業
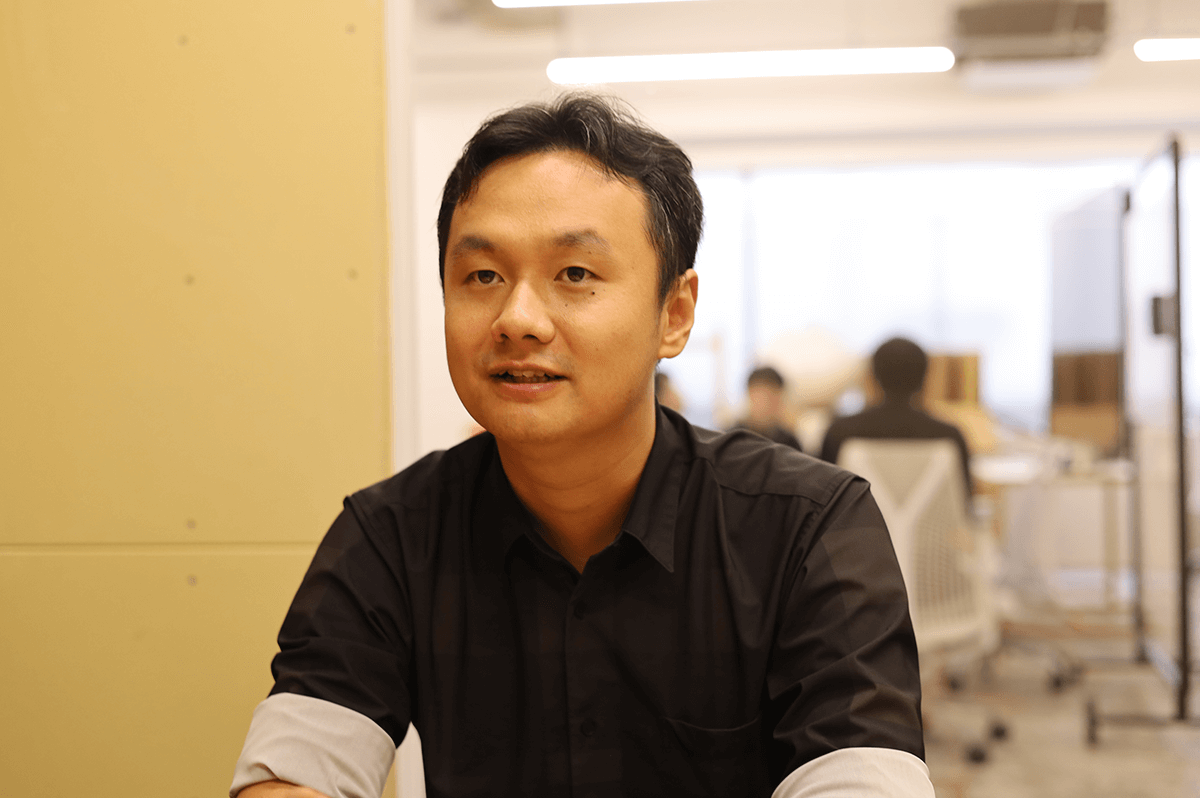
――まず、シェルフィーという会社名について聞きたいのですが、どういう意味を込めているのですか?
呂さん 本棚のシェルフからきています。「情報を整理する企業」というイメージで名付けました。
――軍艦マンションに住んでいたころに起業したそうですね。
呂さん ええ、会社登記上は軍艦マンションでしたが、実は、その前から横浜市内にある自宅のマンションに仲間を呼んで、仕事をしていました(笑)。
シェルフィーは、私とって2回目に起業した会社なんです。最初に会社を起業したのは大学生のときでした。ある事情でその会社は閉じざるを得なくなったのですが、その翌年に立ち上げたのがシェルフィーということです。
「搾取されてるクリエイターを助けたい」が起業の原点
呂さん 前の会社の起業もシェルフィーの起業もそうなんですが、「世の中にクリエイティブを生み出す人々を助けたい」というのが、私の起業の原点でした。クリエイティブを産み出す人々とは、たとえば、漫画やアニメ、ゲームといったモノをつくり出す人々です。そういう人々がいるからこそ、世の中が彩りあるモノになって、楽しく暮らすことができると思っていたからです。
私の父が建築系のデザイナーだったので、自分自身も「クリエイターになりたい」と思っていたというのもあります。残念ながら、デザイナーとしてDNAは受け継がなかったようで、私は絵がヘタでした(笑)。
ただ、私の父も私の祖父も起業家だったので、そのDNAは受け継いだようです。起業への憧れ、起業したいという思いが募った結果、クリエイターの人々に貢献できるビジネスをしたいということで、起業したわけです。
漫画を描く人だったら、漫画を描くこと自体が自己実現になっていると思うんです。なので、ちょっとお金がつくだけでスゴく嬉しいと感じているところがあります。その状況を見たときに、ビジネス的に搾取されている、利用されているという感覚が私の中にありました。私が1冊500円の漫画を買っても、漫画家には50円の印税しか入らない、残りの450円はどこに行ったんだ、ということです(笑)。
日本社会の変化を推進することに自分の命をかけたい
呂さん 最初に起業した会社は、漫画を翻訳して、アプリを介して世界に配信するという事業をやりました。事業は好調で、最終的には某有名週刊少年誌の漫画を配信するところまでいきましたが、若さゆえの爪の甘さもあり、その会社は閉じざるを得なくなりました。ただ、「自己実現のためにも、また起業する」という思いはありました。
そのころは25歳になっていたので、クリエイターだけでなく、日本社会にも貢献したいという意欲も湧いていました。実は私、幕末の志士の生き様が大好きで、「ああいう生き方をしたい」と思っていました。ちなみに、息子には「りょうま」と名付けています(笑)。
なので、次の会社では、世の中を変えるとか、日本社会の変化を推進するといったところに自分の命をかける、仲間を集めて切磋琢磨するような事業をしたいという考え、方向性を持っていました。
その軸でいくと、これから100年、200年先も続く日本社会の課題は、少子高齢化だろう、ビジネスのニーズもそこにある、と考えました。少子高齢化の根本解決は難しいので、その状況下でもなんとか工夫してうまくいくようにできるかどうかがカギになるだろう。そして、そのカギを握るのが、ITによる生産性の向上だと考えました。
つまり、SaaSによる生産性の向上、マッチングによるリソース面での非効率性の打破ということです。これらの課題解決策とクリエイターの支援をどう掛け算していくか。それがずっと頭の中にありました。
そんなとき、ブラジルオリンピック会場建設の入札価格が、人手不足などによって、2倍になったという新聞記事を見ました。東京オリンピックを控えていたので、日本でも起こりうる問題だと感じました。
父はデザイナーとして建築に関わっていましたし、現場で建設に携わる人々も、建物をつくることにこだわりを持って従事している方々なので、言ってみればクリエイターです。そんな彼らが自分たちが生み出した価値に見合った対価を得られているかと言えば、間にいろいろ入っているはずなので、そうではないだろう。「自分の人生を使うのはここだ」と思いました。この着想を得たのが2012年のことです。その翌年にシェルフィーを立ち上げました。








