全分野のエキスパートがチームを結成
建設工事紛争審査会は、弁護士を中心とする法律委員や建築・土木・電気・設備などの技術分野の学識経験者、建設行政の経験者などの専門委員で構成され、専門的かつ公正・中立な立場で紛争の解決に当たります。
この事例では7月と11月の2回、現場にて工事瑕疵についての立ち入り検査を行い、請負人に対しては工事瑕疵の補修を命ずるとともに、発注者に対しては工事残代金の支払いを命じました。瑕疵の責任について審査をして、有償の追加工事と瑕疵補修工事を判別して、気持ちのすれ違いも乗り越えて仲裁に至っています。仲裁に至る期間は平均的に1~2年だそうです。
なお、審査会の行う調停や仲裁の手続は、原則として非公開です。上記の事例は書籍『建設工事の紛争処理』(建設工事紛争研究会/清文社/1981年)に掲載されていたものです(余談ですが、図書館でお借りした定価2,400円のこの書籍、ネット書店で10万円近いプレミアム価格になっていました)。
建設工事紛争審査会に申請するメリットとデメリット
建設工事紛争審査会への申請にはメリットとデメリットがあります。
メリット:裁判に比べて簡易・迅速な解決が期待できます。標準的な期間は、あっせんが4か月程度、調停が6か月程度、仲裁が1~2年程度とされています。
デメリット:裁判における確定判決と異なり、相手が合意内容に従わない場合でも強制力がありません。また、相手が話し合いに協力しない場合は、手続きが進まないこともあります。
建設工事紛争審査会については国土交通省のサイトで確認できます。『請求価額100万円までのあっせん申請手数料1万円』から始まる申請手数料の算出表もあり、費用等も明確です。タイパ、コスパともに良いため、万一の紛争のときは、選択肢になり得るかと思います。
参考:建設工事紛争審査会
「施工管理求人ナビ」では施工管理の求人を広く扱っています。転職活動もサポートしていますので、気になる方はコチラからご相談ください!

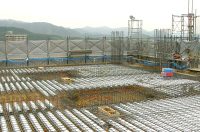






このオジサン面白い記事書くなぁw
私的には好きです!
建設工事紛争審査会って国交省の管轄組織ですよね。余計に発注者側が有利な結末にされるのでは?
ちゃんと、弁護士に頼んで司法の場で白黒つけた方が良いと思いますがね。
なんなら、メディアも使いましょう。