昔は別々のチームだったが、今は全員野球
――以前、砂防、河川、海岸にはそれぞれの考え方があって、けっこうバラバラだという話を聞きました。あと、流域治水に関しては、「全員野球でやるぞ」という掛け声は聞いたことはあります。実際は、どんな感じなんでしょうか?
室永さん まさに今、全員野球でやっている取り組みがありますよ。「土砂洪水氾濫」という現象、砂防が担当する土石流と河川が担当する洪水の中間の現象について、砂防の部隊と河川の部隊がタッグを組んで、流木も含め、メカニズムなどを工学的に捉えようとしているところです。
私は入省して25年ですが、昔の話で言えば、確かに、砂防、河川、海岸は、それぞれのフィールドのことだけをやっている感じはありました。私の知る限り、10年ぐらい前までは、別々のチームでしたね。
ただ、今はかなり状況は異なっています。砂防、河川、海岸は、以前と比べれば、かなり一体になって、いろいろなことを議論するようになっていると思います。
[PR] 転職に成功する施工管理と失敗する施工管理の「わずかな差」
海岸事業はオールインワン、全部自分たちでできる
――室長として、組織マネジメント上で、気をつけていることなどはありますか?
室永さん さきほども触れましたが、海岸が初めての職員もけっこういるんです。海岸事業とはなんなのかというところから、しっかり、丁寧に伝えるよう気をつけています。
海岸室に配属される職員は基本的に優秀なので、飲み込みがむちゃくちゃ早い職員ばかりです(笑)。海岸事業のイロハやわれわれのミッションを伝えると、すぐにそれを飲み込んで、アクションに移してくれます。
あと、職員に必ず伝えることにしているのが、「海岸室はオールインワンだよ」ということです。なにがオールインワンかと言うと、海岸室は、法律を持っていて、事業を持っていて、管理を持っている、つまり、行政として必要なものは全部持っているということです。こういうセクションは、国土交通省の組織の中でも、珍しいんです。
所帯は小さいですが、海岸室に来た職員は、仕事を楽しんで、やりがいを感じてくれます。それは、オールインワンだから、全部自分たちでできるから、というのが大きいと思っています。私自身もそうでしたし。「ここまでにいろいろなものを動かせるんですね」と驚いていた職員もいました。
逆に、それに気づいた職員が勝手にドンドンやることもあります。そのときは、さすがに「やりすぎ、やりすぎ」と抑えに入りましたけどね(笑)。基本的には、職員に任せて、勝手に走ってもらってかまわないというスタンスでやっています。
――あとは、都道府県とのやりとりという仕事もあるわけですね。
室永さん ええ、その仕事がスゴく多いですね。都道府県は海岸事業の主役なので。お金の話とか技術的な話とか、やりとりの内容はいろいろですが、相談件数はかなり多いです。河川と比べると、圧倒的に多いんじゃないでしょうか。
技術的な相談については、国総研の海岸研究室にお願いしています。海岸研究室のメンバーは、海岸保全技術に関しては日本の最高峰を担っていて、スゴく優秀なので、都道府県の職員に技術指導することもあります。スゴく大事な仕事なんです。
上に課長がいない室長なので、できることが圧倒的に多いのが魅力
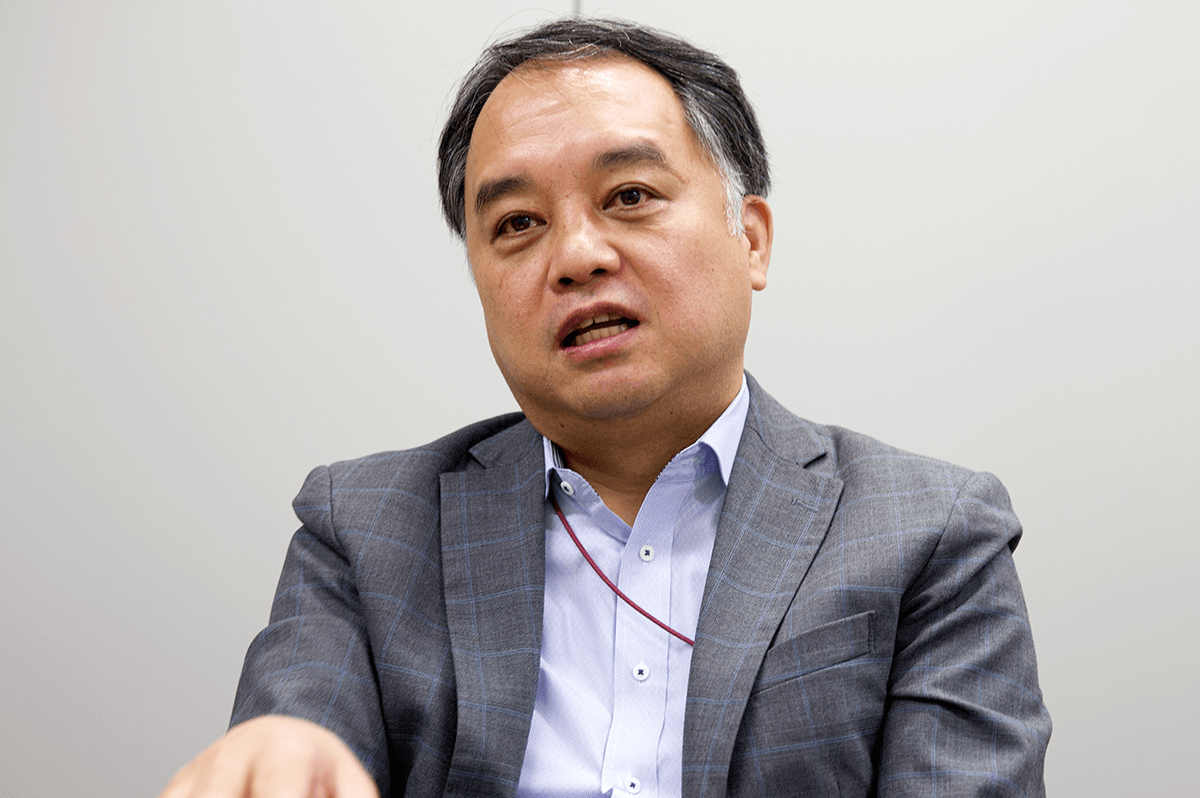
――室永さんにとって、海岸室の魅力はなんですか?
室永さん 海岸室ということで言えば、さっき申し上げたオールインワンで、法律も事業も管理も全部できるところです。
海岸室長ということで言えば、私はこれまで3回室長というポストを経験しているのですが、前の2回は私の上に課長がいました。でも今は、私の上に課長はいません。なので、いろいろなことを自分で決めることができます。前の2回の室長と比べると、できることは圧倒的に多いです。
たとえば、私が海岸法を変えたいと思えば、立案できます。とにかくオールインワンなので、ほかのセクションだと、局長が決めるようなことを、私が決めることもできるんです。もちろん責任を伴うわけですが、楽しみながら仕事ができていますね。
――課長会議に出れるんですよね。
室永さん そうです。課長扱いなんです。ただ、これに関しては、私としては非常に不満があるんです。同一労働、同一賃金のはずなのに、課長の給料がもらえないからです(笑)。課長見習いをさせてもらっている感じですかね。
海岸を愛している方々と一緒に行動することが、なによりの事業PR
――海岸事業のPRについて、どうお考えですか?
室永さん 昔の海岸事業は、防護、利用、環境の3本の柱のバランスをとりながら事業を進めていました。ところが、東日本大震災以降、防護の比重がグッと大きくなりました。防護は当然、今も今後も大事な柱ではありますが、一方で、利用と環境をおろそかにしてはならないと思っているところを後輩や都道府県含め、どう価値観を共有するかが重要なんです。防護一辺倒ではなくて、環境と利用のバランスをどうとるかを考えなければなりません。
海岸には、サーファーの方々をはじめ、ウミガメや野鳥を観察する方々とか、いろいろな利用者がいらっしゃいます。海岸に関わりを持ちたいというポテンシャル的には、河川よりも海岸のほうが圧倒的に多いと推測しています。こういう方々と一緒になにかをやりたいということで、今まさに、いろいろと検討しているところです。
たとえば、先日、海岸室の職員が福岡県で開催された砂浜保全に関するシンポジウムに呼ばれて行きました。地元の高校生が学校の目の前にある海岸の生態調査や測量をやったりして、最後に「この海岸のデータホルダーになりたい」と言ってくれた、という話を聞きました。
このシンポジウムには、地元のサーファーも来てくれて、波は海底の地形に左右されるもので、去年波が立った場所が、今は、海底の地形が変わったので、波が立たなくなっている、自分たちはカラダで海底の地形、その変化を感じることができる、というお話をされたそうです。
こういう海岸を愛している方々は、全国たくさんいらっしゃると思います。日々海岸に触れている方々なので、海岸のちょっとした変化や違和感を感じる方もいらっしゃると思います。そういう方々とお話をすると、「海のためになにかしたい」とおっしゃるんです。
われわれは、そういう方々とどうつながるか、どうコラボしていくか、手探りなところがあるとしても、流域治水の全員野球の先駆けとして、サーファーや高校生など、海岸を愛する人々と一緒に、どう良い海岸をつくっていくか、具体的に考えていきたいと思っています。
前置きが長くなりましたが、事業PRをどう考えるかについては、PRするまでもなく、目の前に海岸を愛している人々がいるので、彼らとコラボレーションし、なにか行動することが、われわれに求められていることです。そういう活動を続けていくことが、結果的に最高の事業PRにつながるのではないでしょうか。彼らが最高のサポーター、最高のパートナーになってくれるよう、われわれとして、しっかり行動を起こしていきたいと思っています。
人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!
「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、
こちらからお気軽にお問い合わせください。






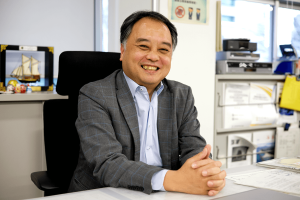
海岸事業を全国一律で考えるのはやめてください。太平洋と日本海では現象が全く違います。片方で必要なことでももう片方は必要ないことがあります。あと海岸事業でもうすることがないからといって効果が薄いこと進めないでくれ、都道府県は暇じゃねぇんだよ。