「重機や機器は自前」という会社の風土が「内製化」の礎に
吉川さん 弊社は1950年に私の祖父が創業したのですが、祖父はとある県の県庁に勤めていました。詳しい経緯はわかりませんが、当時の建設省と一緒に仕事をしていたそうです。それまで直営で行っていた工事を民間に請け負わせる制度が始まるということで、建設省の職員の方から促されるカタチで、祖父は役人を辞め、弊社を起業したそうです。なので、最初の仕事は建設省でした。
森下さん そうだったんですね。
吉川さん 昔は苦労したようですが、いろいろな経験を経た結果、「重機は自前で持つ」という会社の体質ができあがりました。私が弊社に入社したのは20数年前ですが、そのころにはすでにそういう体質でやっていました。当時の建設業界には「重機はレンタルにしたほうが利益率が高い」という雰囲気がありましたが、お構いなしに、自前で重機を揃えていました。パソコンなんかも最新のものを導入していたんです。
そういう会社の風土があったので、ICT重機も自前で持つ、デジタル測量機器も自前で持つことになったわけです。「3回使ってもとがとれるなら、買ってしまったほうが良い」という考え方でやっています(笑)。
森下さん わかりやすいですね(笑)。
吉川さん 機械や機器は、新しいものが出ると、どんどん入れ替えていっています。レンタルだと、オペレータもレンタルすることになりますが、自社保有であれば、自社のオペレーターを育てることができます。機械と人の内製化ができるようになるわけです。
たとえば、3Dレーザースキャナーで言いますと、自社保有していない場合は、レーザースキャナーを使わなければならない状況になってから、レンタルして使うことになると思います。自社保有していると、これは実際にあったことですが、発注者から急に「護岸の動体観測をしてほしい」とリクエストされても、レーザースキャナーの差分で計測することができます。こういうのは、自社保有しているからこそ、できる使い方だと思っているんです。内製化することで、重機や機器などの使い方の幅が広がると考えています。
機械職の人間にとって、建設現場の生産性向上はDNAのようなもの
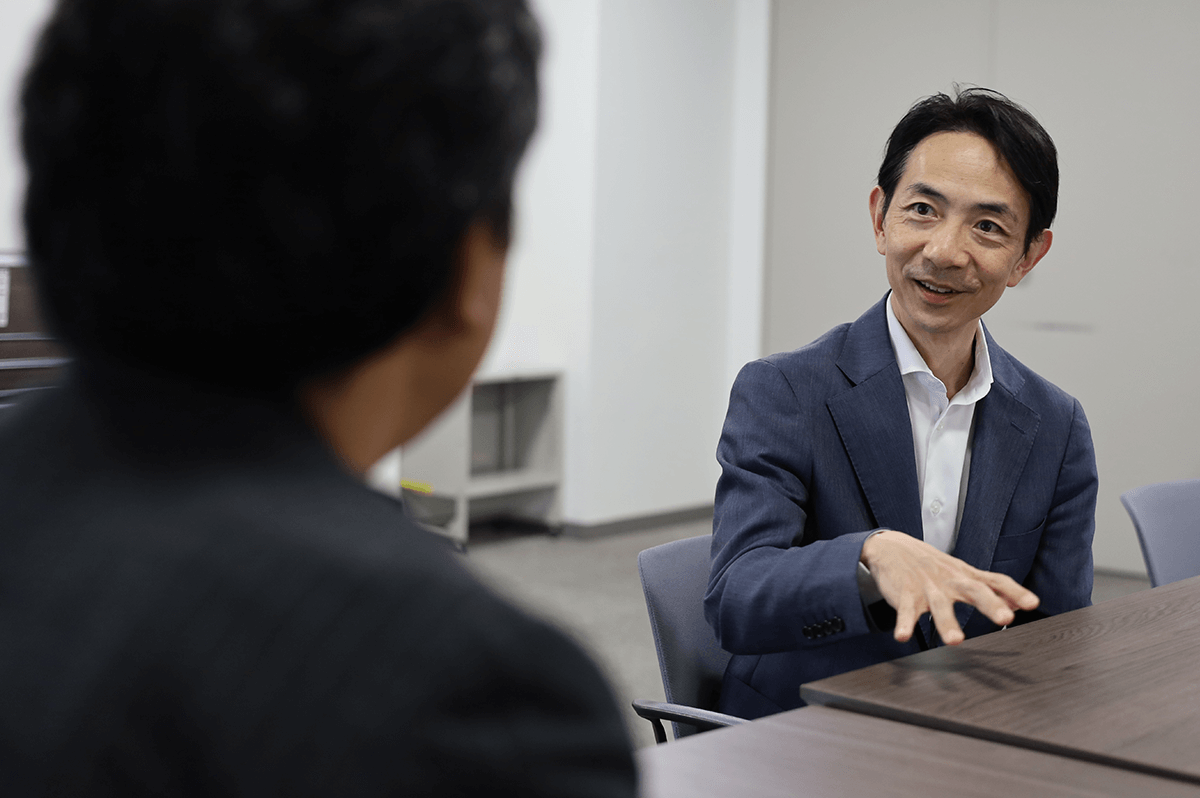
森下さん 私は機械職として入省したのですが、機械グループのご先祖様は、国が直営で工事をしていたころの機械エンジニアの方々です。機械グループの方々は、当時から「建設現場の生産性を上げる」という思いをお持ちで、「人力施工から機械施工へ」ということでお仕事をしておられました。生産性を上げるという使命感は、今でも脈々と受け継がれています。機械職の人間にとって、生産性の向上を追求することは、DNAのようなものです。
平成に入って間もないころ、日本の民間企業の間で情報化施工が盛り上がったことがありました。そのときは残念ながら、海外にさきを越されてしまいました。その後、捲土重来ということで、情報化施工推進戦略が策定されました。この戦略づくりには、私も課長補佐として携わりました。
そのときのわれわれの認識は、建設現場の生産性の向上は、機械化によって終わったわけではないというものでした。さらに生産性を向上させることができる。そのキーになるのがICTだ。建機などにICTを組み合わせることで、それを実現していこう。そういう考えのもと、民間の建設会社が持っている建機をICT化させるための施策を講じることになったわけです。
最初のころは啓発活動が中心でしたが、i-Construction大賞が始まったころからはICT施工に必要な費用も国が負担することにしました。これ以降、ICT施工が一気に普及するようになったわけです。
ICT施工で止まってはいけない。自動化や自律化で更なる生産性向上を
森下さん 私は今のICT施工のままで止まってはいけないと思っています。自動化や自律化を進めることで、生産性はもっと上げられると考えているからです。たとえば、一つひとつの機械をそれぞれ人が操作するのではなく、複数の自律的に動く機械を一人の人間が監督する、しかもそれを遠隔でやるというイメージです。建設現場をそういう世界に持っていきたいと考えています。
金杉建設さんにとって、内製化が一つのDNAとなっており、これを受け継ぐことによって、先駆的な取り組みを実現できたということが、よくわかりました。素晴らしいマインドだと思います。建機などのレンタルはそれはそれで日本の建設業界の強みになっていると思っていますが、イノベーションを起こすには、建機などを自社保有し、常日頃から機械を使える環境があってこそというのは、説得力のあるお話だと感じました。
吉川さん 弊社でも重機をレンタルすることがあるのですが、自社で改造して、マシンコントロールを後付しています。その際には、リース会社に対して「後付けのマシンコントロールを溶接するけど、そのまま返却しても良いか」とちゃんと相談してから行っています。協力会社さんが自前のバックホウを使う場合も、弊社のほうで後付けのマシンガイダンスを装着するようにしています。
森下さん 協力会社さんの反応はどうですか?
吉川さん 基本的には歓迎していただいています。たとえば側溝の据付けで言えば、以前は弊社の社員が座標などを管理しながら作業を行なっていましたが、最近は、協力会社さんが主体となって座標などを管理し、弊社社員は最終チェックするだけといったカタチに移行しています。弊社だけでなく、協力会社さんも一緒にレベルアップすることは、大事なことだと考えています。
機械だけでなく、データづくりの内製化もカギになる

森下さん 側溝据付けのお話がありましたが、小規模工事へのICT施工導入の成功の秘訣はなんだとお考えですか?
吉川さん 実は、小規模土工ではありましたが、小規模工事ではなかったんです。側溝の掘削、据付け自体は小規模工事なのですが、それを含む工事全体としてはそれなりのロットがあったということです。数百m程度の側溝工事単体の発注であれば、受注者がそのためにマシンコントロール付きのバックホウをレンタルするということはあまり考えにくいです。
ただ、今回の場合は、弊社がマシンコントロール付きの小型バックホウを自社所有していたので、ICT施工でやったわけです。たまたまアールのかかった少々面倒な側溝据付けだったので、丁張りをかけたくないということもありました。
森下さん やっぱり、常にICT建機を使える環境があるのが大きいんですね。必要なときだけ機械を調達するとなると、やはり、その現場だけではペイできない、普通にやってしまおうというマインドになってしまうのですね。
吉川さん 弊社の場合は、3D設計データも自社で組めるのもあると思っています。データづくりを外注に出すと、何十万円もかかってしまいますが、自前なら、1〜2日でデータを組んで、重機にデータを放り込むだけで済みますので。
森下さん データづくりの内製化も大きいということですね。




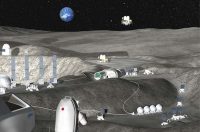



土木系はいいよね。。。
現状知ってると若い子が新しく入るなら土木の方がいいだろうなと思うんだけど
(CIM等の省人化技術の推進、快測ナビ等スマホで仕事ができる)
やっぱり建築の方が人気なんだよね