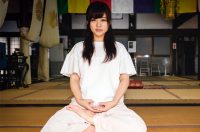「工事情報共有システム」はもう浸透している!
「工事情報共有システム」とは、ASPという情報共有システムを活用したもので「ASP型工事情報共有システム」とも呼ばれます。ASPとは「アプリケーションサービスプロバイダ」の略称です。
なんのこっちゃ、よくわかりませんよね?
ウィキペディアでは次のように説明されていますが、これも、なんのこっちゃ、よくわかりません。
「ASPはアプリケーションソフトの機能をネットワーク経由で顧客にサービスとして 提供することであり、それを行っている事業者である。通常、利用者はブラウザソフト などを使用してインターネットなどのネットワークを経由し、遠隔地からASPのサーバにアクセスすることで、そのサーバ内に格納された各種アプリケーションソフトの機能をサービスの形で利用する。」
・・・簡単に説明すれば、民間のプロバイダ(システム会社)と契約し、その契約先のソフトウェア(ソフトウェア稼働環境)を使用して、工事に関する情報を共有する、というシステムです。
自分でソフトウェア稼働環境を準備する初期投資、維持メンテナンスやセキュリティに関するメンテナンスコストを考えると莫大な金額になるので、プロバイダに小額の利用料を払うことで、「工事情報共有システム」の環境を全て整えることができます。
こういう商売をしている会社(プロバイダ)が20社ほどあり、そのほとんどが24時間365日の運用・監視体制と万全のセキュリティ対策を整えているので、自身でデータ管理するよりも、はるかに安全です。
「工事情報共有システム」(ASP)の開発経緯
「工事情報共有システム」(ASP)が開発された経緯としては、次のような建設現場の問題点を解決する目的がありました。
- 電話での情報共有
→記録に残らない - FAXによる情報共有
→セキュリティなし - 電子メールによる情報共有
→記録が個人に依存、送信容量に限界 - ファイルサーバーによる共有
→アプリケーションがない、アクセス制御が難しい、セキュリティ不安
こうした課題を克服する仕組みとして、「工事情報共有システム」(ASP)が開発されたわけです。
余談ですが、「工事情報共有システム」の始まりは、10年以上前に出てきたキーワード「CALS/EC」(公共事業支援統合情報システム)です。私自身、CALS/ECの発展に寄与してきた経験を持っています。
◎CALS/ECの3大要素
- 情報の電子化:情報を紙に出力することなく保存・授受を行う。
- 通信ネットワークの利用:電子化された情報をインターネット回線で受け渡し。
- 情報の共有化:データを一元管理することで、常に最新のデータの活用。
それが具現化したのが、今の「工事情報共有システム」です。国土交通省では、「工事情報共有システム」の全国的に導入を推進し、いまや必須アイテム。これなしでは、もはや仕事が進みません。
「工事情報共有システム」(ASP)の役割とは
「工事情報共有システム」(ASP)は、工事情報の共有と有効活用によって、次の役割を担っています。
- 事実認定=工事プロセスの証明
- 異なる組織間のグループウェア=発注者+ALL受注者+支援業務
- 受注者のアピールを可視化
- 災害異状時の基幹システム
その中でも「工事情報共有システム」の画面上で見て取れることは、「無条件で事実認定」される点が重要です。
例えば、
- 品質証明に係る体制が有効に機能していた事実
- 現場に対する本店・支店による支援体制が確立していた事実
- 監督職員への報告を適時・的確に行っていた事実
また「工事情報共有システム」は、施工中の利用に限らず、あらゆる検査時に役立つものです。