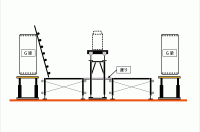学校の先生には分からない「建築施工の実践力」
鉄筋、型枠、コンクリート打設、誰がなんと言おうと、この3つが建築施工の基本だ。一年ぐらい建築現場に関われば、おおよそのことが分かり、大部分は現場の職人に任せておけば、何とか出来る。が、一つ一つ突き詰めて考えると、建築施工は途方もなく奥が深い。
そこで貪欲にどこまで考え、調べ、怒鳴られながらでも、現場の職人に分からない事を聞くかで現場管理者としての質が決まって来ると思う。それこそ学校では教えてくれない、いや、学校の先生が逆立ちしたって分からない、建築現場での実践力が養われていくのだ。
そう言う意味では、現場管理者には、平等にチャンスが与えられている!と言えるだろう。学歴なんぞ関係ない。どこの学校出ようが関係ない。真面目にコツコツ積み上げて来た人間が現場では最後に笑う!私はそう確信してる。
改修工事では「最初の区切り」を設ける
改修工事では、解体が進むにつれ、予想外の事が一杯出て来る。天井を取り去り、壁の仕上げを落とし、床を剥ぐと、躯体が剥きだしになり、設備関連も全部見えてくる。
私はここでガラなどを全部搬出し、現場を一度徹底的に掃除して、気分一新してから施主、監理者と共に現場を廻るようにしている。改修工事の場合、中々区切りがつきずらいので、私はこの時を最初の区切りと決めている。
当然、施主、監理者、施工者共に、予想外のものが目に入る。まずは現実を良く見て、その上で 図面通りに出来る事と出来ない事を把握し、それぞれの立場からどうしたら現状から理想の形に持って行くか考える。一切の隠し事なしに三者が一体になって問題に立ち向かう覚悟が出来ればいい。だから、この時間は大切なのだ。
施工者が現場を進めれば、監理者も腹を決める
皆が本音を語るようになれば、意見が食い違っても結論は近い。会議も実り多いモノになる。が、問題点が全部解決されるには時間が掛かるため、多くの課題はそのまま先送りされることになる。そんな時の打開策は、工程通りに現場をドンドン進める事だ。施工者側はそんな事に引っ張られてはいけない。もう猶予がないとなれば、施主も監理者も腹を決めざるを得ない。
しかし、この現場でも最後は設備にシワ寄せが行ってしまった。教室内の一部の新機種は調整等に手間取り、引き渡し後も作業が続いた。
竣工式が行われたが、私としては何となく終わったような印象の工事だった。もう少し出来たのに!と、やり遂げた感も薄かった。建物の出来は合格点に達したが、私の満足度は60点だった。大した挑戦もなかったし、新しい工法もなく、淡々と基本を積み重ねた現場だった。それが経験の積み重ねなのかな?とも思うがチョット違う。しかし、建築現場の施工管理とは、本来そうあるべきなのかも知れない。