入札不調2倍で東京都の工事執行に危うさも
入札契約制度改革の成否を問う前に、試行のポイントをおさらいしておく。
東京都が実施している入札契約制度改革の要点は次の4つだ。
- 予定価格の事後公表
- JV結成義務の撤廃
- 1者入札の中止
- 低入札価格調査制度の適用範囲の拡大
この入札契約制度改革の試行案は、何の予告もなく「都政改革本部会議」で内部統制プロジェクトチームから示された。2017年3月31日のことだ。当然、建設業界からは多くの戸惑いと不安の声が上がったが、問答無用で同年6月26日以降に公表する工事から入札契約制度改革の試行はスタートした。
すでに試行から半年以上が経過しているわけだが、2017年11月末現在の「入札契約制度改革の試行状況(検証用データ)」によると、大規模工事での11月末までの不調発生率は20.1%。2016年度では9.9%の不調であるため、改革以降、おおよそ2倍以上の不調率となっていることがわかる。このような工事遂行の不具合が露呈した中で、各団体との意見交換が実施されたのである。
東京都の入札制度改革は試行段階とはいえ、東京都内の市区町村の入札制度にも影響を与える。「JV結成義務の撤廃」が原因で地元の大規模工事に入札参加できない中小建設企業にとっては死活問題だ。アベノミクスで活況に沸く首都圏の建設業界だが、中小建設企業の受注機会の喪失につながっている改革からは目をそらすことはできない。そういう意味でも、東京都内の建設業界から意見を集約した東京建設業協会との意見交換には注目が集まった。
入札参加意欲は減退。1者入札中止の廃止を求める
東京都と東京建設業協会の意見交換は、小室一人・東京都財務局経理部長と、飯塚恒生・東京建設業協会会長の挨拶からはじまった。

小室一人・東京都財務局経理部長
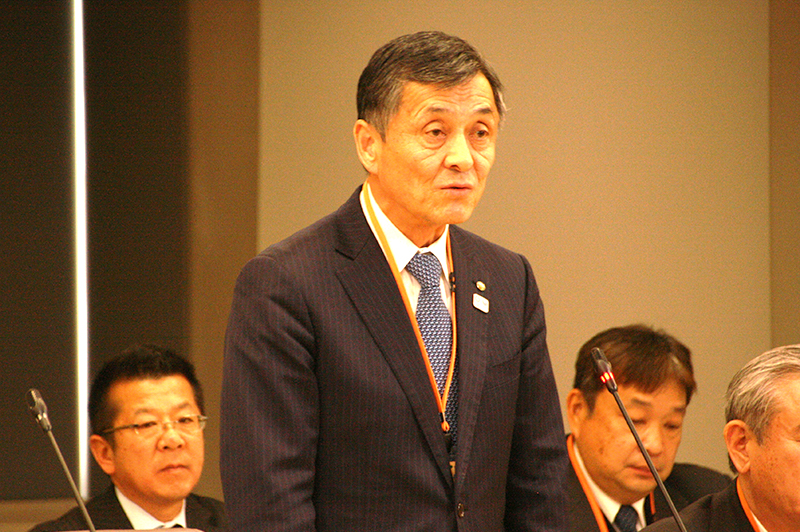
飯塚恒生・東京建設業協会会長
東京建設業協会の飯塚会長は東京都側に対して、まず次のような言葉を投げかけた。
「試行開始にあたり、東京建設業協会からは東京都に対して、会員企業の戸惑いの声、中小建設企業に対する経営の配慮などをお願いした。試行が進められる中、会員の声をあらためて確認したが、入札参加の意欲は少なからず減退しており、試行の一部見直しや改善など数多くの要望があった。建設業界の担い手確保・育成のためには、処遇改善や働き方改革の推進が不可欠であり、これは発注者である東京都の協力なしでは出来ない。大雨、地震などの災害に対応するためには、会員の多くを占める中小建設企業の経営基盤の確立が必要不可欠だ。制度改革にあたってはその点を配慮して欲しい」。
東京建設業協会からの意見要望をまとめると、次の6点である。
- 予定価格の事後公表に係る施策の改善
- JV結成義務の撤廃に係る施策の見直し
- 1者入札中止の廃止
- 低入札価格調査制度における数値的失格基準の引き上げ
- 週休2日の達成に向けた工期設定の徹底
- 週休2日を前提とした技能労働者の賃金水準の確保
「1.予定価格の事後公表に係る施策の改善」については、国土交通省の発注図書と比較すると、東京都の考えている工事内容の情報は少ない、という意見が東京建設業協会の会員企業から寄せられているという。そこで要望したのが、次の4点だ。
- 積算に必要な情報のさらなる提供
- 見積期間の延長
- 工事発注規模の区分見直し
- 予定価格の事後公表の一部見直し
「a.積算に必要な情報のさらなる提供」とは具体的に、「全案件での工程表の公表」「数量内訳書における数量表示の改善」「見積りや特別調査により決定している単価などの公表」「設計成果品の作成月や設計上条件となっている期間(使用機械の損料期間など)のさらなる明示」の4点の情報提供を求めた。
これに加えて、設計図書への質問に対して東京都が明確に回答できないケースもあり、この点も東京建設業協会は要望した。積算にかかわる労力は大きく、しかも東京都の工事は、見積り参考資料の提示が国土交通省と比較すると、必ずしも入札公告時ではないため業界からは不満の声が高い。「とにかく、東京都の見積りにはいつも泣かされる」(東京都内の中小建設企業社長)という声もあり、見積期間の延長も要望に含まれた。









