北海道地震の液状化とアンダーピニング工法
北海道の拡い範囲は「ピート層」と呼ばれる含水率の高い土質になります。すると、高額ではあるものの、もっとも修復後の安定性が高いと言われている「アンダーピニング工法」を選択する場合があると考えられます。その際の注意点を書きます。
ピート層内の鋼管は腐食しやすい傾向が考えられるので、「防錆処理」や「腐食しろ」分を考慮した肉厚にするなどの対策をしなくてはなりません。しかし、底板下での圧入作業をする側としては、抵抗を少なくして、なるだけ薄いものを入れたいと考えるので、耐久性に問題が生じる場合があります。また、ピート層は圧縮性が高く、杭頭付近の腐食が生じやすいので、特に十分な対策を講ずる必要性があります。
こうした腐食の問題を解決するために鋼管杭ではなく、コンクリート杭を使用する場合もあります。ただし、これは駐車場に置いてある輪止めのようなコンクリートを「積み重ねてゆく」工法ですので「挫屈」(折れ曲がる)の可能性が高いという難点があります。コンクリート杭によるアンダーピニングの場合は、挫屈しないようにサイコロ状のコンクリートの真ん中に穴を開けてそこに鉄筋を通す工法もあるようです。
アンダーピニング工法は沈下修正工事の中で唯一、岩盤層もしくは中間支持層と呼ばれるN値(地盤の固さを示す数字)が充分だと考えられる位置から「反力」を採ることで家を持ち揚げます。手間もかかりますので、浦安市で行われていた工事でも1200万円前後の工事費が多かったです。
耐圧板工法と土台揚げ工法
耐圧板工法は一般の方からすると「基礎ごと」持ち揚げるわけですから、外から見た目には、ほとんどアンダーピニング工法と同じように見えます。
しかし、この工法は、深く杭を打つことを諦めて、底板から1m程度の深さのところに厚さ16mm 60cm×60cm程度の鉄板を敷いて、地盤との設置面を増やして反力を獲って、その上にジャッキを掛けて持ち揚げるものです。

耐圧板工法
ほとんどの木造2階建ての重量であれば、地表から2m以内で反力は獲れますので、木造住宅で「耐圧板工法」を選択することはありだと思います。
しかし、上記2つの工法(アンダーピニング工法と耐圧板工法)に関しては、北海道の事情に照らして、もう一つ懸念されることがあります。
それは「地下水位が高い」ことです。地下水位が高いとトンネルを掘る作業する際に、排水工事費用が大きくなります。茨城県神栖地区では、排水手間だけで150万円ほどかかっていたお家も見ました。また排水は地下水位を下げてしまいますので、近隣の住宅に影響を及ぼすリスクもあります。
その点、「土台揚げ工法」であれば、地下水位の問題もありません。浦安市入船地区では「布基礎」のお家が多かったことと、この水位の問題から「土台揚げ」工法が多く選ばれました。

土台揚げ
しかし、土台揚げは地盤改良を伴う工事ではありませんので、地盤が安定していること、再沈下が起こる可能性があることを認識しておいていただなくてはなりません。それでも1棟あたり300万円前後で沈下修正工事が出来ることから選ばれていました。





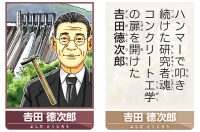




札幌が地元の身としてはこういう情報はありがたい!
こういう情報こそ、地元の建設業者の人に届いて欲しい!
ありがとうございます。少しでも役立つと良いんですが・・。みなさん将来を考えてご心配されているでしょうから。
行政に届け!
ありがとうございます。なかなか行政の方は自分のような現場職人の意見に耳を傾けてくださらないです。大学教授など肩書きが無いと駄目です。
実地の意見を聞ける機会は少ないのでありがたい。後学の為本買わせていただきます。
ありがとうございます。職人も、建築士や工務店に文句ばかり言っていないでもっと発言しないといけないですよね。本は「主婦と生活社」ですから、本格的な専門書というわけではないですが。現場の汗を感じていただける内容だと思います。それと・・ゴーストライター説がありますが、編集はされてますが・・・97%自分の文章です(笑)