法令・基準類に関する情報の集約
実際にドローンや建機を動かす中心となるのは、地場の建設会社である。よってゼネコンの役割は、いかにi-Constructionを実践する立場の人たちが動きやすい環境を作ることができるか、ということになる。それには、まず現場職員がi-Constructionの関係法令や品質基準を知っておかなければならない。
これが先に挙げた「法令、基準類に関する情報の集約と維持」という論点だ。
幸いなことに、i-Construction関連の法令や基準は国交省のHPに集約されているから、必要な時はそこを見ればいい。しかし、これらの法令、基準は時期刻々と変化するので、最新の情報を確認することを徹底させる必要がある。
同時に、社内で蓄積されたノウハウの集積もまた重要な課題となる。私自身、これらの法令や基準に目を通してはいるが、実際のところ分かりづらい。空撮による測量を例に挙げれば、基準点の設け方や高度、毎秒何回シャッターを切ればいいかといった、具体的なことは一切分からない。
この手の情報を一手に持っているのは機器メーカー、レンタル会社、そして先んじてi-Constructionを行なった社内の現場監督だ。これらの情報を集約しなくては、難しい書類を前にして一歩も前に進めない事態が発生する。そのため、全社的なノウハウの引き継ぎ(ナレッジトランスファーという)ができる仕組みを取り入れなければならない。
文章化できるものは社内のサイトなどに集約し、機器メーカーやレンタル会社とは定期的な技術交流会を実施すべきである。これは機器メーカーやレンタル会社にとっても、自社の営業活動になるから双方に利益をもたらす。また、実際に現場でi-Constructionを実施した職員には、社内勉強会などに積極的に参加してもらわなければいけない。
このような場を設定するためには、音頭を取るための組織が必要になる。ゼネコンの中にはIT部門やi-Construction専門の部門を設けている企業もあるが、これらの組織が先導して運営をしていかなければいけない。
機器調達と運用
また、機材の調達も重要である。国交省によれば、i-Construcitonを取り入れる際の機器は、その100%が機器レンタル会社からのリースだという。しかし、同時に大手の機器レンタル会社4社にヒアリングをしたところ、現状i-Constructionに関わる機材を十分に揃えている企業はいなかった。
これらの結果を踏まえると、現地で機器レンタル会社を通じてi-Construction機材を揃える現在のあり方では、対応が不十分である。ドローンなどは比較的安価で現場調達も可能だが、建機や測量機器となると多額の初期費用がかかる。
市場価格を見ると、後付けのマシンガイダンス機で数百万、測量機器で一千万円程度になるので、単独の現場で調達するのは現実的ではない。
これが2つ目の論点の「機器調達と運用」である。
この状況を打開するためには、比較的資金力のあるゼネコンやサブコンが全社的に購買し、運用を回すことが求められる。実際、大手のゼネコンは自社で重機を保有し、運用を行なっているから、この方法を重機以外にも適用すれば、限定的かもしれないがi-Constructionの適用現場の範囲は大きくなる。
このように言うと、いかにも簡単そうに思えるが、現実問題としてこの運用体制が実施されていないところをみると(というのは、私自身全てのゼネコンの内情を知っているわけではないからだが)、問題は機器の運用体制が整っていないことにあるだろう。
機器管理の人員確保
製造業においても、物を作るための道具の管理は非常に難しい。まだ工場内であれば機器の管理は比較的アルゴリズムを組みやすいが、屋外作業を伴う建設現場では、一度リースをしたら壊れて返ってくることも考えられる。
私の経験から言うと、ドローンは大抵一回でうまく飛ぶことはないし、飛んだとしても墜落する。また、ICT機器は繊細な取り扱いが必要で、かつキャリブレーションなど現地で調整しなければならないことも多いため、専門知識が必要になる。では、これらの管理を重機の管理と同じ人間ができるかというと難しく、新たに教育が必要になる。
これが3つ目の論点の「機器管理の人員確保」である。
昨今は深刻な人手不足が続いているが、このような専門性の高い人材の獲得はより難しい。企業戦略としては、第一にメーカーやレンタル会社から人を引き抜くという手を考えなければならない。ただ、日本企業全体に言えることだが、この手の人材の引き抜きは日本企業は不得手だ。そのため、採用が困難なら社員を再教育するしかない。
再教育の対象となる社員というと大体が若手一本槍になるのだが、デジタル化という大きな枠組みで物事を捉える場合、再教育の対象はむしろ上位階級の人員になる。
というのも、現場で裁量権が与えられている人物がデジタル化の仕組みを理解できていないと、現場での意思決定が遅くなるからである。また、何事も上位階級がやろうと言わなければ誰もやらないというのは、建設現場ではよく見受けられる。
よって、再教育対象は現場の基礎知識を持つ主任クラスから、実行の裁量権を持つ工事長クラス、またi-Constructionの実施の促す所長クラスを対象に実施したほうが良いと考える。
また、教育内容はそれぞれのクラス別に異なるほうが良いが、優先順位としては上の階級から教育を実施するほうが、全体統制が取りやすいというメリットがある。つまり、所長から工事長、主任というトップダウン式な教育方法が良いと思われる。
以上がゼネコンに対する提言であった。次回以降は順にサブコン、地場建設会社と提言していきたい。この記事が読者とその企業にとって少しでも役に立ち、現場を変える機会を与えるものになれば筆者としてこれ以上の喜びはない。
※注:これは筆者個人が独自に調査、検討を行ったものであり、筆者が所属する如何なる組織の見解ではありません。また記載内容については公開されている情報及び筆者がゼネコン所属時代に得た知見を元に執筆しており、現在所属する組織の如何なる知見も応用しておりません。





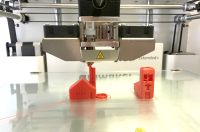




非常に参考になる記事だと思います。
発注者側は何をすべきかにも言及してもらえれば尚良かったです。
結局工事は発注者と受注者の二人三脚で行うものですから。
著者です。
ご意見ありがとうございます。
実は私もその点について考えておりました。
一方で発注者と元請け(ゼネコン)の関係性は複雑で、その点の分析が容易に出来ませんでした。私の知識と力不足が原因です。
この点につきましては順に考えをまとめていきたいと思っておりますので、今しばらくお待ち頂けますと幸いです。
長いだけで中身が無さすぎる。
著者です。ご理解頂けなかったようで申し訳ございません。
人には好みというものがございますから、相性が合わなかったということでご理解頂きたく思います。
原価償却とか会計のこと少しは分かってる?
著者です。減価償却と会計については一通り学んでおります。一応、そいういうビジネスもしておりますゆえ、必須でございます。
分かってると聞かれているということは、分かっていない部分があるということと存じます。
よければ、その箇所をご指摘頂けますれば、読者の皆様にもご参考になりますかと思いますのでよろしくお願い申し上げます。
わり、誤字。減価償却
「受注者は生産を開始するために専門業者に分離発注を行う。この発注先がTier1(一次下請け)となり、一般にサブコンと呼ばれると」ありますが、建設業界では設備業者のことを一般的にサブコンと言いますね。
一般的には協力会社、下請けと呼んでます。
それと、ゼネコンが負担せよみたいな記事ですが、ゼネコンはボランティアなのでしょうか?
まぁ知らんが、元請けが全部何でもかんでもやる必要はないが
下請けに丸投げする業者もなぁと思う。
そもそもとして、特殊な部分をすべて完全に元請けが完璧に把握する必要はないといつも思ってます
元請けはその大きな公共プロジェクトを滞りなく安全に納税者に届けることだと思ってますんで。元請けの監理技術者がドローン運転するようになったら終わり。それは測量屋の仕事。監理技術者はその測量屋のドローンのドライバーの動きをみて安全や法律違反を是正し、正確な測量データを現場に反映させるのが仕事。