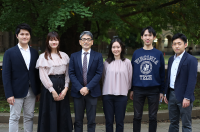アメリカでPhDを取って、海外のインフラ会社で働きたい
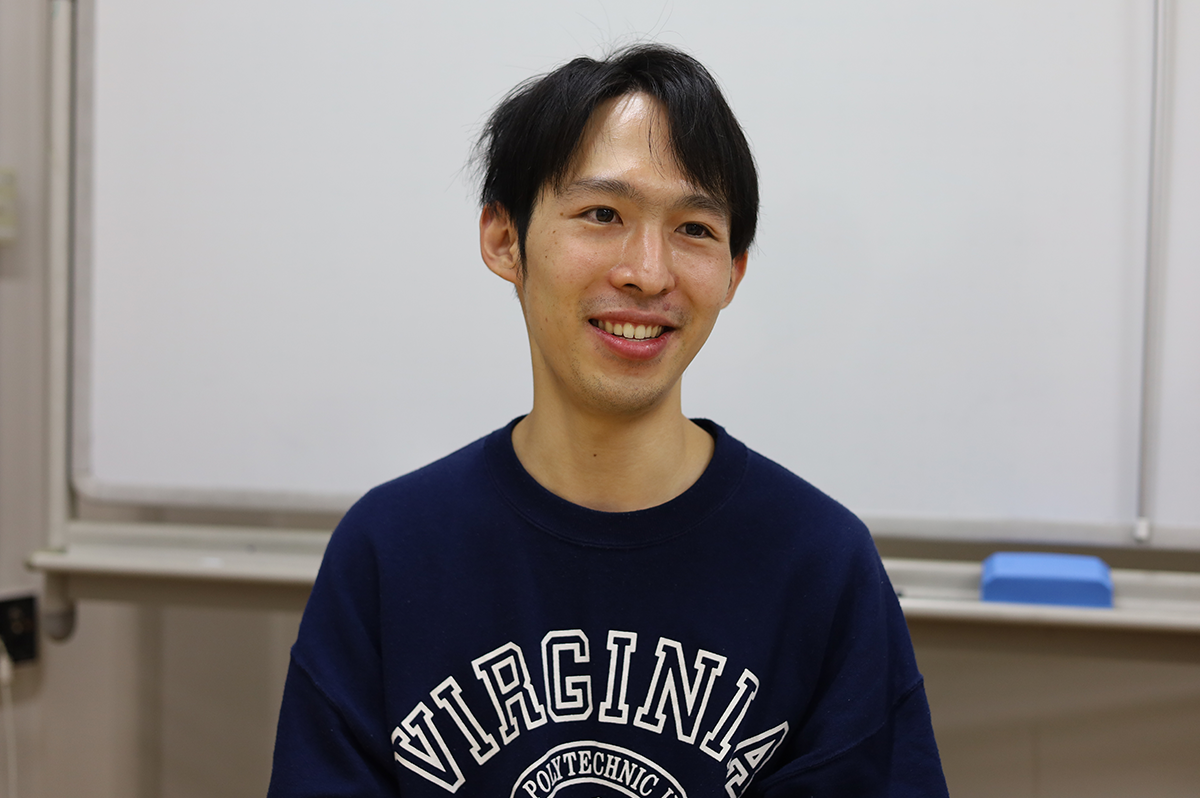
長田さん
――長田さん、今後のビジョンはどんな感じですか?
長田さん 開発途上国のインフラを整備したい、その国の人々に貢献したいという思いがあります。シビルエンジニアという立場から、自分の人生を賭けて成し遂げたいです。学部生のころに、東南アジアの国々に行った経験がもとになっています。
今、インフラプロジェクトのマネジメントに関する勉強をしているところですが、日本の企業で働くより、海外の企業で働くほうが、自分のビジョンを達成しやすいのかなと思っています。
と言うのも、日本の海外でのインフラプロジェクトは、ODA案件がほとんどです。ODA予算は今後、日本の生産年齢人口の減少とともに、減っていくと予想しています。あと、日本のエンジニアリング技術はレベルが高いがゆえに、現地化するためにカスタマイズする必要があるのですが、そこで日本の企業が苦労しているという現状があります。日本のインフラは海外ではオーバースペックになっていて、安くつくりたいという現地のニーズとミスマッチになっているということです。
ボクは、アメリカのとあるインフラ企業のインターンに行ったのですが、アメリカのシビルエンジニアの方々といろいろお話しする機会がありました。インフラ投資には、ODA案件のほかに、PPP案件というものがあるのですが、この会社は、開発途上国においてPPP案件の受注実績を上げている会社です。この手のインフラ会社は、アメリカ以外にもスペインやスウェーデンにもあることを教えてもらいました。
ボクの将来のビジョンを実現するには、海外のそういうインフラ会社で仕事するのが良いのかなと思っているところです。直近で言えば、修士が終わったら、アメリカに行って、PhDを取ろうかなと思っています。
――みなさん、海外志向ですね。
栗原先生 とくに意図はありません(笑)。
日本はPPP案件に対してスゴく閉鎖的
――将来はアメリカの会社を拠点にして、開発途上国でインフラ整備をしたいということですか?
長田さん アメリカと言うより、スペインですね。スペインにはACSという世界最大のインフラ会社あるんですけど、そこを拠点にして、開発途上国のインフラ整備を担うというイメージです。
――インフラビジネスという点において、日本と海外の違いはどこにあるとお考えですか?
長田さん 違いは2点あると思っています。一つ目は、「技術基準の違いによる契約形態の違い」です。日本は非常に自然災害の多い国なので、他国と比べ、設計基準が非常に厳しいんです。アメリカに行ったときにビックリしたのが、高速道路の橋脚の細さでした。日本は、設計基準が厳しいがゆえに、契約形態においてつくる側が強い傾向があります。海外はそこが逆なんです。発注側、設計側が強いんです。
2つ目は、先ほどお話しした「PPP案件の実績の違い」です。PPP案件とは、政府のお金を介さないインフラプロジェクトの契約形態ですが、日本国内での実績はほぼゼロです。たとえば、お隣の韓国では、海外の企業を招いて、PPP案件を成立させています。すごくオープンなんです。しかし、日本はスゴくクローズド(閉鎖的)なんです。その結果、韓国企業はPPP案件について学んで、韓国企業としてPPP案件の実績を上げています。日本企業は韓国企業に大きく水を開けられているんです。
とりあえず大学院に進んで、海外のインフラに役立つ仕事をしたい

塚田さん
――塚田さん、今後のビジョンはどんな感じですか?
塚田さん とりあえず東大の大学院に進むことが決まっています。大学院でもコンクリート研究室に所属して、現在携わっている研究を続けることを希望しています。その先については、まだ深くは考えてはいませんが、日本の企業に就職するのかなという感じではいます。自分が学んだことを活かせる仕事に就けたら良いなと思っていますが、どういう企業だったらそれが活かせるのか、まったく定まっていません。
――海外で働くイメージはない感じですか?
塚田さん そうですね。インターン経験もなく、実際に仕事をしたこともないので、海外で働く覚悟はまだまだできていません。ただ、以前インドに行ったことがあって、インフラという面で、日本との違いを目の当たりにしました。私の中では、このときの経験がけっこう引っかかっていたりするんです。長田さんと話がカブるのですが、「海外のインフラの役に立つことを、日本でできたら良いな」という、ふんわりとした目標は持っています。
「女子なのに、土木を選ぶのスゴいね」
―― 一般論として、「若者の土木離れ」が指摘されていますが、若者の1人としてどう考えていますか?
塚田さん 東大が土木工学科から社会基盤学科に変更したのは、「土木」という言葉を消すことで、学生を増やそうとする意図があったという話を聞いたことがあります(笑)。確かに過疎化が進んでいるジャンルだとは思いますが、社会にとって必要な分野ですし、誰かが担わないといけない仕事だと思っています。
実際に社会基盤学科で土木を学んでいる身としては、「土木という学問は、誇らしいジャンルだ」と思っています。とくに、コンクリートは誰もが当たり前のように利用している存在です。もっとたくさんの人が携わるようになると良いなと期待しています。
――たとえば、高校の友だちとかに「コンクリートの勉強してる」と話したとき、相手にこんな反応されたというエピソードはありますか?
塚田さん 文系の友だちに言うと、基本的に「えー、スゴい専門的なことをしてるんだね」という反応が返ってきます。基本的にはホメてもらえます(笑)。ただ、たまに「女子なのに、そこ選ぶのスゴいね」的な反応もあります。コンクリート研究室という名称が持つ、ある種のドロ臭さが起因しているのかなと思いますが、私としてはまったく納得していません(笑)。「そんなことないよ。実際は高度な数値解析なんかをやっているんだよ」と反論したくなりました(笑)。
人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!
「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、
こちらからお気軽にお問い合わせください。