神戸線を通行止めにして、フレッシュアップ工事を敢行
三嶋さん 保全第二課の後は、部内異動で当時の大阪第二維持事務所という大阪管内の南側の路線を維持管理する事務所に行きました。ここで、フレッシュアップ工事(在職時は堺線で実施)の現場監督を初めて担当し、諸先輩方からフレッシュアップ工事のイロハを教えていただきました。フレッシュアップ工事(現在のリニューアル工事)とは、1路線を数日間全線通行止めにして、ジョイントや舗装の補修を大々的に行う工事です。
その後は、大阪建設局工事審査課に行き、淀川左岸線建設工事などの積算業務をやりました。あと、当時は阪神淡路大震災後の耐震補強工事を全路線で行っていたため、建設部門においても、耐震補強工事を受け持っており、その積算・審査もやっていました。ここは1年だけでした。
また大阪管理部に戻って、管制管理課というところで、交通管制システムの更新設計や通行止めによるフレッシュアップ工事の交通影響予測業務などを担当しました。ここも1年でした。次は本社勤務となり、保全施設部保全計画室というところで、保全工事の積算基準の改訂や保全工事の積算審査をやりました。ここも1年だけでした。
次に、新任係長として湾岸管理部の調査設計課というところに行って、大阪管内の湾岸線の構造物点検、補修・耐震補強の設計などを担当しました。当時、鋼製橋脚隅角部の亀裂が問題になっていて、そのための調査や検討に関する仕事なんかもやりました。このとき、設計に関する実務に初めて触れました。
またまた大阪管理部に戻って、保全第二課の係長として、ふたたび保全工事の積算業務を担当しました。1年半ほどいた後、ちょうど民営化した時期に、神戸管理部の保全管理課に異動しました。予算管理、工事の発注計画、各種調整ごとといったことをやりました。
当時、神戸線は、交通量が多く、ゴッツい渋滞するので、通行止めによるフレッシュアップ工事を行っていませんでした。ただ、私が配属されたときは、震災復旧から10年ほどが経過し、ジョイントや舗装がかなり劣化し始めていたこともあり、大阪で実施している通行止めによるフレッシュアップ工事の検討を前任から引き継ぎました。そこで、以前とはネットワークが充実していることもあり、関係機関と調整を重ね、通行止めによるフレッシュアップ工事を実施しました。神戸線の通行止めは27年ぶりのことでした。ここは4年いました。
【PR】転職に成功する施工管理と失敗する施工管理の「わずかな差」
保全畑が長いが、自分が向いているかはよく分からない(笑)
三嶋さん その後、久しぶりに大阪建設部に戻って、淀川左岸線建設事務所で現場監督を6年やりました。
――けっこう長くいたんですね。
三嶋さん それまで担当として供用開始というものを経験したことがなかったので、「供用開始までここにいたい」と毎年希望を出して、念願が叶い供用開始に携わることができました。長く在職していると欲が出て事業完了までもと思っていましたが、その1年前に次の職場に異動となり、事業完了を最後まで見届けることはできませんでした。
次の職場は、大阪管理局保全部の保全管理課で、このとき管理職になりました。ここでは、地元対応や関連事業として大阪市から受託した咲洲・夢咲トンネルを管理する仕事もやっていました。ここは2年間でした。
その次は、保全管理課長としてまた神戸管理部に戻りました。神戸線のリニューアル工事や通行料金が対距離制になったので、本線料金所を撤去して、新たにPAを設置するといった仕事も担当しました。また、大阪北部地震や台風21号など災害対応にも追われたときでした。
本社の保全交通部保全企画課長として異動しました。国土交通省との調整や保全事業のとりまとめなどを担当しました。ここも2年いました。
その次が、前職になりますが、大阪建設部の担当部長として、淀川左岸線延伸部を担当しました。延伸部区間の工事は、国土交通省との合併施行ですが、現場着手に向けた協議・調整などに取り組んでいました。ここは1年だけでした。
――保全畑が長いですね。
三嶋さん 今年で入社30年目ですが、結果的に保全部門が長いです。保全にかかる部署はほぼ経験させてもらいました。自分が保全に向いているかどうかはよく分かりませんが(笑)。
土木と設備両方押さえておかないとダメ
――部長という立場になると、保全という仕事の見方も変わりますか?
三嶋さん 部長の立場というか、保全の仕事は、365日24時間、お客様が安全・安心・快適にご利用いただけるよう構造物や設備の管理を行っていますので、日々緊張感をもって業務に携わっています。保全としては、土木と設備の両面があるのですが、どちらかと言うと、これまでは土木中心で物事を見てきたところがあります。設備においても、お客様のご利用に直接影響を与える不具合などが起こりますので、職種が全然違い、知識も少ない設備のことについても、これまで以上にしっかり押さえておかなければならないと考えるようになりました。
――仕事量的にはどうですか?
三嶋さん 多いですね。現在リニューアル事業を精力的に取り組んでいます。喜連瓜破、阿波座、湊町では、規模の大きな更新・修繕工事が動いていますし、老朽化したPC桁などの橋梁の修繕、また、耐震工事など、数多くの工事を行っています。昔と比べ、工事数、工事規模ともに膨れ上がっています。現場の体制をもっと拡充できればと思っているところです。
――メンテナンス工事は、新設工事とは違った難しさがあると聞きます。
三嶋さん そうですね。住宅が近接し、交通量が多い供用下で、現場が狭い場所で施工することが多いのですが、その条件下で地元の皆様にご理解をいただき、安全に留意し、品質の良いものに仕上げるよう工事を進めていくことは、関係機関との調整なども含め、都市高速ならではのシンドいところだと思っています。






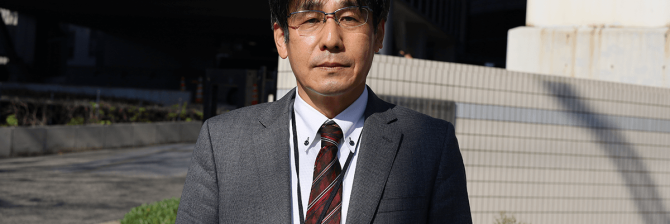
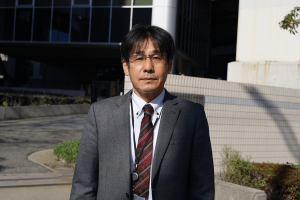
あんたら職員はいいけど、あんたらが雇ってる委託監督がうぜーんだよ。
検査に必要ない書類を要求してきて、立会でもえらそうーにしてやがる。
記事にあるお得意のコミュ術で部下は制御できても委託監督は制御できんようやな
おたくは偉くて現場の現状知らんやろうけど、あんたらが雇ってくる委託監督が、保身で作らせる、無駄な書類。あれ何とかしてよ。竣工検査で見ることなく終わるものばかり、、、
それと偉そうな態度。ほんまもんの発注者が偉そうにしとるのは100歩譲ってガマンするけど、なんでクソ委託が偉そうにしてんだよ
よくもまあ今の時代にメールだけだと人間味がないとかくっせえこと言ってんだよ。こんなんだから建設業界はいつまでたってもブラックなんだよ。