土木の仕事はピンとこなかったが、すぐ好きになった
有限会社礒部組は、高知県東部の奈半利町にある社員29名(うち土木技術者8名)の小さな会社です。今回お話を伺ったのは、礒部組の技術者を束ねる宮内保人さん。スキンヘッドが印象的な「おんちゃん」(土佐弁)ですが、「土木技術者はかくあるべし」という確固たる経験、哲学をお持ちの方で、さまざまな講演会や礒部組HP記事などを通じて、県内外に積極的に情報発信している熱血漢です。宮内さんの「土木魂」を中心にお話していただきました。

有限会社礒部組技術部長 宮内保人さん
施工の神様(以下、施工):宮内さんは、礒部組では長いんですか?
宮内保人(以下、宮内):礒部組にお世話になって、今年で27年になります。
施工:入社前、土木に興味があったのですか?
宮内:土木をやりたいという気持ちはまったくありませんでした。
施工:工業高校でしたか?
宮内:いえ、普通の高校でした。
施工:礒部組に入社した理由は?
宮内:県外で設備工事などの仕事をした後、高知にUターンして、仕事を探していました。そのとき、現在の社長に何回か声をかけてもらったからです。土木の仕事がピンとこなかったので、最初のうちは断っていました(笑)
施工:初めての土木の仕事はどうでしたか?
宮内:すぐ好きになりました。人様のお役に立てる仕事だからです。普通の暮らしを下支えするのが土木の仕事なので。駆け出しのころは、仕事をやっている間は、楽しいことなんてほとんどなく、辛いことばっかりでしたが、できあがったときの達成感、われわれがつくったものが人の役に立つことの喜びというものが大きかったです。やりがいのある仕事だと感じましたね。
施工:これまでどういったお仕事をしてきましたか?
宮内:田舎という土地柄から、都市土木はやったことがなく、山の仕事がメインでした。道路改良、砂防のほか、林道や治山などの森林土木、農業土木もけっこうやりました。
施工:山の仕事は楽しいですか?
宮内:どんな現場でも同じだと思いますが、土木の仕事では、同じものをつくることは二度とありません。例えば、海でテトラポッドをつくる仕事でも、端から見れば、他の場所にあるのと同じものに見えますが、現場が違えば条件も違うので、まったく別物です。山の仕事もそうです。
同じ条件が二度とない山の仕事では、先読みをして、優先順位をつけて、リスクを前倒しで解決していくことが、技術者のウデなんです。この辺が、土木の技術者がほかの分野の技術者と違うところです。もののディテールにこだわって、つくり込むことも大切ですが、全体を見通す力、マネジメント力こそ、土木技術者が身につけるべき能力です。もちろん苦労はありますが、自分の思う通りに仕事が進んだときの醍醐味は、格別です。
崩落の予兆に気づかなかったミス
施工:山の仕事の大変なところは?
宮内:山の崩壊とか落石が多いことです。何回も危ない目に遭いました。自分が数秒前にいたところがドサッと抜け落ちたこともありました。山が崩れる場合、必ず何らかの予兆があるんです。しかし、若いころはなかなかわかりません。土木は経験工学だと言われますが、経験を重ねると、その予兆がわかるようになってきます。突然山がドサッと崩れたように見えても、ベテランはその予兆を感じ取り、危険を回避した例は少なくありません。
私自身はその現場にいませんでしたが、3年ぐらい前、林道工事で大きな崩落がありました。20〜30mの山を切っていて、その下でコンクリートを打っているときに、その中腹辺りから、ポロポロと土が抜け落ちていたのを見たそうです。ベテランの作業員さんが「あれ?これはヤバイ」と思って、ほかの者に引き上げるよう指示し、その数分後、大きな崩落となりました。予兆に気づかなければ、7〜8人が生き埋めになっていたでしょう。
施工:予兆に気づかず、事故になったケースは?
宮内:気づかなかったことはあります。いくら経験を積んでも、工期などを気にして、自分に余裕が無いときには、適切な判断ができなかったことがあります。幸い事故にはなりませんでした。そのときは、運で助かったわけです。
6年ほど前、山の国道がズタズタになったので、応急で道路を通す仕事を担当したことがありました。ある日、かなりの大雨の中、作業をしていました。本来は作業を中止すべきところを、緊急だし、作業も山場を迎えていたので、私には、工事を止めるという選択肢はありませんでした。
作業員さんたちに「危ないので、止めましょう」と言われ、フッとわれに返りました。「じゃあ、片付けてから帰りましょう」と言うと、「メシを食わせてくれ」と言われました。自分もメシを食って、現場に戻ってみると、山が崩れていました。あと10分遅れていたら、私を含め、6名が生き埋めになっていたところでした。いかに緊急であっても、大雨の中で作業をやらせたのは、私のミスです。予兆があったかもしれませんが、結果的に見逃してしまいました。自分の心に余裕がなかったからです。
土木には、どんなヤツでもできる仕事、役割がある
施工:予兆を察知する能力は、経験を積めば身につくのですか?
宮内:経験を積んだだけでは、身につかないと思います。何十年やっても、身につかない人は身につきません。そういう人はいます。一方で、5年で身につく人もいます。これは、自分の経験したことから学ぼうとする意志があるかないか、の違いだと思います。のんべんだらりと過ごしていると、自分の身にはなりません。自分が体験したことだけを頼りにしても、やはり身につきません。人が経験したことを積極的に聞いた上で、自分が経験したことと合わせて、総合的に考えていく、学ぶ姿勢が必要だと思います。この姿勢がない人はたぶんダメですね。
施工:そういう姿勢は現場代理人に必要なのですか?すべての作業員にも必要なのですか?
宮内:みんなです。土木は面白い仕事で、飛び抜けて賢いヤツでも、けっこうアホなヤツでも、誰でもできる仕事なんです。どんな人でも、できる仕事や役割はあるんです。それが土木の面白いところです(笑)
土木は「勘」を磨くことが大事
宮内:「勘」という言葉があります。「勘」と聞くと、何か直感的、感覚的なものだと捉える傾向がありますが、私は違う風に考えています。私にとって、土木の世界での「勘」とは、経験を通じて、初めて身につくものなんです。経験で磨いていくものが「勘」なんです。
施工:「勘」は知性ですからね。
宮内:そうですね。知性と感性です。私は、土木技術者にとって、いちばん大事なものは、感性だと思っています。経験に基づく勘も含めた感性ですね。現場に立って、そこの空気とか、土とか、いろいろなものを感じ取れる力です。
カチンときても、相手の立場になって考える
施工:工事現場では、さまざまなルールやマニュアルがあると思います。そういったものに日々縛られていると、感性が働かなくなりませんか?
宮内:悩ましいところです。「場合によっては、ルールを無視します」とは絶対言えません。ただ、現実として、現場は生き物ですから、臨機応変に対応することも求められます。そのときは、しっかり発注者に説明する必要があります。どんなものを作りたいとか、どういう風に進めたいということは、はっきり話すよう、私自身教育されてきました。協議の結果、自分の考えが採用されないことは多いですが、それはそれで仕方のないこととして、自分の思いや意見は伝えなければなりません。
施工:お役人は融通がきかないことが多いと思います。カチンとくることは?
宮内:ありますね。「決められたことを守ってさえいれば、それで良い」という人もけっこう多いですから。正論、建前だけをタテに突き詰められると、現場が回らなくなります。ただ、そこをギリギリやられると、言われていることが正しいだけに、われわれとしては、なす術がありません(笑)
私は、そういう場合、「相手の立場になって考える」ことにしています。「仕事が進まないのは、小難しいことばかり言うお前のせいだ」と考えるのはカンタンですがね。そんな場合、物事の優先順位が違うわけですから、相手の優先順位がどこにあるかがわかれば、お互いの考えを近づけることができます。そういう努力も、現場をうまく進めていくために必要なことです。地元住民への対応も同じことです。そういう努力を続けていれば、世の中、そんなに悪いものではないので、なんとかなります。まあ、まれにどうにもならないモンスターもいますが(笑)
施工:土木技術者は、より高い、広い視野、視点を持つことが必要だと?
宮内:私は、土木の技術者はそうでないければいけないと思っています。少なくとも、そういう高みを目指す姿勢は必要でしょう。できるかできないかは別にしてもね。






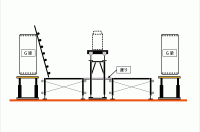





土木技術者として高みを目指すなら技術士を取得するべきです