設計単価が市場に追いついていない
土木業の給与が上がらない原因は、単純に「工事の元請負金額」が安い、この1点のみだと考える。
そして、その理由は3つある。
1つ目は、設計単価が市場に追いついていない点だ。
年々設計単価は上がっているのだが、市場単価も上昇しており、追いかけている状態がここ数年続いている。そのためタイムラグがあり、結果的に合わないのだ。
また役所は市場単価の調査をする際、並行して実勢調査を行っているのだが、この性質が悪い。
「実勢調査」とは、簡単に言うと大手などが大量購入した時の、実際の仕入れ値である。つまり設計された時点で市場単価より安くなっており、最低制限で落札して見積をとると、実行予算が組めない事態に陥る。
(この問題は土木業界の週休2日阻害の一因にもなっているのだが、今回の内容とは少しずれるので、またの機会に触れたいと思う。)
2つ目は、設計者が歩掛をいじってしまう点だ。これは「施工の神様」の他の記事でも度々見かけるが、予算ありきで、ありえない機械設定であったり、標準歩掛では無く独自の積み上げで数量等をいじってしまうケースがある。
そもそも、標準歩掛自体びっくりするほどの好条件で設定されており、第三者等の様々な要因が絡む実際の現場では無理をしないと厳しいのが現状である。
安全と利益を考えた時、誤った判断をしてしまい危険作業の事故が減少しない一因でもある。
直工費と経費の見直しは必須
工事の元請負金額が安い3つ目の原因は、設定工期が適正で無く、それに伴って技術者経費が合わない点だ。
設定工期については言うまでないが、現実に厳しい声しか聞こえてこないのだから、適正とはとても言えない。
技術者は歩掛の中に世話役として入っているのだが、協力業者ごとに上がってくる施工費は、その分を食いつぶしているので、現場管理費、一般管理費等から捻出せざるを得ない。
わからない人は、自分の月給×工期に、本社の経費やその他諸々を組んでみて欲しい。工期が長くなれば、かなり厳しくなるはずだ。
つまり、設定工期を見直すのと同時に、直工費と経費の見直しは必須だろう。


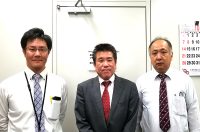







経営者の豪邸を見ると利益がないとはいえない。
例えばどこの会社ですか?><
役所の担当者が数年で変わってしまうのも問題、自分で判断出来るだけの経験が無いから前例を踏襲するしかない。
それはありますね。
癒着の問題等もあるので一概には言えませんが、異動が速すぎて毎年、何もわからない人がくる。
残業するな、休め。結果、工事期間が長くなるから管理費がかさむ。
80点以上の好成績を取れ。結果、創意工夫等の費用がかさむ。
原価を抑えろ、利益をあげろ。
どないせーちゅうねん!
まじで土木ストライキしてやったらええわ
本来、独自の技術力等で工期短縮などが創意工夫ですが、昨今は意味は無いけどとにかく自腹切れば創意工夫みたいな、
本末転倒だねww
全て緊縮財政が悪い
MMT的にはインフレするまで国債はいくらでも発行してもいいのに、財務省が財政を引き締めるから公共工事費も圧縮されるのです。
いっそ公共工事を全廃してこの国のインフラが崩壊すれば国民も財務省の愚かさがわかるのでしょうかね。
役人の目を見るとわかる
国民は直接払っていないから理解できない(しない)。
発注者は自分のお金でないから適当にやる(面倒毎はお任せ)。
元請けは利益を確保できれば十分。
それらのしわ寄せが下請け、孫請けにくるんですね。
そのしわ寄せ対策もしているようですが、効果は微妙。
何のための単価設定なんでしょうね。
まさに表題通り。
実際、工種により、「ハナから無理じゃん。やれるもんならお前やってみろっっ!」てう単価で設定されてることが多すぎます。
他の工種で四苦八苦してなんとか帳尻を合わせていかなくては本当に赤字になってしまう。
厳しい公共工事単価設定と、何それほんとにそれで良い工事できんの?っていう安かろう会社から、自分たちや仲間業者、そして建設業界を守るためだって談合をしてきた人達の気持ちはよく分かりますね。それが良いとは言えないけれど。
良いとは言えないけれど。。。。
うんそうですねー難しいですよね。
このような記事を今後も継続して掲載して頂き、建設業の現状を多くの方に知っていただきたい。
そして、若い人たちが魅力とやりがいと相応の対価の受けられる業界になってほしいと切に願う。
公的市場価格(–物価・–資料)では生コンや鉄は変動しているのだが、10年以上価格を変えてもらえない製品がかなりある。
何度、価格変更を提出しても価格が変わらない。これで設計されるのだから、積算価格より高い販売価格も出てくる。
意図的にやっているのだろうが、こういう仕組みはダメだと思う。
安いのはまだしも、安すぎますからね。
これだと他の業種と競うのは無理ある。
本来利益がでる単価でなければおかしいのに
公共工事は利益を出したら、やれ悪いやつらだの、やれ利権だの言われ
現状は「それどこで買えるの?」ってのが市場単価
結果管理費を削るので管理技術者の給与は上がらず、当然それより責任レベルの低い職人も上がるわけがない。
公共工事は積算資料を用いてまともに積算すると明らかに低入が多発するくらい高値ですけどね。ただし資産管理部署が予算要求の段階で民間価格の安い見積もりを使用するため、発注部署は低くせざるを得ないこともしばしば
底入になるのはそれでできるという事では無く、取れなければ仕事自体が無いから致し方なくが本音です。
現在はコロナもあって発注数は異常に少ないです。
知っていたら申し訳ないですが、災害防止、維持管理系は予算や範囲、日常に支障が出ないように等、長期的また計画的にやる必要があります。
災害がおきてからやればいいでは遅く、またその時に即応できる地場の業者がいなければ言わずともわかると思います。
もちろんそれが全てでは無いですが、低入が発生する原因を間違えておられると感じます。
人手不足→働き方改革→会社赤字→賃金カット→人手不足
市場単価(建設物価調査会)排水構造物の単価の見直しを求める!製品の現場加工がひとくくりで切断含むとなっているが、100mで折れ点12か所ある場合と100m直線の単価が同じなのはおかしい。国交省に意見しても市場単価だからと掛け合わないし、建設物価調査会に言っても全く取り合わない。このような事案が多く請負(請け負ったものが負ける)。現場からの切実な意見を聞き入れず改善をしようとしない。