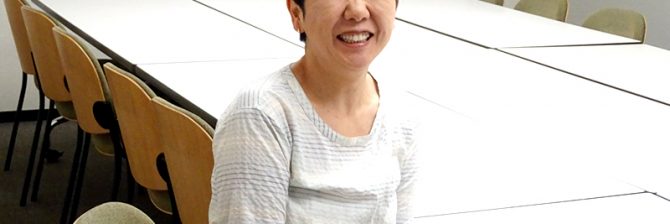土木が女性を拒絶した時代
――最初は就職ではなく大学での研究を希望されていたのですね。
大学時代は、交通行動を確率モデルで表現し分析する研究をしました。研究の楽しさを経験して出来れば大学に残りたいと思っていました。でも、その時に「まだ女性はちょっとね」と言われました。
――企業への就職活動にはそういったイメージがありますが、進学も難しかったのですか。
当時、博士課程に進学するのは留学生だけで、助手になるのが通常のルートでしたので。また、ある方から「うちの大学はまだ女性の助手は無理だ」と言われました。公式見解だったかどうかは不明ですが、当時の私は割と素直に「ああそうなのか」と思いました。今だったら闘っちゃうと思いますけど。
――大学に残れないとなってからの、企業への就活はいかがでしたか。
門戸は全然開いていませんでした。当時の大学には学校推薦という制度がありました。各社から学部は何人、修士は何人と打診があるのですが、女性は取りません、ということは明示的にも言われていました。
就職情報誌、通称「電話帳」は私も含めた理系の女子学生には届きませんでした。この電話帳というのは、各社の情報と資料請求ハガキがまとまっている分厚い冊子です。それが理系の女子学生には来なかった。男子が余らせたものを恵んでもらって、残りの中から探す、そういう時代でしたね。そういう暗黙の拒絶のメッセージと、明確な拒絶のメッセージの中で、「自分を採用してください」と働きかけることは精神的に非常にエネルギーの必要なことでした。
採用の過程でも、毎回、毎回、この次はどうだろうって思っていました。今は違うと思いますが、昔の試験官は本音で話す方が多かったので、「他の女性の手前もあるので、最初の2~3年は事務職として働いて欲しい」と言われることもありました。
――常に、理不尽な圧力がかかった状態だったのですね。
こういうのは子供の虐待と同じだと思います。小さい頃から、女子はあれもダメ、これもダメ、女子は能力がないでしょ、ないよねと言われ続けていると、何となくそうなのかなって刷り込まれてしまう。「君が総合職で就職したら、一人の男子がその職につけなくて泣くんだよ。それでも就職したいの?」って。そういう繰り返しですよね。